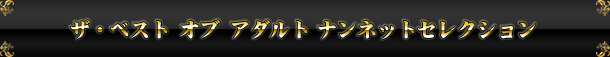2008/09/17 19:58:39
(WmIHrFzd)
クリちゃん剥き剥き、の話題に刺激されたので、栗の話題を少し。生家には
栗の低木がありました。年数かければ大きくなるのでしょうが、二十年程で
切られたと思います。もともと期せずして生えてきたようで、やや家屋にも
近すぎたせいかも知れません。ボクの小学校三年生の頃だったか家の間近に
父が池を作ってくれたことがありました。その折には池の際に栗の木が来る
ように避けてくれたのですが、もっとずっと後、更に家屋を増築する段階で
切られてました。もうボクが京都に行っちゃった後のことです。
ボクが生家でダンゴ三兄弟だったと、たぶん既に言ってあると思います。
たまたまだったが、三人とも「自分の木」なるものを持っていたんですよ。
ボクのは柿でした。ただし、渋柿。もちろん期せずして生えてきたものだと
言うことでした。先の栗の木は次兄のものとされ、さらに4つ下の三男には
葡萄の木が持分とされました。こいつは自生したのでなく、父がどこからか
手に入れてきたものですが、先例に倣ったのでしょう。もちろん、名だけで
採れた収穫はいつも家族で均分していました。ウチの親は横暴じゃなくて、
その辺り、子供にとって最高でしたね。
大阪の能勢の山間部に縁があって御呼ばれしたとき、ついでに裏山にある
クリ畑に案内していただきました。ずいぶんの急斜面で、こんなところでは
オチオチ栗拾いなぞしてられないな、と思った覚えがあります。そんな山で
そこのお爺さんが60kg入った袋を担いで下りたのには頭が下がりました。
田舎の人は偉いもんだと思いましたね。
栗って、昔はもっと重要だったみたいです。青森の三内遺跡には栗の木が
栽培されていたそうです。あんまり貯蔵性がないのは昔も一緒でしょうが。
やはりカロリーを口にできる手段として大切だったんだと思います。縄文は
まだ水耕の技術がなかったので人口もそう増えることがなかったけど、この
遺跡には同時に数百戸の人口が暮していたと推定されるそうです。イネには
陸稲(おかぼ、と呼びます)といって畑で作る方法もあるけど、水耕と違い
収量が少なくて、ムギにも及ばないそうです。そんな頃には栗も今より重要
だったんでしょうね。
久しぶりに栗でも口にしよう、と思って出たのに、けっきょく手に入れて
口にしたのは広東甘栗でした。嗤い話にしかなりませんね、プハハ。
今日、ゆかりさんクリちゃんには、どんな出会いがあったのかナ?