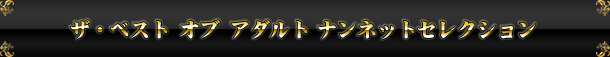2008/09/23 17:34:04
(zZcYYWv0)
ゆかりさん燃焼不全日記、お読みさせていただきました、おかわいそうに。
なぐさめにもならないのでしょうが、童謡「赤とんぼ」について喋ります。
夕焼け小焼けの 赤とんぼ 負われて 見たのは いつの日か
山の畑の 桑の実を 小かごに摘んだは まぼろしか
十五でねえやは 嫁に行き お里の 便りも 絶え果てた
夕焼け小焼けの 赤とんぼ とまっているよ 竿の先
:この歌詞は知ってますよね?「追われて」じゃなくて背負われて、という
意味なのも知ってました?小さい頃、文字抜きで耳からだけ入ってきた時は
「追われて」の意味に理解してました。もう時効かナ?
本題は第三節をめぐっての問題です。
「十五でねえやは 嫁に行き お里の 便りも 絶え果てた」
15歳で嫁に行ったか、むかしは早く行かされたんだな、と思っても、じゃ
なんで「里からの便り」がこないんだ、と疑問に思いませんでしたか?
「負われて」の意味よりもっと深刻な隔絶がここに隠れています。隠す心が
毛頭なかったにもかかわらず、明治生まれの作詞者と今の人間との時代的な
差ができてるためです。
ぱっと見では作者のお姉さんが嫁に行ったと思いそうですが、そう取ると
自分の家から先方にやっちゃった娘なんぞ、いまさら知るもんか、っていう
エラク冷たい家の仕打ちが浮き彫りになります。そんなはずないんですね。
「ねえや」という呼称は「ばあや」と同様、使用人に対する呼称です。この
歌われてる「ねえや」は幼い頃の作者をあやし、一緒に遊んでくれたそして
さして年上でもなかった子守ねえやのことです。
ねえやが他家へ行ったので、実家からときおり届けられてた些細なものが
届けられなくなった、その一抹のさびしさが歌われてるわけです。
子守奉公という言葉もあったように、戦前頃までは幼少時の子供を他家に
あずける奉公制度が慣習として一般的でした。農家などでは子守といっても
広く農作業一般だったろうと推測します。都会では丁稚(でっち)奉公なる
雑用一般の商店勤務があったと思います。本人にとってなかなか厳しい生活
だったと思いますが、他方では、ともかくも子供に最低限の食事を確保して
やる保証でもあったのじゃないか、とボクは考えています。
という辺りはさておき、これまたまだ幼い子守ねえやだったと理解すると
第二節もほぐれてきます。エエ、よく考えるとこれもヘンな歌詞ですョ。
「山の畑の 桑の実を 小かごに摘んだは まぼろしか」
クワの実、食べたことありますか?赤くてきれいなうちは酸っぱいし渋いし
で、とっても喰えたもんじゃありません。甘くなるのは濃い紫から黒っぽい
色に変ってからですが、そうなるとグチャグチャに柔らかくて、食べてると
手が黒っぽくなっちゃいます。実を食べるもんじゃなくて、蚕に食べさせて
養蚕で現金を稼ぎ出す大切な手段として、桑を植えたんですね。
あんな実を摘んでかごに入れるなんて、まだ大きくなってない子のシワザ
ってもんですよ。まァ、おねだりしたのが更に幼少の作者としても、いまだ
子供っぽい雰囲気の抜けない二人のようすが浮かんできますね。
アハ、子宮派ゆかりさんには何の慰めにも、と叱られるかナ?失礼、ペコ