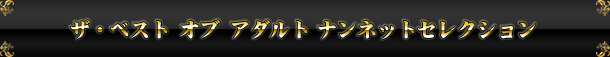2008/09/26 20:23:12
(lwvwoIo9)
そうっか、カラオケなしのハナ金でしたか?残念でしたネ。でも、ああいう
書き込みをしたボクとしては、精一杯のアドバイスに目を留めてもらえて、
その意味では一安心といった複雑な気持ちです。来週ぐらいには、お互い様
いいことがありそうですね。
話が飛びますが、ゆかりさんの生家って関西でも田舎ですか、それとも街
でしたか?いえね、こう尋ねるのは「赤とんぼ」の話のつづきのためです。
第二節「山の畑の 桑の実を 小かごに摘んだは まぼろしか」この中には
むつかしい部分もないと見えるけど、ほぐしてみると『待てよ』って言葉も
あるんです。それは「山の畑」の場所なんです。ま、そま山に入った辺りに
彼の家の桑畑があって、そこへ何かで行った折に桑の実を取ってもらっても
不都合はないんですが、彼自身の意味とは微妙に食い違ってくるかもです。
そまやま、って言葉知ってました?知ってれば田舎の子ですね。杣山って
字を使います。これは「材木を伐採するための山」というのが辞書での意味
ですが、もともとは深山=みやまに対置される言葉で、外山=とやま、とか
端山=はやま、とか呼ばれます。
深山は、みやま以外に「しんざん」とも読まれますが、そう読んだときは
意味も違っています。いや逆に「みやま」と読む方が特殊な意味をかかえる
といった方が正しいかな。「しんざん」は、単に深い山、遠い山、高い山、
行き着くのに大変な山、といった意味ですが、「みやま」は違うんです。
「みやま」には、人が立ち入っちゃいけない領域、といったニュアンスが
含まれています。神の領域、というのが一番なんでしょうね。昔の人の心が
みえてきます。神とその心にかなった動物たちの世界とでも言うところかも
知れない。明治になって外国の登山家が槍や穂高という北アルプスの鋭鋒に
登ろうとしたとき、案内を頼まれた村人達が(猟師や炭焼きの人たちもが)
二の足を踏んだウラには、こういう心があったのです。単に技術的に可能か
不可能かという次元じゃなかったはずですが、文化的にけっきょくは負けた
悲しさ、そうした潤いの部分は歴史の陰に塗りつぶされていったかとボクは
思っています。
それに対して外山や端山は山菜、きのこ、炭、材木など手に入れ、また狩
をする場で、そのかわりの山仕事も色々あったものと思います。ま、ボクも
具体的に知らないので大きいことは言えない。山芋掘りも自力で挑んだこと
ありませんしね、ヘイ。若い頃、京都の北山歩きにずいぶん精を出しました
が、労働には程遠い存在のままでした、ヘヘ。
歌詞に戻り「山の畑」の「やま」は子供の距離感を表わした言葉であって
地形的な「やま」じゃないと思うのです。田舎の人は少し前まで自宅からの
距離感で外部の世界を「いえ」「のきば」「のら」「やま」といった言葉で
区別していただろうと想像しています。そうとすると、露風のこの歌詞での
「山の畑」は地形的には河原にあったかも知れません。ひとこと付け加えて
みたくなりました。へそ曲がりだったかナ?