昭和50年代前半、親元を離れて東京で大学生活を送る私は、父方の大叔父が経営する銭湯でアルバイトをしていた。
仕事内容は日曜・祝日のボイラー業務。
工業高校在学中にボイラー技師の資格を取得していたので結構いい給料が貰え、毎日の風呂代も浮くため、生活は割りと豊かだった。
その頃、都内のアパートに風呂の設備は完備しておらず、利用客は非常に多くて、銭湯経営は儲かる仕事のひとつだった。
儲かる上に番台に座れば素人女の裸を見放題なので、銭湯経営(=番台に座ること)はプロ野球の監督やオーケストラの指揮者と並んで、「男の憧れの職業」にも数えられていた。
番台業務や脱衣場の掃除、洗い場の湯加減調整という一番オイシイ仕事は、大叔父とその息子(父の従兄弟)で独占しているため出番はなかったが、洗い場の奥にあるボイラー室には外から自由に出入りできたので、扉の小窓から女湯の洗い場を好きなだけ覗けた。
お陰で、私と同年代の女子学生や少し年上のOL、出勤前に利用するホステス、子ども連れの若い母親や色っぽい年増の主婦など様々な女性の裸を目のあたりにできた。
ボイラー室は暗いので相手に感づかれることがないのに対し、室内灯に照らされた洗い場は明るく、女性客のヘア、乳房、尻がよく見えた。
当時、ヘアヌードはまだ解禁されていなかったので、童貞の私が女性のヘアを目にしたのはそのときが初めてだった。
目を付けた何名かの利用客をたまに外で見かけると、「服を着てても、オレはアンタの全裸の姿をよく見知ってるんだよ」と思っては、勃起したものだ。
初めはアパートに帰るまでガマンして、帰宅後に思い出しオナニーしていたが、やがて覗きながらその場で生オナニーするようになった。
人生で一番セックスしたい20歳前後の年齢で童貞だったことに加え、女性の生々しいヘアや乳房や尻が目の前にあって異常に興奮するため、放出する精液の量も半端じゃなかった。
それでも、ボイラー室に射精するような真似をしたことはない。
生オナニーを始めた頃はパンツの中にそのまま出していたが、パンツばかりかズボンまで汚れてしまうので、ズボンのチャックを開けてチンポを取り出し、準備してきたチリ紙(当時はティッシュという言葉がまだ一般的ではなかった)の中にするようになった。
大叔父も父の従兄弟も、私がボイラー室の小窓から女湯の洗い場を覗いていることは知っていたはずだが、何も言われなかった。
大らかな人たち、大らかな時代だったと思う。
 (無題) - はじめまして素敵な体ですよ!かわいい声とピチャピチャ音で興奮させてもらってます。 08:45 レス数:72 HOT:71
(無題) - はじめまして素敵な体ですよ!かわいい声とピチャピチャ音で興奮させてもらってます。 08:45 レス数:72 HOT:71 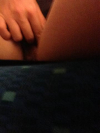 新幹線オナニーしました。 - 西へ来て下さい一日中楽しみましょう新幹線でもホテルでも変態ではしたない貴女をアナ 14:15 レス数:50 HOT:50
新幹線オナニーしました。 - 西へ来て下さい一日中楽しみましょう新幹線でもホテルでも変態ではしたない貴女をアナ 14:15 レス数:50 HOT:50  (無題) - この子動画に移動してますよめちゃくちゃえろい 04:16 レス数:45 HOT:45
(無題) - この子動画に移動してますよめちゃくちゃえろい 04:16 レス数:45 HOT:45  熟女の貸し出し♪ - もう 旦那さんのところに、帰ってきたんですか? 近くなら奥さまをかりたいてます 14:13 レス数:34 HOT:33
熟女の貸し出し♪ - もう 旦那さんのところに、帰ってきたんですか? 近くなら奥さまをかりたいてます 14:13 レス数:34 HOT:33