今から5,6年前のことです。
その頃、まだ結婚しておらず、妻と僕は、僕のワンルームマンションで同棲をしていました。
当時、僕は29歳で不動産の営業を、妻は27歳で美容師をしていました。
職業柄、僕は水曜日、妻は火曜日が休みだったので、なかなか一緒に遊ぶことができず、それだったらいっそのこと一緒に住んじゃおうか?!ということになり同棲生活が始まりました。
なので、たまにどちらかが連休が取れて休みが重なったりすると、朝から晩までイチャイチャして二人の時間を楽しんでいました。
しかし、始めは何もかも新鮮で楽しかったその同棲生活も、二年目を向かえる頃になると、マンネリとういか、お互い慣れみたいなものが出てきて、毎日のようにしていたHも、週に1、2回に減っていました。
そんなある日、僕の会社に一人の新人が配属されてきました。
高校を卒業して田舎から出てきたばかりのそいつは、まさに、右も左も分からないといった状態で、とりあえず僕の下について研修をすることになりました。(その時は、まさかそいつが僕たちのマンネリ生活の起爆剤になるなんて、微塵も思いませんでした。)
そいつの名前は、ケンジ。
田舎もん丸出しのそいつは、名字で呼ぶより下の名前で呼ぶ方がしっくりきました。
そのケンジが配属されて一ヶ月が過ぎた頃、僕たちは仕事終わりに酒を飲みに行きました。
「どうだ、ケンジ。少しは仕事なれてきたか?」
「は、はい。先輩のおかげで少しずつなれてきました。ありがとうございます!」
子どもの頃から野球しかしたことのないケンジは、ちょっと抜けたところはありましが、ドがつくほど素直で可愛い奴でした。
その日、本当は飲んではいけない歳のケンジに人生初のビールを飲ませると、顔を真っ赤にして喜んでいました。
「そういえば、ケンジ、休みの日は何してるんだ?彼女とかいるのか?」
「か、彼女ですか?そんなのいないっす。ずっと空き家です!」
「空き家?ってことは、お前、彼女いないのか?」
不動産業界らしく、”空き家”、というケンジの言い方が可笑しくて、僕はおもわず笑ってしまいました。
「じゃあ、ケンジ、お前、まだあれか?もしかして童貞か?」
「・・・は、はい。。ど、ドウテイっす。」
「ははは。童貞なのか?もしかして、キスもしたことないのか?」
「な、ないっす。キッスもなにも、、女の子の手もさわったこともないです。」
ケンジが赤い顔を、さらに赤くしてそう答えました。
その姿を見ていたら、なんか無性に可笑しくて、僕の中にちょっと悪戯心が湧いてきました。
「そうか、そうだったのか?!じゃあ、ちょっと俺の家に来るか?」
突然の僕の提案にキョトンとするケンジに、あえて同棲している彼女が居るということは言いませんでした。
そして、家に着く前にコンビニでビールやらつまみやらを大量に買い込んで、僕の家に向かいました。
「ただいま~」
「おかえり~」
ドアを開けると、中からいつもの彼女の声がしました。
その瞬間、ケンジは??という顔をして僕の顔を見ました。
「まぁまぁ、いいからあがれよ!お~い、お客さん連れてきたぞ~!」
すると、彼女がちょっと驚いたよう顔をして出てきました。
まさか、お客さんを連れてくるとは思っていなかった彼女は思いっきり油断していました。
「あ、おかえりなさい。。え、え~と。。」
「こいつ、ケンジ。今度、新しく入社した俺の後輩。」
「は、はじめまして。。」
「で、こいつは俺の彼女のチアキ。」
「ど、どうも。。ケンジです。」
突然の紹介に、ケンジとチアキのお互いにドギマギしている感じが、また面白ろくて、僕は思わず笑ってしまいましたが、とりあえず、ケンジを部屋の中に入れました。
「もう、お客さん来るなら、帰ってくる前に言ってくれたら良かったのにっ。」
一つしかないワンルームの部屋の扉を閉めると、チアキは小さな声で僕に言いました。
「だって、急だったんだもん。いいじゃん、どうせチアキも明日休みだろ?」
「そうだけど、、、でも、何もないよ。。」
「いいの、いいの、ちゃんと買ってきたら。ほら、チアキの好きな梅酒も買ってきたよ!」
僕はそう言うと、コンビニの袋をチアキに渡しました。
「そういう問題じゃなくて。。お化粧だって、恰好だってこんな。。」
ユニクロで買ったスエットの上下を着てほっぺを膨らますチアキを無視して、僕は扉のガラスからケンジの方を見ました。
すると、ケンジがベッドの前にちょこんと座っているのが見えました。
ケンジは、律儀にも背筋を伸ばし正座して、まるで固まっているようでした。
その理由はすぐに解りました。ケンジの目線の先には、部屋の中に干してあったチアキの下着があったのです。
うすいグリーンのブラジャーとフリルのついたパンティーがケンジの体を石のように固めていたのです。
チアキは、まだそのことに気が付いてなくて、コンビニの袋からお酒を取り出したりしていました。
なので、僕はそのまま放っておくことにしました。
「まぁいいじゃん、とりあえず、今夜は飲もう!」
僕はスエットに包まれたチアキのお尻を軽くなでると、ビールを二缶持って、ケンジの待つ部屋に入っていきました。
すると、ケンジはそれまで釘付けになっていたチアキの下着から目を逸らし、テレビの方を向きました。
「ん?どうしたケンジ?さぁ、飲もうぜ!」
「は、はい。い、いただきます!」
ケンジの慌てる顔が面白くて、ちょっとからかってやりました。
「あっ、あれか? ケンジ、女の下着も見たことないのか??」
「え、いや、、そういうわけじゃなくて、、す、すみません。。」
「な~んだ、、いいよ。そんなの見せてやるよ。ほら。」
僕はチアキがまだ部屋に入ってこないことをいいことに、ブラジャーを取ってケンジに見せてあげました。
「ほら、可愛いだろこれ。俺が買ってやったんだよ。まぁ、あんまり大きくないけど、Cカップだよ。ほれ。」
「・・・」
僕がケンジに手渡そうとすると、ケンジは困ったような顔をしました。
その時、チアキがつまみを持って部屋に入ってきました。
「ちょっ、ちょっと!!何してるの?!」
「え?これ? ケンジが見たことないっていうからさ。。」
チアキは慌てて僕の方にとんできて、僕の手からブラジャーを奪い取りました。
「いいじゃ~ん。ブラジャーくらい、別に。」
「よ、よくないでしょ。」
チアキはよほど恥ずかしかったのか顔を真っ赤にして、自分のブラジャーをスエットのお腹の部分に隠しました。
そのチアキの恥ずかしがる様子が、なんだかとても新鮮で可愛く見えました。
「わかった、わかった。じゃあとりあえず、乾杯しよう!」
僕はそう言うと、チアキに梅酒をついでやり、とりあえず三人で乾杯をしました。
はじめは訳が分からない、、という顔をしていたチアキも、お酒が入ると徐々に打ち解けてきました。
「え?じゃあ、ケンジさんって、まだ最近まで高校生だったんですか?」
「そ、そうなんです。」
最初は照れてほとんどしゃべれなかったケンジも、少しずつ話せるようになりました。
「チ、チアキさんはおいくつなんですか?」
「え?私ですか? いくつに見えますか?」
「二十、、、二、、三ですか?」
「え?うそ。私、もう二十七ですよ。もう~そんなこと言っても何も出ませんよ♪」
照れて言いながらも、チアキは嬉しそうな顔をしてました。
そのチアキの顔が僕の悪戯心に火をつけました。
「チアキ、こいつね、まだ童貞なんだって。キスも手を握ったこともないんだって。」
「せ、先輩!そ、それは。。」
ケンジは照れて下を向いてしまいました。
その様子がまた、おかしくて、僕は続けて言いました。
「チアキ、さっき『何も出ませんよ』って言ったけど、手くらい握らせてあげたら?!」
「え?手を?」
「そう、手くらい握らせてあげたっていいじゃん。減るもんじゃないし。」
ケンジはうつむいたまま、チアキも自分の手を握りながら、モジモジしています。
「あ?あれ?ケンジ、チアキの手は嫌か?」
僕がちょっと大げさな声で言うと、ケンジは急に顔をあげて言いました。
「い、嫌じゃないです!チ、チアキさんの手、握りたいっす!」
その声に驚いたように、チアキは照れてさらに顔を赤くしました。
僕は昔、付き合い始めた頃のうぶなチアキを見ているようでなんだか嬉しくなりました。
「ほら、チアキ、ケンジの手を握ってあげろよ。」
僕がチアキの手を掴んで、ケンジの手の上に載せるとチアキはケンジの手をそっと握りました。
ケンジは、じっとしています。
「ほら、、ケンジさん困ってるよ。。」
そう言いながら、チアキもケンジ以上に照れて困ったような顔をしています。
そのチアキの顔が可愛くて、さらに、僕を大胆な行動に走らせました。
「ケンジ、そんなんじゃ、いつまでたっても童貞のままだぞ!」
そう言いながら、僕はチアキのことを引き寄せると、チアキにキスをしました。
「もう、ダ、ダメでしょ。。」
そう言いながらもチアキの目がトロンとするのを僕は見逃しませんでした。
そういう僕も、久々にするチアキとの本気のキスに興奮していました。
「ほら、ケンジ、キスってのはこうやってするんだよ。」
こうなったら、もう止まりません。
僕は、チアキのスエットの中に手を入れると、さっき隠したブラジャーを引っ張り出し、ケンジに渡しました。
ケンジはチアキの体温で温められたブラジャーを握りしめながらも、僕とチアキの様子をジッと見ています。
「ほら、チアキのブラジャーを見て喜んでるよ。」
僕がチアキの性感帯の耳元に息を吹きかける言うと、チアキはイヤイヤと首を振りながらも目を閉じています。
「ケンジ、じゃあ、もっと良いものみせてあげるよ。」
僕は、スエットの上からチアキの胸を揉みました。
家に居る時、ブラジャーを付けてないのは知っていましたので、服の上からでも、その大きさと柔らかさは伝わってきます。
「いや、ダメ。。そんなことしたら恥ずかしいよ。。」
恥ずかしい、、言葉ではそう言うチアキでしたが、本気で抵抗する様子はありませんでした。
逆に、今までに見せたことの無いような、淫靡な様子に僕の興奮は加速しました。
「ケンジ、、ほら、これがチアキのオッパイ。」
僕はチアキの後ろにまわると、チアキのふくらんだ胸の形を強調するようにケンジに向かって押し出して見せました。
そして、僕はそのてっぺんにある、左右二つの乳首を服の上から親指と人差し指でつまんで見せました。
「あっ、うん。。ダ、ダメだって。。」
スエットの上からでもくっきりと見える二つのお豆を、ケンジはまさに目を点にして見つめています。
「ケンジ、どうだ?いいだろこのオッパイ?」
「は、、はい。最高っす。。」
「ケンジさん、やだ、、見ちゃダメ。。」
チアキは恥ずかしいのを隠すためか、終始目をつむって、後ろにいる僕の方に顔を向けました。
僕はそのチアキのくちびるにキスをしながら、胸を揉み続けました。
「チアキ、、ケンジは童貞なんだって。。だから、チアキの可愛いオッパイ見せてあげようよ。」
「い、いや、、、」
「いやなの?見せてあげちゃダメ?」
「だって、、ケンジさんだって、私の胸なんて見たくないよ。。」
チアキは、そう吐息を吐くように言いながら、僕の顔を見ました。
「じゃあ、ケンジが見たいなら、見せてあげても良い?」
「・・・」
まさか、こんな展開になるとは思っていなかった僕は、逆にドキドキしてケンジに聞きました。
「ケンジ、チアキのオッパイ、、見たい? それとも、見たくない?」
「・・・み、、見たいっす。。」
その瞬間、はぁ~とチアキが甘いと息を吐きながら、僕のくちびるに吸い付いてきました。
僕は、そのチアキの反応を体で直に感じ、今までにない、興奮に襲われました。
自分しか見ることがないと思っていたチアキの体を自分以外の男に見られ、そして、その男とどうにかなっているところを想像すると、その妄想と衝動を抑えきれなくなってしまいました。
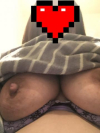 朝からムラムラ - 1番最初に投稿されたのから見ましたが魅力的なおっぱいですね♥️特に乳首や乳輪の大 15:54 レス数:139 HOT:32
朝からムラムラ - 1番最初に投稿されたのから見ましたが魅力的なおっぱいですね♥️特に乳首や乳輪の大 15:54 レス数:139 HOT:32  指示 - コスプレはありませんか?チアとか 20:57 レス数:26 HOT:25 ↑
指示 - コスプレはありませんか?チアとか 20:57 レス数:26 HOT:25 ↑ (無題) - 今夜は少しだけ特別な気分で心地よい時間をご一緒できたら嬉しいです☺️ 20:29 レス数:19 HOT:19
(無題) - 今夜は少しだけ特別な気分で心地よい時間をご一緒できたら嬉しいです☺️ 20:29 レス数:19 HOT:19