私が住んでいた街は、日本屈指の歓楽街を有する地方都市だった。
最新の風俗街が居を構える一方で、昭和のノスタルジーな雰囲気を残す旅籠屋街も多く残っていた。
昔で言う赤線、青線地帯だ。旅籠屋やラブホテルが乱立したその地域は昼間から立ちんぼや不倫カップルが行き交っており、初めて通るものでも、淫らな空気に酔ってしまう、そんな場所であった。
私の祖母の家は、自宅からその街を越えたしばらく先にあり、小学生高学年にもなると、性への興味とその街が持つ大人の気配に、胸を高揚させ、ドキドキしながら通ったものであった。
ある日、いつもの通り祖母の家に向かう道すがら、ある旅籠屋の入口の脇に、30代前後の女性が立っていた。
女性と目が合うと、彼女はにっこりと微笑み、まだ小学6年生であった私に手招きをした。
女「僕、かわいいなぁ。こんなところでなんしよん?」
私「おばあちゃん家に行くとこ。」
女「そうなん?おばあちゃん家は近いの?こっちにおいで、ジュース買ってあげるよ。」
女はそう言うと自販機でジュースを買い、私に与えた。
知らない女からジュースをもらうという事と、子供ながらこの街に警戒はしていたものの、女のにっこり笑った表情と優しい声に、警戒心は緩み、私はジュースを受け取った。
女はまゆみと名乗ったが、私が何をしているのかという問いかけには無言で微笑んでいた。
まゆみ「僕みたいな子、かわいくて好きなんよ。良かったら仲良くして。」
当時の私は、坊ちゃん刈りにTシャツ短パンと、子供の男の子そのままの格好で、顔も童顔だったので、一部の女子にはモテていた。
屈託なく話しかけてくるまゆみに私は心を許して、座ってジュースを飲んでいた。
まゆみとはたわいのない話を交わしていたが、不意にまゆみが僕の手を取り、旅籠屋の裏に手を引いて連れて行った。
まゆみ「僕かわいいから、サービスしてあげるね。」
まゆみはそう言うと、しゃがんで私の唇に唇を重ねてきた。
キスなんてしたことない私は咄嗟に避けようとしたが、まゆみは私の頭をガシッと掴み、さらに唇を押しつけると、舌を唇の間に差し込み、強引に私の口内を舐め回した。
恐怖と恥ずかしさと突然の状況に頭は混乱したが、口内を艶かしく動き回る舌を絡められ、舌をしゃぶられ、唾液を吸われる快感に、身体の力は抜け、頭はボーッとし、私は獣に貪られる獲物のようにただ力無くそこに立ち尽くし、ただひたすらに口をしゃぶられ吸われた。
数十分だろうか。
まゆみが満足するまで吸われたのち、私の唇は解放された。まゆみの目はトロンとなりながらも奥底に獰猛な光を宿していた。
まゆみ「たまらんわ。もう、たまらんわ。堪忍してね
。」
まゆみはそう言うと私の短パンに手を突っ込み、まだ未発達の私の蕾をぎゅっと握りながら、首筋と耳に舌を這わせた。
まゆみに舌を吸われてボーッとしていた私はさらに与えられる快感に動くことができなかった。
頭はカッカし、心臓は爆発しそうになっている中で、生き物のように這い回るまゆみの舌に、ただ味合われるだけの存在としてそこに立っていた。
まゆみ「かわいい僕が反応してる。」
まゆみは嬉しそうにそう言うと、短パンのボタンとチャックを下ろし、パンツを下げた。
まゆみは無言で顔を埋め、私の蕾を口に含むと、強く吸った。
私「あっ!!」
まゆみ「ほら、剥けた。かわいい頭が出てきた。」
まゆみはそう言うと剥けたばかりの私の亀頭をおしゃぶりを吸うように吸いたてた。
私「あっ、あぁぁぁ、あっ!」
上下するまゆみの頭を押しのけようとすればできたはずなのに、私にはその快感を跳ね除ける勇気を持ち合わせてはいなかった。
なすがままに私は蕾を味合われ、まゆみの生き物のようにうねる舌と私の蕾の奥にあるものを吸い出されようとする動きに耐えられず、まゆみに精を吸われた。
精を吸われてからも、まゆみは私の蕾を口から離すことは無く、延々と舐めてはしゃぶり、吸われた。
四度目の射精の後、薄くなって既に精液ですら無くなった体液を吸い終わると、まゆみは私の蕾を解放した。
そのまま、また唇を長く吸われ、既に力無い抜け殻のような私を見て、まゆみは満足したようで。
まゆみ「平日の昼間はここにいるからね。」
と言った。
私は恐怖と喜びと、蕾がまだ吸われているかのような鈍い感覚を覚えながら、走って逃げ去った。
怖くて、走りながら涙が出てきたのを覚えている。
その後、無事祖母の家に着いたが、まゆみのことは誰にも言わなかった。
そうこうして、数ヶ月が過ぎた頃、私はまた同じ道を歩いていた。頭ではいけないと分かりつつも、あの日目覚めた、自分の中の男に導かれるように、あの旅籠屋の前に行った。
まゆみは私に気づくとにっこりと笑い、手招きした。
私は自ら、まゆみの後を追い、旅籠屋の裏の茂みに入って行った。
~ 完 ~
 彼撮り動画 - ごゆっくり、おやすみくださいませ… 23:45 レス数:104 HOT:49
彼撮り動画 - ごゆっくり、おやすみくださいませ… 23:45 レス数:104 HOT:49  どうですか? - ちせちゃんの乳輪舐め回したいわ 01:21 レス数:29 HOT:24
どうですか? - ちせちゃんの乳輪舐め回したいわ 01:21 レス数:29 HOT:24 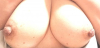 (*ˊ˘ˋ*)。♪:*° - 桃花さんのコメントは優しくて可愛くてエッチだから、反応が返ってくるとこちらはだい 03:04 レス数:19 HOT:19 ↑↑↑
(*ˊ˘ˋ*)。♪:*° - 桃花さんのコメントは優しくて可愛くてエッチだから、反応が返ってくるとこちらはだい 03:04 レス数:19 HOT:19 ↑↑↑ どんな方がみてるんだろう・・・ - この人は、本物のスケベ女です。ぜひ見ましょう。 22:23 レス数:56 HOT:18
どんな方がみてるんだろう・・・ - この人は、本物のスケベ女です。ぜひ見ましょう。 22:23 レス数:56 HOT:18  52歳おばさんです - 出遅れました相変わらず最高です 00:39 レス数:16 HOT:16
52歳おばさんです - 出遅れました相変わらず最高です 00:39 レス数:16 HOT:16