ある日、いつものように学校から帰って玄関の鍵を開けようと
ポケットの鍵を取り出そうとすると、
すすり泣く声が聞こえてきた。
ふと顔を上げて、向かいの家をみると、美和さんが後ろ向きになって
るのが見えた。
小さな庭に入り、濡れ縁まで近づくと、
美和さんは、横座りになって肩を落として畳を見つめ、泣いていた。
どきどきした。見てはいけないものを見てしまった気がした。
シオンちゃんは今日はいないようで、
静かな家の中には、時々洟をすする音が響いていた。
見て見ぬ振りしようと、後ろずさろうとしたら、
「ケン君?」と、後ろ向きのまま声を掛けられた。
「うん」
「おかえり」
「ただいま」
「・・・・」
「・・・・」
悲しい気持ちが声に出てて、たまらなくなった。
畳にあがり、膝をすりながら、すぐ傍に近づいた。
下を見ると、畳がぽたぽた落ちる涙で濡れていた。
「おねえ、ちゃん?・・・」
耳がきーんと鳴っているように感じた。
こんな時、大人はどうするのだろう?
頭の中はぐるぐる回るばかりで何もわからない。
なにかすることを探して、見つけたように
何も思いつかない自分に言い訳するように
小さい子供が泣くのをなだめるみたいに、
手のひらで背中を上下にそっと撫でた。
ゆっくり撫でているうちに、
しゃくりあげるような泣き声が聞こえだして、
美和さん、くしゃくしゃの顔をして静かに泣いていた。
大きな瞳が濡れてて、長いまつげにしたたり、ああ綺麗だなと思った。
そんな事を考えてる自分に、むっとして、僕は黙って
しばらくの間、できるだけ優しく、背中を撫でていた。
竿竹屋さんの売り声が通りから聞こえてきた。
ふと、彼女は向きを変えて、こちらを向いた。
いきなり、彼女は僕を抱きしめてた。
膝立ちになって、ぎゅっとしているから、
僕の頭は美和さんの両腕が回されて胸に押し付けられてた。
美和さんは、声を出してわんわん泣いていた。
心臓が止まりそうだった。
白いTシャツの下の、柔らかな、だけど弾き返されそうな胸に、
僕の顔が埋まってた。
どれくらいなのか、見当もつかないくらい時間が過ぎた。
僕はどきどきしていた。頬っぺたに、たぶん乳首の感触・・・
いつも真っ白なTシャツにくっきり浮かんでいた、あの乳首が頬に当たって
る。
美和さんが悲しんでいることも忘れ、僕はくらくらしていた。
「ありがとうね」
どれくらいたった頃か、そう美和さんは囁いた。
静かに美和さんは抱擁を解いて、僕の両頬を手のひらで挟み、顔を覗き込ん
だ。
「えっちな事、考えてたでしょ」
美和さんは、涙だらけの顔で、微笑みながら言った。
「考えてないよ」
「うそ」
「うそじゃない」
「うそ」
「うそじゃない」
「うそついてもおねえちゃんにはわかっちゃうんだぞ」
「なんで?」
見透かされて戸惑いながら、なぜばれたかわからずポカンとしていると、
「こ、れ、」
と、僕のジーパンのチャックを指差した。
「おっきくなってるもん」
テントが張っていた。
 寝る前に - こちらこそありがとうね。気持ちよくいけた?だらしないデカ乳だたくさん絞ってまだま 01:10 レス数:67 HOT:67
寝る前に - こちらこそありがとうね。気持ちよくいけた?だらしないデカ乳だたくさん絞ってまだま 01:10 レス数:67 HOT:67  今日のパンティ - いい食い込みだねこんどはワレメに食い込ませて! 01:34 レス数:17 HOT:17 ↑↑↑
今日のパンティ - いい食い込みだねこんどはワレメに食い込ませて! 01:34 レス数:17 HOT:17 ↑↑↑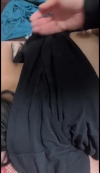 嫁に悪遊 - 某サイトで拝見してます!僕もそこの住人です!黄色 ryo5163 です。是非とも 00:16 レス数:16 HOT:15
嫁に悪遊 - 某サイトで拝見してます!僕もそこの住人です!黄色 ryo5163 です。是非とも 00:16 レス数:16 HOT:15