第二十三章
「あれ以来、すべてに自信がもてるようになったというか、ラグビーもそうですし、美佐に対してもそうです。」
昨夜の妻との情事に思いを馳せていた私は、田中君の言葉で我に返りました。
彼女とよりを戻せたことは妻も私もメールで聞いて知っていました。
「そう、よかった」
妻は顔を赤らめ答えます。彼女が田中君とのセックスを思い出していたのか、その後の私とのそれを思い出していたのかは知る由がありません。
「昨日、国体の選抜チームに選ばれたって連絡がありまして、今日はその報告も兼ねてお邪魔しました」
「すごいじゃない、おめでとう」
あれから三ヶ月以上たつのにも関わらず、妻の「すごい」という言葉に反応して心臓の鼓動が大きくなってしまいます。
「よかったじゃないか、おめでとう」
努めて平静を装い私も祝福の言葉をかけました。
「ありがとうございます」
「そう言ってくれれば、もっとお祝いらしい食事を用意したのに」
「いえ、これでも十分なご馳走です」
「そうだ、少しいいワインがあったはずだわ。持ってくる」
「そんな、お食事だけでも十分です。それにお礼をしなければいけないのは僕のほうなのに」
「それとこれとは別よ。それに私だってすごく嬉しいの。あなただって、ねぇ」
「うん、うちの大学から国体に選ばれるなんて、たぶん創部以来はじめてのことだと思う。君は学校にとってもそうだが、私たちにとっても誇りだよ」
これは私の本心から出た言葉でした。あの夜抱いた嫉妬心は、その後、妻との絆をより深く感じることで、今や彼に対する深い感謝に昇華していたからです。
「そんな、お二人が僕のために、お体を張ってくださったから。なのに、そんなことまで言っていただいて。」
彼の両目から大粒の涙が溢れ出しました。妻の太もも程もある太い袖で顔を拭きながら、肩を震わせながらむせび泣く彼に、妻はもらい泣きしています。
「体を張ったのは妻だけなんだけどな」とは言わず、私も胸が熱くなるのを感じました。
「さぁ、せっかくのめでたい席なんだから、湿っぽいのはよそう。田中君も、泣くのは国体チームでレギュラーになって、天皇杯を取ったときにしろ、な?」
「はい」
尚も規格外の量の涙で頬を濡らし続ける彼に、私はボトルを差し出しました。
※元投稿はこちら >>
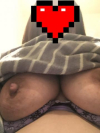 朝からムラムラ - もう終わりかな?いない? 12:59 レス数:40 HOT:38
朝からムラムラ - もう終わりかな?いない? 12:59 レス数:40 HOT:38  おデブでも可愛い熟女 - ありますよ。ぽっちゃりさんは抱き心地も良くて大好きです 12:45 レス数:35 HOT:25
おデブでも可愛い熟女 - ありますよ。ぽっちゃりさんは抱き心地も良くて大好きです 12:45 レス数:35 HOT:25  指示 - すじまんですけど、m字とかは、、個別のやりとりでもいいですか?( 13:29 レス数:15 HOT:14 ↑↑
指示 - すじまんですけど、m字とかは、、個別のやりとりでもいいですか?( 13:29 レス数:15 HOT:14 ↑↑