第二十一章
下半身に強い疼きを覚えて、意識を取り戻しました。
薄く目を開けると、私は白い人影に組み伏せられているようです。
意識がはっきりするにつれて、それが裸の妻であることがわかりました。
そして、妻と私の下半身が繋がっていることに気づくと同時に、なにか普段と違う心地よさを感じ、鳥肌が立ちました。
その理由が、固くなった私自身に絡みつく、妻の粘膜の熱、そして触感にあることを認識した私は、戸惑いながらカラカラに渇いた口を開きました。
「由美、田中君は」
「一時間くらい前に帰ったわ」
時計を見上げるとお昼を過ぎています。
後から妻に聞いた話では、ちょうど私が目にした辺りが最終盤だったようで、あの後、二人は眠りにつき、昼前に起きた彼は、何度もお礼を言いながら帰宅したということでした。
久しぶりに味わう妻の生々しい感触に、早くも果てそうになりながら会話を続けます。
「そうか、それで、どうしたんだ」
「どうしたって、なにが?」
「おまえがこんなことするのが、初めてのことだし、それに、つけてないだろう?」
「うん、つけてない。だめ?」
「だって、もう子供はいいって、おまえが言ったんだろ」
「そう、だっけ」
「そうだよ、ううっ」
結婚してから数年間、子宝に恵まれないことに悩んだ時期もありました。
しかし、元々私も妻もそれほど強く子供を望んでいたわけではありませんでしたし、世間でよく聞くお互いの両親からのプレッシャーがなかったこともあって、不妊治療を受けたりはしませんでした。
できないものはしょうがない。
二人ともそう思っていました。
結婚後十年以上がたち、お互いに三十台半ばを迎えたころから、それまでつけていなかった避妊具を使用するようになりました。
提案したのは妻からでした。
「今からできちゃったら、かえって大変だと思うの。子供を欲しいという気持ちがまったく無いわけじゃないけど、お互いの立場を考えたら、これから子育てするっていうのはリスクのほうが大きいんじゃないかって。なにより、私、今のままで十分幸せだわ」
妻の考えには十分な説得力がありましたので私もそれに賛同し、以来セックスの際には必ずゴムを着用するようになっていました。
ですから、数年ぶりに生で味わう妻の蜜壷の感触に、快楽を感じるより先に戸惑いを覚えてしまったのです。
両手を私の胸板に乗せたまま、前後左右に腰を動かし続けます。
ベッドに膝立ちになっていた姿勢を改め、蹲踞のような体勢で両足を大きく開き上半身を上下させ始めます。
より深い挿入感が得られるようになりました。
「ああ、由美、いいよ、よすぎる」
「あなた、私も、いいの」
「ごめん、もういきそうだ」
「ああ、私も、いく、いっちゃう。ねぇお願い、一緒に」
「ああ、もうだめだ、いくよ」
「ああっ」
妻は私の上に倒れこみました。
互いの両腕、両足を絡め、強く抱きしめ合います。
私の首筋を、熱い液体が濡らすのを感じました。
妻の涙でした。
「あなた、ごめんなさい」
「いいよ」
「あんなことになるなんて、思ってなくて」
「いいんだよ、元は俺から言い出したことだ」
「ごめんなさい。嫌いになった」
「いや」
「ほんとに」
「ああ、むしろ前より好きになった」
「ああ、あなた」
「由美」
「また、大きくなってきたわ。もう一回、抱いてくれる」
私は無言で妻を抱きしめる腕により力をこめると、きつく唇を重ねました。
妻の中で再び勢いを取り戻す自分自身を感じながら、言いようのない充足感と虚無感とが私の中で交錯していました。
これで終わった。私たち夫婦にとって初めての、そして最後の寝取られ体験が。
そのときは確かにそう思っていました。
※元投稿はこちら >>
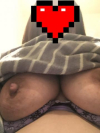 朝からムラムラ - 乳首甘噛みしたいですね〜 11:40 レス数:36 HOT:34 ↑
朝からムラムラ - 乳首甘噛みしたいですね〜 11:40 レス数:36 HOT:34 ↑ おデブでも可愛い熟女 - 最高じゃないですか!羨ましいです 10:28 レス数:34 HOT:26
おデブでも可愛い熟女 - 最高じゃないですか!羨ましいです 10:28 レス数:34 HOT:26  おじの指示 - 変態野郎を見て何が面白いんだかww 11:44 レス数:14 HOT:14 ↑
おじの指示 - 変態野郎を見て何が面白いんだかww 11:44 レス数:14 HOT:14 ↑