人妻を寝取られた屈辱。愛するがゆえに寝取らせた旦那。ヒトの女の寝取りの記録。様々なNTR体験談が投稿される掲示板。
1: 巨根のラガーマンに寝取られた妻
投稿者:
sinn9nnn
◆MCbX1O.Cg.

よく読まれている体験談
嫁の浮気寝取らせ・妻の浮気実況報告 23698view
2016/02/26 00:41:11(gYRLqwRG)
実話だろうと創作だろうとどうでもよいですが、楽しんでいる人だけが訪れればよいのではと思います。???を代表に、作者の意欲をなくすような発言は控えて頂きたい。自己満足だけする独りよがりなオナニストはここにはいりません。
私の楽しみを邪魔しないでください。
期待して待ってる人は大勢います。少なくとも私は日々楽しみにしてます。がんばってください。
16/03/17 12:46
(0A2xzNvc)
投稿者:
sinn9nnn
◆MCbX1O.Cg.
第二十三章
「あれ以来、すべてに自信がもてるようになったというか、ラグビーもそうですし、美佐に対してもそうです。」
昨夜の妻との情事に思いを馳せていた私は、田中君の言葉で我に返りました。
彼女とよりを戻せたことは妻も私もメールで聞いて知っていました。
「そう、よかった」
妻は顔を赤らめ答えます。彼女が田中君とのセックスを思い出していたのか、その後の私とのそれを思い出していたのかは知る由がありません。
「昨日、国体の選抜チームに選ばれたって連絡がありまして、今日はその報告も兼ねてお邪魔しました」
「すごいじゃない、おめでとう」
あれから三ヶ月以上たつのにも関わらず、妻の「すごい」という言葉に反応して心臓の鼓動が大きくなってしまいます。
「よかったじゃないか、おめでとう」
努めて平静を装い私も祝福の言葉をかけました。
「ありがとうございます」
「そう言ってくれれば、もっとお祝いらしい食事を用意したのに」
「いえ、これでも十分なご馳走です」
「そうだ、少しいいワインがあったはずだわ。持ってくる」
「そんな、お食事だけでも十分です。それにお礼をしなければいけないのは僕のほうなのに」
「それとこれとは別よ。それに私だってすごく嬉しいの。あなただって、ねぇ」
「うん、うちの大学から国体に選ばれるなんて、たぶん創部以来はじめてのことだと思う。君は学校にとってもそうだが、私たちにとっても誇りだよ」
これは私の本心から出た言葉でした。あの夜抱いた嫉妬心は、その後、妻との絆をより深く感じることで、今や彼に対する深い感謝に昇華していたからです。
「そんな、お二人が僕のために、お体を張ってくださったから。なのに、そんなことまで言っていただいて。」
彼の両目から大粒の涙が溢れ出しました。妻の太もも程もある太い袖で顔を拭きながら、肩を震わせながらむせび泣く彼に、妻はもらい泣きしています。
「体を張ったのは妻だけなんだけどな」とは言わず、私も胸が熱くなるのを感じました。
「さぁ、せっかくのめでたい席なんだから、湿っぽいのはよそう。田中君も、泣くのは国体チームでレギュラーになって、天皇杯を取ったときにしろ、な?」
「はい」
尚も規格外の量の涙で頬を濡らし続ける彼に、私はボトルを差し出しました。
16/03/17 22:37
(.9qR9zvs)
続きありがとうございます。いつもドキドキ興奮しながら読ませていただいてます。毎回楽しみにしています。続きがあるならお願いしますね!
16/03/18 08:20
(4Wz4v/2J)
大学の教務課に勤めて、ラクビー部の副顧問の貴方が…田中君が国体のメンバーに選ばれたのを知らないなんて…ストーリー的にどうなんでしょうね?
16/03/18 09:35
(ytH/1rqF)
投稿者:
sinn9nnn
◆MCbX1O.Cg.
第二十四章
その後の田中君の活躍はめざましいものでした。
本来の資質を開花させた彼は国体チームでも中心選手となり、本大会でも決して前評判の高くなかった本県選抜チームをベスト4に導く原動力となりました。さらに、その活躍が認められ、ユニバーシアード七人制日本代表の選考合宿に呼ばれるまでになったのです。
私と妻は彼の試合を欠かさず観戦に行くようになっていました。
そして一試合ごとに成長していく彼の雄姿を我が事のように喜びました。
彼の生活は一変し、多忙を極めるようになってからは、我が家へ来ることもほとんどなくなっていきました。
私も妻も寂しさを感じてはいましたが、それは同時に彼がラガーマンとして順調に成功への階段を駆け上がっていることの裏返しでもあったので、気持ちの折り合いをつけて彼の応援に没頭しました。
田中君にとっての飛躍のシーズンは瞬く間に過ぎ、再び春を迎えました。
突然、彼から電話があったのは大学の春季休暇を目前にした頃でした。
大学の食堂で昼食をとっていたときです。
「お久しぶりです」
「おう、どうした。代表の海外遠征中じゃなかったのかい」
「一昨日、帰国しました。昨日こちらに戻ってきたところです」
「ああ、そうだったのか。疲れたろう、どうだったい、海外遠征は」
「はい、おかげさまで、怪我することもなく、無事に。それで、あの突然で申し訳ないのですが、西村さん、今日か明日の夜、お時間とっていただけませんか?」
「ん、ああ、いいよ。久しぶりだから嫁も喜ぶと思う。今から連絡とってみて、都合がつくようなら今日でもいいよ」
「いえ、その、できれば、外で。二人でお会いしたいのですが」
「それは構わないけど」
田中君の声色にただならぬものを感じ、電話を切った後、少し心が粟立ちました。
16/03/18 21:16
(UocwU4uE)
お?
以前伏線として登場していた彼女さんの登場かな??
個人的には奥さんがまたガッツリやられちゃう話も聞きたいし。
色々な書き込みがありますが、気にせず続きお願いします!
16/03/18 23:27
(GCnSAmJF)
投稿者:
sinn9nnn
◆MCbX1O.Cg.
第二十四章「これ、おみやげです。あまり時間がなくて、気の利いたものが買えなかったのですが」「ありがとう、ただでさえ忙しい遠征中に気をつかってもらって悪かったね」いつものショットバーのカウンター席。田中君は深緑色の紙袋を私に手渡すと、前置きもなく今日のお題に話を移しました。「あの、実は、美佐とのことなんですが」「ああ、彼女も寂しがってるだろう。僕たちのことは気にせず、もっと時間を作ってあげたらいいのに」「昨日、代表チームが解散した後、まっすぐ彼女のアパートに行きました」「そうか」そこで何かがあったであろうことは話の流れから想像がついたのですが、軽く相槌をうち話の続きを促しました。「それで、その、久しぶりだったのと、海外遠征ですごく刺激を受けたのとで気分が昂ぶっていまして」「刺激って、まさかお前、オーストラリアのパツキンお姉ちゃんにじゃないだろうな」とは言いませんでした。ラグビーの世界レベルを知ったということなのはすぐにわかりましたし、なにより、彼の様子は冗談を言うのが憚られるほど沈んで見えたからです。「結論から言います。実は、僕、美佐にお二人とのことを話してしまいました」口に含んだシングルモルトを噴き出しそうになり、慌てて飲み込むと今度は激しく咳き込んでしまいました。チェイサーのグラスをつかむと一気にを呷り、落ち着いたところで彼に向き直り尋ねます。「嘘だろ」「ほんとにすいません」「それは。食事のことじゃなくて、つまり、あの夜のこと」「すいません」彼が深く頭を下げるのですが、そもそも座高が違うので、私は見上げる格好のまま腕を組んでため息を漏らします。「それは、そうか、うーん、しかし、それは」「ほんとに、何て言ってお詫びしていいか、すいません」彼は肩を震わせ頭を下げたまま謝罪の言葉を繰り返します。「まぁ、それは、わかった。それで?彼女の反応はどうだったんだい?」ようやく顔を上げた彼の両目は潤み、その上の極太の眉毛を八の字に垂れ下げた表情の弱弱しいことといったらこの上ありません。グラウンド上で見せる、敵に噛み付かんばかりの野獣のような表情を知っている私からすれば、同じ人物とは思えませんでした。知り合った当初の、消え入るような声で話を続けます。「実は彼女、前からおかしいとは思っていたようなんです。僕の、変わりようっていうか、急に自信をもった態度をとるようになったことを」「うん、まぁ、それは彼女じゃなくてもそう思ったやつは多いかもな」「もちろん、そのことについて聞かれても僕は答えをはぐらかしていたんです。ただ昨日は彼女を抱いた後、久しぶりのお酒で酔っていたこともあって、気が大きくなっていたというか。いや、こんなこと言い訳にしかなりません、すいません」「いや、済んだことはもういいよ。それで、そのことを聞いた彼女はなんて言ったんだい?」「怒りました」「そりゃ、そうだろうなぁ。」彼女が怒りにまかせて、このことを口外してしまうのではないか。真っ先に心配したのはそのことです。しかし、話は予想外の方向へと進んでいきました。「怒るには怒ったんですが、その、彼女は『ずるい』って言うんです」「んん?」「つまり、僕が、いわゆる浮気をしたことを『自分ばっかりずるい』ってことなんです。でも、西村さんもご存知のとおり、あの時は彼女から別れを告げられた後でした。厳密に言えば、浮気でもなんでもないんです。だから、そのことも話したんですけど聞く耳をもたなくて。」「それで?」「その、大変申し上げにくいことなんですが、彼女の言い分としては、自分にも同じことをさせろってことなんです」すぐには彼の言っていることが理解できませんでした。初めは、彼が外国で怪しげなカルトの宗教にでも染まってきたのかと思ったくらいです。「えーと、ちょっと、ちょっと待ってくれ。それは、つまり、私と君と、君の彼女の三人で、ってことか?」他に客はいませんでしたが、マスターの視線を気にして、小声で答えました。「いえ、それが、その、少し違ってまして」私に合わせて、声のトーンを低くした彼が、肩をひそめて話します。「どう、違うの?」「奥さん、西村さんの奥さんも一緒にって」「ええ?それは、おかしくないか?君の彼女は何を考えてるんだ?」「そうですよね、そう思いますよね。西村さんからそういう言葉がでることは彼女も予想していました。それで、もしよかったら、今度、直接、彼女から話を聞いてもらえませんか」「彼女と?電話で?」「いえ、日を改めて別の場所で。西村さんが今日、この場で拒否されないようなら、自分の口から説明したいってことなんです」私は大きく息を吐き出しながら、リキュールグラスの中に残るラガブーリン16年に視線を落としました。
...省略されました。
16/03/19 20:57
(dzSm8UJJ)
さすがに無理な展開や。期待しとったのに(笑)
16/03/19 21:13
(k1BUeh.s)
回りからの非難を気にせず、楽しく読ませて頂きましたが…やっぱり無理でしたか。上の方が言うように、展開に無理がありましたね。
16/03/19 21:34
(FCOKIL2e)
sinn9nnnさん、楽しく拝読しています。次の展開も楽しみです。よろしくお願いします
16/03/20 12:17
(wFD0rB8Q)
新着投稿
動画投稿
体験談
官能小説
人気投稿
 勢いのあるスレッド
勢いのあるスレッド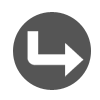 新着レス
新着レス
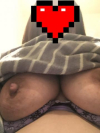 朝からムラムラ - 乳首甘噛みしたいですね〜 11:40 レス数:36 HOT:34 ↑
朝からムラムラ - 乳首甘噛みしたいですね〜 11:40 レス数:36 HOT:34 ↑ おデブでも可愛い熟女 - 最高じゃないですか!羨ましいです 10:28 レス数:34 HOT:26
おデブでも可愛い熟女 - 最高じゃないですか!羨ましいです 10:28 レス数:34 HOT:26  おじの指示 - 変態野郎を見て何が面白いんだかww 11:44 レス数:14 HOT:14 ↑
おじの指示 - 変態野郎を見て何が面白いんだかww 11:44 レス数:14 HOT:14 ↑