女の一生に一度の痛みの筈だった。
春は、心の中で母を思いながら、敵国の将校の一物を、本当なら結婚するまで清い筈の秘密の部屋に迎えようとしていた。
ハーレーの一物は巨大だった。
意識して受け入れようとするが、どうしても本能的な恐怖と憎しみが頭に浮かぶ。
ハーレーも、自分の巨大な一物を持て余していた。
「うーん、やっぱりお前には大き過ぎるか。」
無理やり犯せる立場なのに、一度は春の身体を心配したのは、既にハーレーが春に対して、便利のよい道具と言う以上の感情を持っていたからかもしれない。
「申し訳ありません。マスター。
あの、あの、良かったらなんですが..」
春は顔を赤くして吃り吃りハーレーに言った。
「もしマスターがよろしかったら、あの写真の女の子みたいに、わたしを後ろから可愛がってくださいませんか?」
あの写真の女の子とは、春が初めてハーレーのお仕置きを受ける原因になった、ハーレーの収集した変態写真の中の一枚だった。
その写真には、多分春と同じくらいの年齢の金髪お下げの少女が、全裸でベッドに四つん這いのような姿勢にされ、両手を前でベッドの枠に縛られてる姿が写されていた。
しかもその後ろに、これも巨大な一物を勃起させた白人の大男が迫っている。
つまりこの少女は、縛られてバックから犯されるわけだ。
春は、自分をその写真の少女のようにしてくれ、と言っているのだ。
ハーレーはまだ幾らか残っている理性で春を見つめ、
「本当に、良いのか?」
と尋ねた。
春は恥ずかしそうに両手で顔を覆って、
「マスター。ごめんなさい。
私、マスターに可愛がってもらいたいのに、マスターのあれを見て、情けないけど怖いって思ってしまいました。
後ろからなら、多分恐くありません。
でも、卑怯な私が逃げないように、手も縛っていただけると、嬉しいです..。」
よし、分かった。
これも、神様の思し召しかもしれない。
いつも下っぱで情けない思いをして心が歪んだ俺に、天使が生まれ変わって恵みを与えてくれてるのかもしれん!
ハーレーは春の両手を革紐でベッドの頭の部分に縛りつけた。
春は両膝で体重を支えながら、鞭で赤く腫れたお尻をハーレーの方に向けた。
ハーレーの大きな両手が、細い春の腰に掛かる。
ハーレーの一物は、春の膣口に当てられた。
グイッと引き付けられた。
同時に春は、膣口がメリメリと裂けた音が聞こえた気がしたが、それから意識は真っ暗な闇に沈んでいった。
気が付くと、行為は終わっていた。
一物を血だらけにしたハーレーが、不器用に春の手首の革紐を解いているところだった。
下半身がズキズキと激しく痛んだ。
何故か吐き気もするし、頭痛も激しい。
しかし、任務を果たさなければ..。
手首を解かれた春は、すぐに起き上がって洗面所に急いだ。
動く度に、下半身、特に割れ目がズキズキ痛んだ。
それでも苦痛を顔に出さず、お湯に浸けたタオルを絞ってベッドに戻り、春の徐々に喪失で血だらけになったハーレーの一物を拭き清めた。
「春、お前の身体は..」
気を使ってくれるハーレーに、
「マスター、ありがとうございます。
春は本当にうれしいです!」
と感謝の言葉を返す。
「もう俺は良い。
お前、自分の身体を洗ってこい。」
ハーレーから言われて、春はわずかの水で自分の下半身を拭き清めたが、破られた処女膜からの出血はまだ止まらなかった。
仕方なく春は、股間に布を挟んでハーレーのところに酒を運んで行った。
ハーレーは感動していた。
この日本人の少女は、本当に俺に処女をくれた。
かなりの痛みの筈なのに、健気に俺の世話を先にするなんて!
もうこの少女を手離しはしないぞ。
結婚は出来ないが、ずっと側に置いてやる。
「春。さあ、今夜は俺のベッドで一緒に寝よう。
心配するな。もう今夜はしないから。」
春は迷っている様子だ。
「あの、私のような目下の者が、マスターと一緒に休むなんて..」
「良いから来い。可愛いやつめ。」
そう言われた途端、春はハーレーの胸に飛び込むと、顔を押し付けながらこう言った。
「優しい..、優しい..、私のマスター..。」
翌日から、ハーレーは官舎の中では、春に対して妻に準じた扱いをしようとした。
しかし、春は控えめな態度とメイドとしての分をわきまえて、殆ど以前と変わらなかった。
良い服を買ってやろうとしても、
「着る機会がありません。
それより、マスターがお喜びになる物をお買いください。」
と遠慮する。
ある時、あまり宜しくない中国人商人から、フランスのキャバレー等のショーガールが身に付ける、スパンコール付きのパンティーを手に入れた。
あの清楚な春に、これを穿かせたら、恥ずかし過ぎて泣くのではないか?
ほんのいたずら心だったが、帰って春に手渡すと、一度は顔を真っ赤にして別室に下がったが、やがてそのパンティー一枚の裸体でハーレーの前に姿を現した。
「いかがでしょうか?
やはり、似合いませんか?」
と羞恥で顔を赤らめた少女は、いやらしい筈のなのに、とても美しく思えた。
それからは、いやらしい下着だけでなく、春に似合いそうな可愛い服を買っては、それを着せた春をお供にしてシンガポールの街を歩くことも増えた。
そして知人に会う度に、春を自慢した。
ハーレーの春に対する信頼は際限無かった。
極秘の書類でも、数字が絡む難しい物なら、持ち帰って春に計算させた。
時には官舎に忘れた重要書類を、春に届けさせることまでさせた。
同僚達の中には、他国の女の子に対して無用心だと言う者もいたが、「春は英語は喋れるが、読み書きは出来ないんだ。」と言い訳した。
幸い上司である司令官からは何も言われなかった。
※元投稿はこちら >>
 おデブでも可愛い熟女 - 臭そうなブタやからって、業者が入ってきたらあかんやろ! 21:25 レス数:93 HOT:56 ↑↑↑
おデブでも可愛い熟女 - 臭そうなブタやからって、業者が入ってきたらあかんやろ! 21:25 レス数:93 HOT:56 ↑↑↑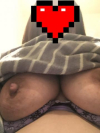 朝からムラムラ - 1番最初に投稿されたのから見ましたが魅力的なおっぱいですね♥️特に乳首や乳輪の大 15:54 レス数:139 HOT:32
朝からムラムラ - 1番最初に投稿されたのから見ましたが魅力的なおっぱいですね♥️特に乳首や乳輪の大 15:54 レス数:139 HOT:32  指示 - コスプレはありませんか?チアとか 20:57 レス数:26 HOT:25
指示 - コスプレはありませんか?チアとか 20:57 レス数:26 HOT:25