床に正座して話を聞いていたはるは、あろうことか、自分の股間か熱く濡れきているのに気がついた。
殿様のご命令で、この身を切り取られ、料理されて食される..。
それを思うと、はるは恍惚となりかけた。
「おやっ、そちはこんな話を聞いても恐がらぬのか?」
ますます殿様は面白そうだった。
「あの時は、余はドライの乳首を食した。
なかなか良い味、歯応えであった。」
ドライはふーっとため息をついた。
今は無い乳房、乳首が興奮で膨らみ、硬くなるかのような錯覚までした。
フュンフは、目下の者からはドライ様と違って冷酷で恐ろしい、感情がない、と言われている。
しかし、今殿様が直々にあの時の話をするのを聞いて、自然に目頭が熱くなった。
殿様が、そのフュンフの方を向くと
「またあの客人が来たら、もう片方の乳房をご馳走するかな?」
と聞いた。
フュンフは答えた。
「もし、許されますならば..、乳房だけではなく、この身を全て食して頂きたく..。」
殿様は今度はドライに聞く。
「それではそちの相棒がおらぬようになるな。」
ドライは感情の籠らぬ声になるように努力して答えた。
「畏れながら、フュンフはまだ若く美しく、しかも利発。
それに対し、私はすでに盛りを越えました。
一度は殿様のご寵愛を頂いた身が、老いさらばえるのは辛ろうございます。」
「つまりは、フュンフではなく自分を食してくれ、と言うことか?」
「畏れいります。」
面白がっている殿様の声だけが明るく、あとの二人の声は一切の感情を込めない冷たい口調にと努めてはいるが、膝まずいて聞いているはるは、天使同士が話しているかのような尊さを感じた。
殿様がドライとフュンフを側に来らせ、片方づつの乳首を摘まみ弄った。
「その方らの乳首を触るのも久しぶりだが..」
二人は冷静な表情を保って直立している。
殿様がドライの乳首を強くつねった。
ドライの表情は変わらない。
しかし殿様は
「ほう、やはりまだ硬くなるではないか!」
と言うと、今度はフュンフの乳首を噛んだ。
一度強く噛んで口を離すと
「どうだ、このまま余が噛み千切ってやろうか?」
と言い、再び強く噛み始めた。
フュンフの目から涙が落ち、冷たい表情が溶けかけて恍惚となってきている。
しばらく片方だけのフュンフの乳首を噛んだ後、殿様は二人に命じた。
「余が許す。ここで二人で楽しむがよい。」
二人は殿様のベッドからやや離れた床に下がり
、そこで殿様に深く一礼すると、お互いの下半身を覆っていた布地を脱がせ、そして抱き合いキスを交わした。
床に倒れ、お互いの腕を相手の背中に回し、硬く抱き締め、まさぐり会う。
二人の仲は、もともと演技から始まった。
殿様から、レズビアンをせよ、と命じられて、殿様の前で奴隷の義務として演技を披露していた。
それが数年しての今は、心から相手の身体が欲しいと思う。
しかし、殿様の所有物である自分達は、勝手に殿様以外の者に好意を抱き、ましてや肉体的な快感を求めようなどはしてはならないことである。
事実二人が密かに抱き合ったことは、一度もなかった。
それが今は、殿様から許されて、大好きなあの人と抱き合える。
畏れ多く勿体ないこと、と思いながら、二人は硬い床の上で、激しく求めあった。
それを見ながら、殿様ははるを側に呼びつけた。
ガウンの裾を捲って一物を出し、それをはるに口で慰めるように命じる。
はるは、小さな口を開け、分からないながらも必死に唇と舌を使って殿様をお慰めした。
床の二人は、殿様が見てくださっているのを意識しながらだったが、感情も高まっていた。
時々小声だが、お互いの名前を呼ぶ。
殿様にしてみれば、いつも冷静で鋭利な二人が、このような生々しい姿になるのを見れるのは自分の前だけだと言う満足感も味わえた。
二人の喘ぎとうわ言が聞こえる。
「お姉さま、だめ..、一人で死なないで..」
「フュンフ、貴女もなの..?」
「どうか、どうか一緒に..」
「そうね、一緒に..、殿様のために...」
はるは自分の口の中の殿様が、さらに巨大化し逞しくなったように思えた。
何度かはるの歯が殿様の一物に当たった。
「ああ、許されないことだわ..」
しかし、はるは殿様から受けるであろう罰を恐れるより、ドライとフュンフの妙なる喘ぎと呟きのように、殿様が甘美な死を与えてくれることを思い、萎縮することなく殿様が快楽に浸れるように努力した。
殿様の射精を受け、それを勿体ないことと感じながら、全てを飲み下した。
さらに習ってもいないのに、やや硬さを弱めた殿様の一物を、自分の舌で清めることも出来た。
気がつくと、床の二人は行為を終え、床に並んで正座し、はるが殿様の一物をお世話しているのを見守っていた。
殿様が「もう、良い」とはるを退けると、二人は深々と土下座した。
「お見苦しいものをお見せして、申し訳ございません..。」
立ち上がった殿様は満足げであった。
「たまには、このような趣向も良いな。」
まるで子犬の頭を撫でるかのように、はるの頭を撫でると
「そちは不思議なやつだな。
余を口で満足させた者は少ない。」
と言った。
そしてまた二人に向かい
「余は今晩はもう荒れないと思うぞ。
ごく普通の奴隷、家畜で良い。
二人ほど連れてまいれ。」
と命じた。
※元投稿はこちら >>
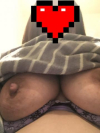 朝からムラムラ - 1番最初に投稿されたのから見ましたが魅力的なおっぱいですね♥️特に乳首や乳輪の大 15:54 レス数:67 HOT:41 ↑
朝からムラムラ - 1番最初に投稿されたのから見ましたが魅力的なおっぱいですね♥️特に乳首や乳輪の大 15:54 レス数:67 HOT:41 ↑ 指示 - めっちゃ人気じゃん! 14:33 レス数:22 HOT:21
指示 - めっちゃ人気じゃん! 14:33 レス数:22 HOT:21