殿様が身を引き、はるとの間に距離を取った。ヒュン!
鞭を空振りする音がした。
『ああ、始まるんだ。
きっと私の身体、ズタズタにされるんだ。』
空気が鳴り、はるの脇腹の皮膚が裂けた。
殿様の鞭は、連続してはるの柔らかな肌を襲った。
背中、胸、脇腹、腹、下腹、尻、太股!
鞭の先端は太股に巻き付き、柔らかな内股まで赤い線が付いた。
胸の一番繊細な乳首も直撃された。
逃げようにも逃げられない。
吊られたはるの身体は、ぐるぐると回転した。
しばらくして、殿様の手が止まった。
はるの身体の回転も止まり、正面に殿様の身体があった。
『殿様、息を整えておられるみたい..。』
普通の少女なら、そんな事など考えるゆとりは無かっただろう。
それだけ、はるは特別だったのかもしれない。
また鞭が飛ぶ音がして、逆さに吊られて上を向いてるはるの股間、割れ目を鞭が直撃した。
はるは、自分の身体が激しくのけ反ったのは覚えている。
その後、意識に空白があった。
『これが、気絶なの..?
私、悲鳴を上げたのかしら?』
そう思ったと同時に
「今ので何発目かわかるか?」
と殿様の声が聞こえた。
「55回目でございます。」
はる自身が驚いたことに、はるは殿様の質問に答えることが出来た。
また殿様の声がする。
「大したものだな。
悲鳴も上げずに、ちゃんと打たれた回数まで数えていたか。」
どうやら、気を失ったのはほんの瞬間で、悲鳴を上げずに済んだらしい。
「下ろしてやれ。
いや、その前にリングを着けよ。
その後で夜伽を命じる。」
二人の召し使いが最敬礼するのが、逆さの視界の隅に見えた。
年上の召し使いが、手に尖った錐のような物を持って近づいてくる。
膝を折って座ると姿勢を低くし、はるの顔を覗き込んだ。
「まだ気を抜いてはだめ。
これから左の乳首に穴を開けて、金のリングを通す。」
はるの左の小さな乳首は、鞭の直撃を受けて皮膚が裂け血が出ていた。
それにも関わらず、召し使いは高濃度のアルコールで周囲を消毒した。
はるは、跳び跳ねるようにのけ反ったが、必死に悲鳴をこらえた。
召し使いは、はるの息が整うまで、錐を乳首に突き立てるのを待ってくれた。
若い召し使いが、はるの身体を揺れないように押さえ、年上の召し使いが鋭い錐の先端をはるの乳首に当てている。
「刺すよ。」
年上の召し使いが、そう告げた。
これまで彼女が乳首に穴を開けた少女の殆どは、穴を開けられると告げると、諦めてはいるものの、やはりやめて欲しいと言うかのように、ふるふると顔を振り、泣きそうな顔をしたものだった。
それを見ながら、「私は悪魔だから..」と自分に言い聞かせながら、彼女は少女達の乳首を刺してきた。
このはると名付けられた少女も、自分の乳首に付けられたリングを見るたびに、私を怨むのだろう。
そう思って、今一度はるの顔を見た。
はるの顔は泣いてはいなかった。
固くはあるが、微笑んだのだ。
そして吊られて逆さになった顔を上に向け、自分の乳首に当てられた錐をしっかりと見た。
召し使いが手に力を込め、錐がはるの乳首を貫いた時も、目を閉じることなく見続けた。
わざと苦痛を与えるためのリングを嵌めるには、錐を乳首に貫通させただけではなく、その錐をグリグリと回転させては抜き取り、また貫くのを繰り返すと言う野蛮な方法が取られている。
殿様は、その時に流れる少女の苦痛の叫びがお気に入りだった。
鞭に耐えた者でも、これで叫ばない者はいなかった。
だから、乳首貫通の拷問で叫ぶ少女に対しては、お気に入りのおもちゃとして、寛大に扱ったつもりである。
悲鳴を上げたからと言って、すぐに屠殺処分にすることはしなかった。
このはると言う家畜は、どの程度叫ぶであろうか?
殿様は非常に興味深かった。
しかし、
※元投稿はこちら >>
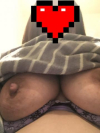 朝からムラムラ - 1番最初に投稿されたのから見ましたが魅力的なおっぱいですね♥️特に乳首や乳輪の大 15:54 レス数:67 HOT:41 ↑
朝からムラムラ - 1番最初に投稿されたのから見ましたが魅力的なおっぱいですね♥️特に乳首や乳輪の大 15:54 レス数:67 HOT:41 ↑ 指示 - めっちゃ人気じゃん! 14:33 レス数:22 HOT:21
指示 - めっちゃ人気じゃん! 14:33 レス数:22 HOT:21