射精が終わり僕の動きが止まると、希星は「終わったの?」と聞いた。
「うん」
「…そう。シャワー浴びてくるね」
「ああ」
希星はフラフラと立ち上がり、浴室に入った。すると暫くして、洗濯機が回る音が聞こえてきた。
不審に思って脱衣所を見たが、希星の脱いだ服がない。僕は浴室の外から
「着てたの、全部洗ったのか?」と聞いた
「…うん。そのまま帰ったら、ママにバレちゃうから」
「…親とか、警察に言うんじゃないのか?」
「あなたのこと、警察や裁判所に、渡したくない」
この希星の言葉に、僕は今までと違う雰囲気を感じたが、真意を聞く勇気がなかった。
「…乾くまで、どうするんだ?」
「布団に潜ってる。シーツ替えてくれないかな」
「いいよ」
僕は、血と精液で汚れたシーツを剥いで、新しいのを敷いておいてやった。
浴室から出てくると、バスタオルを身体に巻いた希星は布団に潜り、僕に背を向けて静かに肩を震わせ始めた。
僕はその横に座り、黙って見ていることしかできなかった。
やがて服の乾燥が終わると、希星は布団から出てきた。そこで僕はやっと
「どうするんだ?俺のこと」と聞いた。
「家に帰って考えてみる。今夜電話するから、出てね」
そう答えると、洗い終わった服を着て、隠れ家から出て行った。
その夜、僕は自分の部屋でソワソワしながら、希星からの電話を待った。
電話が来る代わりに、警察が迎えに来るのかも知れない。一応、それも覚悟していた。
すると7時過ぎ、家電に掛かってきた。
母が応対し、子機を持って僕の部屋に来た。
「あの子なんだけど、出る?」
これまで何度も僕は、希星からの電話に出ず、母に断ってもらった。
「ああ、出るよ」
「ほんとに?」
母は怪訝な顔をしながら、子機を僕に渡した。
「優太君?」
「うん」
「…なんとか、気付かれずに済んだ」
「そうか…なんで言わない?」
「私の初めての相手が、犯罪者だなんて、悲しすぎるから」
「いいのか?」
「その代わり…ねぇ、私の彼氏になってくれない?」
僕は絶句した。あの希星がこんなことを言い出すのは、何か訳があるに決まってる。だがそれを聞くよりも、不登校になる前からの、希星への反発心が先に立った。
「やだよ!俺、お前のこと好きじゃねぇもん!」
「なんでよ?いいじゃない!私これでも結構モテるんだよ?」
「知ってるよ!でも俺は、お前の何でも全力でやろうとする所が、ニガテだ!」
「…私が、合わせるから。これからは、もっと、気楽に…」
僕は耳を疑った。あの希星が、まさか…
僕はようやく、希星の話を聞く気になった。
「俺を彼氏にして…どうするんだ?」
「…私は前から、あなたのことが好きだった。でも、あなたの前では素直になれなくて…」
希星は急に、少女マンガのようなことを話し出した。だがそれを真に受けるほど、僕も単純じゃない。黙って続きを聞いた。
「だから今日、あなたに強引に迫られて、許してしまった。ホントはちゃんと、告白してからそうなりたかったんだけど」
「…そう、思い込むことにしたのか?」
「うん。そうじゃなかったら、悲しすぎるから」
「でもそれは、お前が嫌いな、ゴマカシになるんじゃないのか?」
「…それでもいいの。今回だけは…」
「いやでも、それは…」
僕が口ごもっていると、急に希星の声が震えだした。
「お願い、やり直しさせて…じゃないと私…」
泣き落としだ。だが僕の方にも、怒りにまかせて希星の大事なものを奪ってしまった罪悪感が、少しはあったので、これ以上無碍に拒絶することはできなかった。
「…友達から、でもいいか?」
「ほんとに?うん、それでいい」
「じゃあ…」
「ねえ、そしたらさっそく友達っぽいことしよう!」
「なにを?」僕は嫌な予感がした。
「明日朝、迎えに行くから、学校へ行こう!不登校の原因の私と友達になったんだから、行けるよね?」
「…来てもらうのはいいけど、玄関から出られないかも」
「そうなの?」
「実は、何度か試したんだ。出ようとすると足が動かなくなって」
「それでもいいよ。私がそうしたいんだから、ね?」
電話を切って、母に子機を返しに行くと
「どうだった?」と聞いてきた。
僕が明日、希星に迎えに来てもらう約束をしたと話すと
「行けそうなの?」と聞いた。
「分からない。玄関からは出られないかも」
「そういう気持になれただけでもえらいわよ!がんばって!」と返す母の声は、感激で震えていた。
不登校になるのも楽じゃないが、復帰するのも楽じゃなかった。
※元投稿はこちら >>
 ご主人様、皆様 - じゃあしよう。 05:37 レス数:114 HOT:109 ↑↑↑
ご主人様、皆様 - じゃあしよう。 05:37 レス数:114 HOT:109 ↑↑↑ わお - もっと見たいなー 黄色きてmoko0415 04:56 レス数:85 HOT:84
わお - もっと見たいなー 黄色きてmoko0415 04:56 レス数:85 HOT:84  (無題) - パイチンは嫌い? 01:17 レス数:70 HOT:69
(無題) - パイチンは嫌い? 01:17 レス数:70 HOT:69 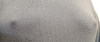 (無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:32
(無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:32