「やっと、終わらせてやったぞ…。」
出張先の対応に苦慮し、ようやく開放された僕は、客先を後にした瞬間、目立たぬようにガッツポーズをして、理不尽な客の対応を滲ませた言葉が口から出た。
ただ、朝風呂の件で終始集中を欠いた僕の対応不足もあったが、そんなこと僕にはどうでもよかった。
現在20時半をまわり、ホテルに着くのは21時を超えるだろう。
初日に大浴場でユカを見かけた時間より遥かに遅く、チャンスと思っていた今夜に一抹の不安を覚えた。
まず、あの家族が今夜も泊まっているかさえ確認していないわけなので、希望的観測も甚だしいばかりであった。
それでも、ユカともう一度会いたいという思いは強く、ホテルへトンボ返りすると、フロントで鍵を受け取り、何を思ったのか大浴場のほうへ足を進めた。
普段からストーカー事件の記事を見るたびに、よくもまぁこんなモチベーションになれるよな、などと感じていた僕は、ようやくストーカーの気持ちを理解したのではないかと感じた。
大浴場の入り口には、そこにスリッパはなく、部屋に戻ろうとしたとき、小さなゲームコーナーがあることに気がついた。
そこからは、大浴場の入り口を見ることができた。
だめもとで、あそこで待ってみるか。
明日は移動日のため多少の寝不足はかまわない。
部屋に戻り、部屋着に着替えた僕は小銭とともに、なかばあきらめモードでゲームコーナーにあるビデオゲームを始めた。
時折、大浴場の方へ目をやるが、静止画のような景色は変わることなく、育成ゲームの少女だけがすくすくと育っていくばかりだった。
小銭も尽きてきたころ、遠くの方からスリッパの音が聞こえた。
咄嗟にゲーム機の後ろに隠れ、様子を伺っていると、なんと待望のユカが父親と共に現れた。
一気に鼓動が早くなった僕は、あくまで偶然を装うため、はやる気持ちを抑えながら5分ほど遅れて大浴場へ足を進めた。
ゲームは終了することもなく放置されていたため、画面の中の少女に見送られ、応援されているように感じた。
暖簾をくぐると、当たり前のように、スリッパが二つ。
脱衣カゴにはユカの抜け殻が温もりを保った状態で存在していた。
今日は、黄色いパーカーか…。
変な感傷に浸りながら、温もりが消えぬよう、ユカの肌着をそっと持ち上げ、すぐさま顔を埋めた。
おそらくはこれが最後の花園になると思い、悔いのないほど、ゆっくり吸っては、顔を離して吐き、吸っては吐きを数回繰り返した。
汗の匂いがほとんどなく、さわやかな石鹸の香りのようなものが鼻孔を満たし、汚れなき少女の偶像が閉じた目の前にはっきりと現れたかのようだった。
はやる息子を落ち着かせ、深呼吸をしながら浴室へと入っていくと、今まさに、内湯から露天風呂へと移動しようとしている二人がいた。
僕はかけ湯をして、まずは内湯に入り様子を伺いながら、移動するタイミングを図った。
外からは中がよく見えるだろうと思い、注視することをやめ、横目で神経を研ぎ澄ませながら、あらゆるシミュレーションを練っていた。
そしてついに動きがあった。
父親は露天風呂の縁に腰掛け涼むようになり、それをきっかけに僕は露天風呂へと移動することを決めた。
数パターンのシミュレーションを引っさげて、露天への扉を開けて、はじめて自ら親子の方へ歩み寄りを始めた。
あくまで自然に、避けることなく一直線に親子が入る露天風呂へ歩を進め、勝負をかけた。
このときすでにユカと目があったことを確認したが、後ろ姿で座る父親の存在が僕を萎縮させ、同時に息子まで萎縮していた。
でなければ、こんな一直線に向かう選択など取りはしなかった。
近づくにつれてユカは次第に唇を甘噛しながら湯面に視線を落としていた。
状況が急展開したのは、僕が露天風呂に入る段に足をかけたときだった。
「お兄さん、お疲れさま。」
一瞬動きを止めてしまうくらい、少女の父親から突然に声をかけられた。
「あっ、お疲れさまです…。」
予想外の声かけに、ぎこちない声と笑顔で対応するのがやっとだったが、ほろ酔いの父親は機嫌も良く、僕が肩まで浸かるまでの短時間にも、いろいろと話しかけられることになった。
その話によると、家族旅行で来たこと、明日が最終日であること、そして再婚したばかりだと言うことだった。
それらの話しをしている時もずっとユカはうつむきながらも、僕の方をちらちらと見ている状況が続き、僕自身も父親の話は半分、ユカへの意識を常に持ってた。
その話半分で聞いていたの話の中でも、ユカが男湯に入っている理由が見えてきた。
それは、父親の最後の話題である再婚したばかりということが関係していそうだ。
ユカはこの父親の連れ子で、まだ新しい母親に慣れておらず、一緒に風呂に行くことを拒んでいるようだった。
僕はやっと、身体に似合わず男湯に入っていたことが、腑に落ちた。
といっても、親父だったら、止めようよ、とは思った。
その流れで、僕も自身の仕事の事などを話すことで、父親には信頼してもらえたようで、いろいろと話しを聞かせてもらうことになった。
そんな中、父親は朝風呂での光景を繰り返すかのように、露天風呂から上がり、ユカに声をかけた。
「さて、サウナ行ってくるかな。ユカはどうする?」
そうすると、首を素早く無言で横に振る、ユカ。
その想定通りの姿を見て父親が笑うように、ユカはサウナが得意ではないのかもしれない。
確かに小さい頃は僕もそうだった記憶がある。
「お兄ちゃん、一緒にどうだい?」
弾む話題の途中、咄嗟に誘われたが、断る理由もないためご一緒しようかと思ったが、朝のことを思い出し、
「すみません、実は、僕もちょっと苦手で…」
そういうと苦笑いを見せると、父親はまたもや笑いながら、最近の若い奴はというノリで、内湯の方へ鼻歌交じりで向かっていった。
父親は内湯に入る扉を開けたところで、僕の方を振り返り、何やらニヤつきながら、言葉を発した。
「じゃあ、お兄ちゃん、ユカ見といてね。のぼせないように~」
そのつもりではいましたが、いざ父親から言われると、公認をもらったかのように、あらゆる事が頭の中を走り回った。
同時にユカの方へ目を配ると、口まで湯船に沈みながら、こちらへ目線を向けていた。
も〜!お父さんったら!
そう言いたそうな、視線を僕に向けながら、口から息を吐きだし、ブクブクと可愛い姿を見せていた。
父親がサウナに入るのを僕が確認していると、ユカも横目で確認していたらしく、二人してもう誰の目も我々を見ていないことを共に確信した。
しばらくの沈黙の後、僕は満を持して、ユカに声をかけた。
今まで接触はあったものの、ちゃんと声をかけるのはこれが初めてだった。
「こんばんは、ユカちゃんって言うんだね。何回かお風呂で会ってるよね?かわいいから覚えちゃったよ。」
後から考えると、この百点満点の変態発言にも、ユカは今までの事を思い出しているのか、恥ずかしそうに目線を落とし、より激しく口でぶくぶくと空気を出して反応を見せていた。
少し離れた位置だったため、ゆっくりと父親がいたところまで僕は移動をはじめ、その間もどこに観光に行ったのかなど、何ともない会話を進めていたが、それ以上に今後の展開について思考を巡らせていたのは言うまでもなかった。
距離にして2メートルといったところだろうか。内湯を背にしてユカに対面する位置に到着した。
先程まで、父親の存在に萎縮していた息子は、すでに興奮の頂にあり、揺れる湯面の下にはいつ露わになってもユカの目線を釘付けにできる準備が整っていた。
いろいろときっかけを考えたが、自然な流れにしようと、特に伝えることをせず、先ほどまで父親が座っていた露天風呂の縁にゆっくりと体を引き上げ、ユカの目の高さになるように、重力に逆いそびえ立つ注目の的を露わにした。
初めて内風呂で見せたときと同じシチュエーションだったが、距離は半分以下、外のため湯気もほとんどなく、ユカの瞳と息子の間には、邪魔するものは殆ど無かった。
想定の通り、湯船から目の高さに来るまでの間も、ユカの目線はある一点を追いかけるように動いていることを僕は確認していた。
そして対面すると同時に、これまで湯面につけていた口元は、お湯から離れ半開きになり、目は今までにないくらい大きくなっていた。
「気になる?」
我慢ができなくなり、ユカの注目の的の話題について僕は切り出した。
「えっ、あっ、あのぉ。」
いままで凝視していたユカの目線が泳ぎ、言葉にならない反応が帰ってきた。
主語はないが、お互いの思うところは共通していただろう。
この言葉だけで十分だった。
「ごめんね、いきなりだったもんね。あまりこの状態を見たことないだろうから、気になっちゃうよね。」
ユカは、すこしハッとした表情を見せたが、今まで半開きだった口ははにかむようにきゅっと結び、コクンと頷いた。
僕はおもむろに息子に手をやり、今朝鏡越しで不鮮明だっただろう動きを、目の前でして見せた。
根本から先まで大きくグラインドさせる動きは、あくまでユカに向けたパフォーマンスであって、自ら果てるための動きではなかった。
しかしながら、その気になって動かしたのならば、今すぐにでも果ててしまいそうな興奮を覚えていた。
「今朝、ユカちゃんの後ろで、こんな動きしてたんだけど分かってたかな?」
「うん、何してるのかなって。気になってた…あっ、ました。」
緊張しながら、丁寧語に直すあたり、可愛くて仕方がない。
続きを見せるにはもう少し打ち解けないといけないと思った。
「ははっ、そんなに緊張してかしこまらなくてもいいよ。お兄ちゃんだと思ってさ。」
「はっ、はい…。」
「んっ?」
「あっ、うん…。」
ユカは、そうラフに答えたことが恥ずかしかったのか、嬉しかったのか、またもや口までお湯につけ、ブクブクブクと空気を吐き出していた。
たまらなく可愛い。
僕のバロメーターは、瞬間跳ね上がりを見せた。
ユカはブクブクさせながらも、間違いなくすべての意識が視力で捕らえる目の前の光景に支配されているような目をしていた。
そのため、跳ね上がった瞬間、眉が上がり、目玉をあちこちに動かして動揺を見せていた。
このやり取りで僕が聞いたユカの声は、年並のハリがあり、眼の前にいるのは確実に少女なのだと確信できるものだった。
その声に僕の息子は再度、ビクンと大きく脈打ちをした。
ただ、内湯から見えないように背を向けているせいで、そり立つ息子は明るいわけではなかった。
不鮮明ではないが、光量と距離が見せつけたいと願う僕の目的には達していなかった。
そこで手を動かしながらもあたりを確認すると、露天風呂スペースは以外と広く、奥の方に木で作られた樽風呂のようなものが見えた。
そこは内湯からも見にくく、しかもライトアップのようにスポット照明も上からあった。
そこへ行きたい。
そう思うと同時に、僕は行動に移していた。
「ユカちゃん、あっちのお風呂に入ってみようか。」
立ち上がると同時に、僕はユカへ手を伸ばしていた。
股間に曲がらぬ信念を持つ男の差し出すその手が、ただの違うお風呂に誘われている以上の意味が有ることはきっと分かっていただろう。
一瞬の躊躇があったが、これまで湯船にずっと入っていた、手が僕の方へ伸びてきた。
その手をつかむとゆっくりと立ち上がるユカは、スレンダーながら、膨らみを持った体を露わにした。
初めての接触と至近距離で対面するこの状況に、ここで行動を起こしそうになったが、ぐっと我慢し、移動するという目的を遂行した。
「滑らないように気をつけてね。」
「うん、ありがと、キャッ」
一歩目のタイルで足を滑らせたユカは、僕の腕に両手で捕まる形になり、いままでの緊張する顔とは別の顔を見せた。
よっぽど焦ったのだろうが、その顔がまた可愛かった。
「ほら、きをつけてっていったのにー。」
そう、からかうと、ユカは声を上げて笑い出した。
「だって、いろいろ緊張してたんだもん!」
「たとえば?」
「えっ、んー、裸見られちゃったとか!」
「えー、いままでも普通に見てたのにー?」
「もー、いいの!」
そう言うとユカは微笑むのを我慢するかのように、ツヤツヤのほっぺをプクッと膨らませた。
いまのアクシデントで緊張がほぐれたのか、年並のかわいい反応が帰ってきた。
僕は膝を落としたユカを引っ張り上げると、まるで町中を歩くカップルのように、腕を腰に回した。
ユカにしてみれば、初めてのことだったのかもしれない。
背中を反らし、驚いたような反応を見せたが、僕にしてみても、こんなすべやかで、ハリのある生腰を支えたことなどなかった。
肌から伝わる情報すべてが、オスの本能を直接刺激し、驚きで固まるユカの目線の下では、鍛えられた名刀のように、光り輝く亀頭が内湯の光に映し出されていた。
そんなことを知る由もないユカを樽風呂へエスコートする際、自然とユカの腰を自分に引き寄せ、腕のみならず、自らの腰や脇腹、太ももで少女の素肌を感じ取っていた。
その引き寄せる強さに驚いたのか、ユカは腰を引きつつ、二人して樽風呂までの道のりを歩いた。
数メーターの距離だが、何度、僕にしがみつく掌を優しく息子にエスコートしようかと思っただろうか。
おそらくはエスコートすれば、答えてくれたかもしれない。
しかしながら、初めては、その目で認識しながら、自発的に触らせたい。
その思いが僕を抑制していた。
目的地につくと、そこは腕を広げたくらいの樽風呂だった。
二人でちょうどくらいの大きさ。
踏み台を使って二人で入ると足同士が触れ合うほどの大きさだった。
あたりを再確認するも引き続き、二人だけであることが確認できた。
あたりは静寂と冷ややかな空気に包まれ、まるでフィクションの世界にいるようでもあった。
少し横に並ぶように湯船に浸かると、僕は大人の女性を口説くかのように、ユカのプロポーションを誉めはじめた。
ユカは声として反応することはほとんどなかったが、うれしそうにハニカみの笑顔を絶やさなかった。
しかし有る瞬間、はにかみから恥じらいに変わった。
それは僕がお湯の中で行動を起こしたときだった。
湯に入れていた手を、ゆっくりと隣に座るユカのお尻へ移動させ、手の甲でそっと触れたときだった。
はじけるような弾力を感じたとき、その反動のようにユカ自体もビクンッと肩を揺らした。
目は一瞬見開いたが、何かを悟ったかのように、また揺れる湯面に目線を戻した。
きっとこういうことになることは、想像していたのか、すべてを受け入れるという好奇心がそうさせたのかもしれない。
それを確認すると僕は、手のひらを返し、片手には少し余るほどの片側のお尻をゆっくりと包み、そっとなでた。
ユカはぐっと堪え、動くことは無かったが、口元はゆるみ、徐々に肩で息をするようになった。
触れる掌から、鼓動の高鳴りが確実に伝わってくるようだった。
そのまま僕は、腰、背中と徐々に愛撫を上昇させるごとに、ユカは背中をピンと延ばし、そして反り返りそうになった。
僕の手が最終地点の肩に回ったとき、二人の上体はぴったりとくっつき、僕の体はつべらかな肌に触れ、その瞬間、二人の間にはお湯も入り込めぬほど、ユカを抱き寄せていた。
「いい?」
そういうと、終始無言のユカは、返事をせずとも、肩の強ばりを感じ、何を意味するのか分かっていることを、僕は明確に感じ取った。
沈黙は承認だと自らを奮い立たせ、肩をさらに引き寄せると共に、巻き込むようにユカの唇を奪った。
あくまで触れる程度に軽く、ユカの初めてであろうことに対する少しばかりの優しさだったのかもしれない。
ユカの唇は強ばりからかキュッと固く閉じられていましたが、引き寄せる腕と逆の腕で抱き寄せるように包み込むと、ユカの強ばりは取れ、僕の顔の動きに合わせて唇がプルプルと反応するまで身を委ねていた。
まだ未発達の小さな口は、何にも汚されていない、これぞプレーンといえる感触がした。
この戯れは十秒ほど続き、はっと周りが気になり、僕は急いで唇をはずして周囲を確認した。
誰の目も受けていないことを再確認すると、僕は最終目標へ行動を移した。
「ユカちゃん、ちゃんと見せてあげるからね。」
今にも溶けてしましそうな瞳を潤ませ、ユカはコクンと頷き、僕の肩にうなだれた。
僕は、頭をひとなでしながら、再度唇を奪った後、そっと樽風呂の縁へと腰を浮かせ始めた。
ユカの目の前の水面より、徐々に姿を現す息子を、ユカは目線を動かすことなく、じっくりと見つめていた。
縁に座り終わる頃には、ユカは僕の両足の間に入り、上から照らすスポットライトのせいで、まるで王座に座る王に忠誠を誓う女官のような構図になった。
湯上がりの息子はスポットライトに光り輝き、ユカの目には初めての光景であったに違いない。
「どうかな?」
そういうとユカは、恥ずかしそうに口をきゅっと結んだが、僕の顔を見上げて、ぼそっとつぶやいた。
「なんか、すごい…」
僕はもう一度頭をなでながら話しかけた。
「どういう風にすごい?」
「なんか、ピクピク動いて、ユカに話してるみたい。」
「そうだよ。ユカちゃんに見てほしいって言ってるんだよ。」
「そうなの?なんかおかしい!」
「そして、触ってほしいって言ってるよ。触ってあげてくれる?」
そう僕が息子に成り代わり、要望を伝えた。
それを聞いたユカは躊躇うことなく、コクンと頷くと、また唇を甘く噛み締め、ユカは風呂を移動するときのようにゆっくりと湯船から手を僕の方にさしのべてきた。
その手は、ユカの見つめる眼の前の柱に向かい、そっと登り棒を掴むようにキュッと握りしめた。
「あっ、かたい…」
その無邪気なつぶやきは、僕の息子を今まで経験したことのないほど硬直させた。
すでに頭は充血し、これ以上膨らむと皮が張り裂け、中から羊羹のボールが出てくるのではないかと思ってしまうほどだった。
「ちょっと動かすね。」
そう言うと、そっとユカの手を僕の手で被せるように介助し、上下に動かそうとした瞬間、これまでにないカリの張りにユカの指が引っかかり、手が止まってしまうほどだった。
こんなこと今までなかった。
終始二人は無言のまま、僕の誘導に素直についてくるユカ。
着々とゴールに向かって突き進んでいった。
温泉成分も助けてか、すべすべのユカの手のひらはこの世の物とは思えない刺激を僕に与え、あっという間に根本付近まで白いマグマが上昇してきたのが分かった。
「ユカちゃん。すごく気持ちいよ。」
そう言うとユカは、ご満悦のような笑顔を見せた。
「手の中で、すごい動いてるよ。生きてるみたい。」
「もちろん生き物だよ。とても気持ちいから、先っぽから、ぬるぬるが出てきちゃったよ。」
「えっ、そうなるの?あー、本当だ。」
先端からは噴火前の水蒸気のごとく透明な潤滑成分があふれ出し、ユカの滑りをなおも助ける結果となった。
いままで片手で触っていたユカは、気が付くと両手になり、小さな手で包むように、愛おしそうに触りだした。
上になる手の指は、湧き続ける潤滑液をくりくりと頭になじませ、手慣れた女性の動きを自ら行っていた。
末恐ろしいな。
僕は少女の魅力にどっぷり浸かってしまった。
溢れ出る潤滑とユカの包み込む手の上下運動は、温泉のチョロチョロと流れる音を上回るほどの、クチュクチュという音を辺りに響き渡らせていた。
こんな状態を長く続けられ訳もなく、状況は急変し、ギブアップ宣言とも言える言葉を発した。
このとき、両手で愛してくれていたユカの顔は、すでに吐息が息子をくすぐらんとするところまで来ていた。
「ユカ、ユカちゃん、見せてあげる、からね。見せてあげる、か…」
根本に溜まっていた白いマグマだまりは間欠泉のように吹き出し、数センチメートルのところで見守るユカの頭を飛び越えた。
長く糸を引く粘着性のマグマはユカの後ろから頭、顔へと爪痕を残し、それに驚き止まったユカの手の動きを全く無視するように、白いマグマは四発、五発と勢いを落とさないまま、ユカに回数と同じ白線を残した。
次第にマグマの勢いも弱くなったが、その影響は甚大で、ユカの顔に直接着弾するような飛距離に変わった。
おでこ、目頭、そして半開きになるお口へと標的を変えたマグマは的確に着弾し、これまでのリビドーを表すかのように、流れ落ちない粘着性を見せていた。
その様子を意識朦朧と見ていた僕は、噴火の終了とともに、目の前で被災したユカを再認識する事になった。
まだしっかりと握りしめているユカの手を取り、ゆっくりと離すとユカも我に返ったように、自らに付着した白いマグマを不思議そうに摘まんでは取り除いていた。
「ごめんね、ユカちゃん。でもこれを見せたかったんだ。こんなにでたのはユカちゃんが初めてだよ。初めてになってくれてありがとうね。」
そういうと取りきれない付着物を取り除きながら、お湯ですすぎ落とした唇が露わになるとき、僕は再度抱きしめ、キスをした。
今度は大人の男女のような深い、深いキスだった。
唇を吸い付くし、ゆっくりと離した瞬間、サウナから出てくるユカの父親を確認した。
現実に戻された二人は、一生懸命付着物の跡が無いよう、露天風呂の方に移動して、除去作業に勤しんだ。
露天に出てきた父親は、二人のあわてふためきを見て、大笑いしながらユカに声をかけた。
「なんだ、仲良くなったなw よかったな、ユカ!」
「そんなことないもん!」
ユカは、恥ずかしさからか声大きく叫んでいた。
その横顔は大人の女性のような美しさと少女の可愛らしさが同居していた。
それを見た父親は何かを感じたのか、僕の方に目線を移し、意味深な笑顔を見せてこういった。
「お兄ちゃん、見ててくれてありがとうな。でものぼせちゃったのは、お兄ちゃんの方みたいだな!責任取れよ!」
この後、記憶に残っているのは、露天風呂に響く父親の笑い声と、チェックアウト30分前にけたたましくなるモーニングコールの電話の音だけだった。
あの後、どう風呂から上がり、どう過ごしたか、どうユカと別れたか。
それも思い出せないくらい夢の中の出来事のようだった。
もしかしたら夢だったのかもしれない。
そそくさとチェックアウトをすませ、朝食にもありつけなかった僕は、ユカとの痕跡を探したが、その家族は見あたらず、清掃中の看板がでる大浴場の前でしばし感情に浸っていた。
「さて、帰るとしますか。」
誰に言うともなく、自らの中で区切りをつけるため、僕は口にした。
スーツケースを転がし、清々しい空気の中、それとは反対にどこかスッキリすることがない僕は、大通りのバス停まで歩いていた。
その時、後ろから車がやってきて、クラクションを二回鳴らして横を通り過ぎた。
その時、風にのって僕の耳に届いた声があった。
「お兄ちゃん!またね!」
聞いた声。
咄嗟に車を見た僕の目に、車の窓から顔を出し、手を振るピンクのパーカーの少女が映った。
※元投稿はこちら >>
 ご主人様、皆様 - これから夜中まで肉便器しますレスが遅れますが気長に待って貰えると嬉しいです、 06:06 レス数:122 HOT:117 ↑↑↑
ご主人様、皆様 - これから夜中まで肉便器しますレスが遅れますが気長に待って貰えると嬉しいです、 06:06 レス数:122 HOT:117 ↑↑↑ わお - もっと見たいなー 黄色きてmoko0415 04:56 レス数:85 HOT:84
わお - もっと見たいなー 黄色きてmoko0415 04:56 レス数:85 HOT:84  (無題) - パイチンは嫌い? 01:17 レス数:70 HOT:69
(無題) - パイチンは嫌い? 01:17 レス数:70 HOT:69 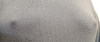 (無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:32
(無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:32