「ん、もう、朝か、、、」
静かに鳴り響く、ベッド上のアラームに気が付き、重い目を開けた。
寝ぼけながらも、昨日の大浴場の少女を真っ先に考えると日常の朝の強張りより幾分か、その強度は高かった。
今日の仕事は、昼前からの業務のため、レストランの朝食時間ギリギリに入ると、やはり客はほとんどいないことが分かった。
バイキング形式のトレーを持ち、軽めの料理が並ぶ机に向かうが、頭はスッキリせず、いまだ夢の中といったところだった。
そのとき、奥のテーブルから一組の家族が食事を終え、こちらに向かってきた。
昨日の少女の家族に違いない。
夫婦と見られる二人に挟まれ、スラッとした姿の少女は、僕が抜け殻探索をした際に見た、ピンクのパーカーを着ていた。
一糸まとわぬ姿も最高だが、どこかの読者モデルかと思うほどの出で立ちは、その姿そのものに加えて、昨日の姿さえもより素晴らしいものにランクアップさせるものだった。
僕はこの中身を知っている。
そしてその眼には、僕の強張りを写し込んだのだと言う、満足感に浸っていた。
そのうち家族は僕の目の前を通過していくが、その際、少女は横目でチラッと僕を確認し、軽く唇を噛む仕草をした後、少しうつむき加減に恥ずかしさを見せた。
その姿からも昨日の出来事を証明することになり、朝の強張りとは異なった成長を見せた。
夢見がちの中、朝から良いものを見れたと思っていたが、通り過ぎてからの父親の発言を耳にし、僕の意識は一気に覚醒した。
「さてっ、出かける前に朝風呂だな!」
サラダバイキングに目を移していた僕は動きを止め、横目で家族の後ろ姿を見ると、父親は少女の肩を叩き、お前もなと言わんばかりの動きをしていた。
僕は急ぎ料理をかき集め、空っぽの胃に流し込むように平らげ、出かける時間など意識する暇もないほど、入浴の準備を整え、大浴場へ向かった。
案の定、男湯の入り口には二つのスリッパが並んで置かれていた。
それを確認すると、すでにもぬけの殻の脱衣場に一目散に飛び込んだ。
目的地は、浴室入り口ではなく、そのすぐ脇に置かれていた脱衣カゴだった。
二つあるカゴのうち、目指すのはピンクのパーカーが入るカゴ。
先日のカゴ内の配置を覚えるなど、今の僕には配慮する暇などなかった。
ピンクのパーカーを確認すると、一気にカゴ内のすべてを抱え込み、その中に顔を突っ伏し、静かに、ゆっくりと、コーヒーを抽出するかのように、フィルター越しの少女を味わった。
突っ伏した衣類は、程よく少女の温もりを宿しており、先程飲んだフレッシュジュースよりもフレッシュで、諦めたホットミルクよりも濃厚な少女ミルクのコクが僕の鼻に押し寄せた。
これだけで、ご飯三杯、いや、白濁三発はイケると、突っ伏しながら考えていた。
そしておもむろに顔を離すと、一番少女に近いもの、直接触れているものを探し始めた。
ピンクのパーカーをめくると、そこには昨日とは違う薄ピンクの上下が置かれていた。
パーカーに守られることで、温かみも、湿っけも保たれた、言わば大吟醸のお宝が眠っていた。
僕は息をすべて吐ききり、上下を持ち上げると、優しく、そこに留められているものをすべて回収するかのように体内に流し込んだ。
昨日のボディーソープの香りなのか、いい香りが鼻の中を駆け抜けていくが、その奥には湿った生の香りも混じっていることを僕のセンサーは敏感に検出していた。
そのセンサーのボルテージを示す僕の息子は、これまで経験のないほど反り返り、パンツの抑圧を無視するかのように、腹との隙間を確保するほどだった。
昨日のようにここで果ててしまうことも容易だったが、まだ本丸に侵入していない兵士は、無駄死にと同然。
ここは断腸の思いで我慢をし、可能な限り自然な形で脱衣カゴにお宝を戻した。
少し離れたところに僕も脱衣カゴを確保し、急ぎ脱衣をすると、一部が入浴目的ではない部分を露わにした裸が鏡に写った。
さすがにこのまま鉢合わせはまずいと思い、タオルを四つ折りにして厚みを増し、できるだけフォルムをなだらかにした状態で、恐る恐る浴室入り口の引き戸を開けた。
見える範囲に父親がいないことを確認し、入室すると、すぐそばにあるかけ湯をしゃがんで浴び始め、中の様子を探るとともに、僅かながら僕の存在を知らせるように何度も何度も体にかけていた。
もう流石にかけ過ぎだろうと思い、最後の一回にしようとした瞬間、湯船から大きなしぶき音が立ち、父親と少女が上がってきた。
しまった。朝風呂だから長湯はしないのか…。
本丸を目の前に、なぜ急ぎながらも朝食を食べてしまったのか、なぜ脱衣カゴのお宝を我慢できなかったのか。
悔やむに悔やまれない感情が僕の中に渦巻いたが、何の神様かは存じ上げませんが、こんな哀れな男にも慈しみをいただくことができた。
「ユカ、体を洗ってなさい、父さんはサウナに入ってからいくから」
そう言われると少女は、うん!と可愛い返事をして、洗い場の方に消えていった。
最後のかけ湯を持ったまま固まった僕は、まだ夢は終わってなかった安堵感と、少女がユカという名前を知った幸福感を感じていた。
ユカちゃんっていうのか、かわいいなぁ。
このとき僕は、人には見せることのできない変態な顔をしていたに違いない。
それを噛みしめるように、手桶のお湯をゆっくりと首筋からかけ流した。
ここの洗い場は壁に沿って蛇口と鏡、桶が並ぶようなところではなく、個室シャワーのように区画が壁で区切られ、隣から視線や水を受けないようになっていた。
そしてその並びは、銭湯のように洗い場同士が背中合わせになり、その通路が2m弱という配置のため、鏡に向かう利用者が背中合わせになる形だった。
3本ある洗い場の通路のうち、少女、いや、ここからはユカと言おう。
僕はユカが入っていった通路をもちろん確認ており、ユカの使っているシャワーの音が聞こえてきてから、あたかも偶然のように近寄り、ユカの背中合わせの洗い場を確保した。
もちろん静寂の浴室で分かるように、サウナの父親以外、僕とユカしか洗い場にいないことは明確だった。
背中越しではあるが、確実にユカの気配を背中で感じることができるほどの距離に、今にも後ろから抱きしめたい気持ちが押し寄せてきた。
そんな思いも気付くことはなく、ユカは髪の毛を洗い出した。
これをきっかけに僕は体を、反転させ、ユカのほうへ向き直り、背中をしばらく凝視すると、はじけるように肌を流れ落ちる水が、若さを物語っていた。
まだ僕の存在に気付いていないが、一糸まとわぬユカの背後には、強烈なシンボルを準備したオスが、オアシスで水浴びをする草食動物を見るかのように鎮座していた。
ただ百獣の王とは異なり、その草食動物を欲するがあまり、またたびを欲っして欲望の喉をゴロゴロと鳴らす、まるでユカにお預けをされている飼い猫のようでもあった。
ユカが洗髪を終えて、髪の毛の水を切るとき、あわてて僕は背を向けて、シャワーで体を流しはじめました。
その音にユカは気付いたのか、ゆっくり後ろを振り返るのを、僕は鏡越しにそっと観察していた。
そうすると、僕だと気付いたようで、背中をすこし伸ばすように、ビクッと驚きを見せていた。
その様子をきっかけとして、僕はそり立つ息子をゆっくりとさすり始めた。
シャワーを胸元から浴びながら、焦らすように握りすぎず、自立した角度を押さえつけないくらいのソフトタッチで、シャワーの水圧も利用しながら、ユカに見られても恥ずかしくない形状にまで成長させた。
その動きを感じてか、ユカも背を向けると体を洗う準備をしていたが、顔は鏡を見たまま視線は背中の後ろに向けられているようだった。
しばらくその状態を続けていると、二人の距離は2m程度だったが、両者のシャワーで上がる湯気で、鏡越しでは様子もわからなくなってきた。
堪らなく僕はそっと振り返り、ユカを直視すると、つややかだった体は泡で覆われ、まるで天使の羽衣を着ているようだった。
汚れなき天使の後ろで悪魔の一本爪を研いでいるかの状況が、背徳感の芽生えとともに欲望の門を開けるきっかけとなった。
僕はゆっくりと椅子の上で体を滑らせ、座る向きをユカの方に移した。
もしユカが振り返れば、天使の瞳と悪魔の一本爪の間には何も遮るものはない。
悍ましくもそそり立った映像は、天使の脳裏に直接届くはずだ。
そう考えるだけでも、触れることなく硬度を維持し、むしろ触ることで多少なりとも隠れてしまう部分があることのほうが快感を損ねてしまう状況だった。
この状態がずっと続けばいいのに。
僕の中に、生まれたその感情は、もし振り返られたら終わってしまうのではないかと言う恐怖も同時に覚え、まず天使の近くで昇天したいと思い始めた。
僕が振り返ることで、シャワーの音が単調に変わったことで、ユカは背後の様子が変わったことに気付いたのだろうか。
腕を前に伸ばして洗っている動きが、ピタリと止まり、真後ろの僕が鏡越しに見えるように、ユカは上半身を左に傾けた。
曇り気味の鏡から後ろを確認しようと、目を凝らしているようで、首が僅かに前後している様子を僕は愛おしく感じていた。
それをきっかけに、僕はこれでもかというほど、大きなモーションで息子をしごき始めた。
曇る鏡でも分かるような大袈裟な動きは、決して風呂で行われる動きでは無いことが、ユカにも認識してもらうためだった。
案の定、ユカの確認しようとする動きは大きくなり、相変わらず洗う途中の腕はずっと前ならえ状態だったのが堪らなく可愛く思えた。
ここで僕は後ろ手に、自らに当たっているシャワーを止めた。
あたりの雑音は一気に止まり、二人きりの静けさに変わった。
僕は引き続き、大きなモーションで腕の上下を始めると、ヌチュヌチュという音が響き、ユカとその音を共有した。
その音にたまらず、ユカはゆっくりと頭を右に回し始めた。
あぁ、ユカに直接、ヌチュヌチュと音を立てている部分や行為を見られてしまう。
天使の瞳に、この光景を入れてしまうのだ。
肉体的に興奮と快楽の中にありながら、そのような妄想からも超絶の興奮を奮い立たされた僕は、一気に絶頂の頂きに、登ってしまった。
ユカの横目が僕を捉えようとした瞬間、僕は自らの足を大きくのばして開き、後ろにのけぞるかのように腕で支えながら、その瞬間に天井に届くのではないかという位の勢いで白濁のマグマを放ってしまった。
脈を打つと同時に尻が締まり、その勢いで押し出されたかのように、幾度も発射されるマグマは、天井に届くのではないかと錯覚するほどだった。
あまりの気持ちよさに、僕はのけぞり、ユカの状況を確認することができていなかった。
おそらく、目をまんまるにしてあんぐり口を開いてるのではないか。
そんな妄想のユカを感じながら、実際にユカの近傍ですべての精を放ったのだった。
ようやく激しい脈打ちも終わり、僕はのけぞりを戻し、ユカを確認すると、鏡の方を向いてしまっていた。
しかし、これまでの腕を前に出した状態ではなく、肩を緊張させながら、下向き加減の上目遣いで鏡を確認していた。
絶頂の瞬間、僕はユカを確認できなかったことから、直接見られたかどうかは確認することができなかったが、間違いなくユカは何かを確認し、隠し切れない動揺を僕に示していた。
その事実に興奮が増すが、いつサウナから出てくるか分からない父親との対面を避けるため、収まらぬ快感の余韻の中、あたりに散らばる快感の爪痕を急いで洗い流した。
その様子もユカは鏡越しに確認しているようだったが、そんなユカに僕は声をかけることができなかった。
おそらくは怖がられ、嫌われたのではないかと、一回りは違うであろうユカの反応が怖かったからだ。
僕は逃げるように立ち去ったが、その時、いまだ泡を洗い落とさないままうつむき加減だったユカの横顔が目に入った。
どことなく口元が微笑んでいるようにも見えたが、焦っていたこの時の僕は、一目散に脱衣場に向かっていた。
脱衣場に出た僕は、一転して背徳感に苛まれていた。
一方的な興味を持ち、自らの欲求を少女にぶつけてしまった。
そんな感情に支配されたのもつかの間、脱衣カゴにあるユカの抜け殻を見た瞬間、ふたたび顔をうずめ、深呼吸の中、新たな欲望の芽が出てきた。
ユカの眼の前で、しっかりとシンボルを見せたい。
その欲望を繰り返し念じながら、僕は仕事へと向かった。
今夜がラストチャンスかもしれない。
僕は仕事どころではなくなっていた。
※元投稿はこちら >>
 ご主人様、皆様 - これから夜中まで肉便器しますレスが遅れますが気長に待って貰えると嬉しいです、 06:06 レス数:122 HOT:117 ↑↑↑
ご主人様、皆様 - これから夜中まで肉便器しますレスが遅れますが気長に待って貰えると嬉しいです、 06:06 レス数:122 HOT:117 ↑↑↑ わお - もっと見たいなー 黄色きてmoko0415 04:56 レス数:85 HOT:84
わお - もっと見たいなー 黄色きてmoko0415 04:56 レス数:85 HOT:84  (無題) - パイチンは嫌い? 01:17 レス数:70 HOT:69
(無題) - パイチンは嫌い? 01:17 レス数:70 HOT:69 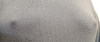 (無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:32
(無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:32