不思議な色香がある。
この少女を前にしたとき、シンドウはいつもそれを感じずにはいられない。
信じられないことだが、彼女はすでに、その未熟な肢体を使って男を惑わせる術を身につけている。
男を知っているだから、情欲を焚きつける色香のごときフェロモンを発散させていても不思議ではない。
だが、違うのだ。
彼女から感じる色香は、それだけではない。
男の肉欲を煽り、無差別的な攻撃衝動を駆り立てるだけのものとは違う。
いい方としては妙だが、敢えて表現するなら崇高な存在の向こうにある淫らさ。
そんな感じだった。
この不思議な色香をシンドウはどこかで覚えていた。
着替えのために家に戻ったとき、鏡台の前で長い髪に櫛を通していた母親を見かけて、ようやくそれを思い出した。
時々、母親に垣間見る色香と同じなのだ。
自分の親に懸想したことなど一度もない。
しかし、男にとって女親とは永遠の女神であり、思慕と畏怖と清廉と淫靡ささを内面に潜ませた常にミステリアスな存在なのである。
この幼い少女を前にしたとき、なぜかシンドウは同じものを感じずにはいられなかった。
あの刑事は姉妹だといった。
最初は、シンドウもそう思っていた。
しかし、彼の見立てを聞いているうちに、違う答えが浮かび上がってきた。
目の前の少女を眺めていると、その答えは、ますます確信に近いものに変わっていく。
狂ったように刺しまくったのは妹だからじゃない。
自分の娘だからだ。
それは単なる感でしかなかったが、シンドウは自分の直感を信じた。
「あの子は元気にしてるよ。またミルクの量が増えたそうだ。ずいぶんと食いしん坊な赤ちゃんだね。すごく元気で、よく笑うから看護婦さんたちにも大人気だ。たくさん可愛がってもらっているよ。なにも心配することはない。あの子は、大丈夫だ・・・。」
事件から三日が過ぎても少女の様子はなにも変わらなかった。
相変わらず魂が抜け落ちたような光のない瞳で一点を見つめるだけだった。
ケガはずいぶんとよくなり、外出の許可も得ていたが、取り調べは警察病院の病室でつづけていた。
なかなか報告の上がってこないのに苛立った係長から、一度署に連行しろと催促されたが、それは無視した。
もしかしたら、捜一の課長から横やりが入ったのかもしれない。
事件のことには一切触れなかった。
ただ、あの赤ん坊のことだけを教えつづけた。
考えがあった。
あの赤ん坊は、同じこの警察病院内にいる。
すぐ身近なところにいて、それは少女も知っている。
だが、彼女は事件以来、監視役の女性警察官に24時間付き添われて、未だに行動は自由になれない。
赤ん坊にも、いっさい会えずにいた。
いずれ限界が来る。
シンドウには確信めいた予感があった。
この少女の瞳に光をもたらすのは、あの赤ん坊しかいない。
「さっき見てきたけど、相変わらずいい飲みっぷりだったよ。ゴクゴク飲んでた。ほんとに食いしん坊な赤ちゃんだよね。」
笑いかけてみても少女の表情は変わらない。
かまわなかった。
あの子の近況を毎日教えてやる。
それが、この娘にどんな変化をもたらすのか。
それを確かめてみたかった。
少女に対する調べは、毎日続けられた。
氷のような冷たい表情は、一度として変わることはなかったが、限界は近いとシンドウは予測していた。
すぐ身近にいるにも関わらず、この子はずっと娘に会えないでいる。
男を刺してまで守ろうとした娘だ。
我が子であるならば、会えないのが一番辛い。
能面のような表情で取り繕っていたが、内心は穏やかでないはずと踏んでいた。
いよいよ10日も過ぎた頃に、頃合いと見計らったシンドウは仕掛けてみることにした。
「今も赤ちゃんを見てきたよ・・。」
目の前にいる少女はいつもと変わらなかった。
ベッドの上に上半身だけを起こし、両手の指を軽く組みながら、無表情に光のない瞳を伏し目がちに落としているだけだった。
シンドウは、少女の顔だけを見ていた。
「ぐっすりと眠っていた。今日もたっぷりとミルクを飲んだそうだ・・・。」
ゆっくり話した。
窓から差し込む柔らかい日差しが、少女の頬を照らしている。
「でも、とても残念なことがある・・。」
毎日、あの子の様子をいって聞かせた。
そろそろ限界になっているはずだ。
まだ、表情は変わらない。
「今日で、あの子ともお別れすることになった・・・。」
かすかに少女のまぶたが動いた。
シンドウは見逃さなかった。
「明日からは、あの子に会えなくなる・・・。」
初めて反応が現れた。
落としていた視線が、ゆっくりとシンドウに向けられる。
「あの子は、施設に預けられることになった・・・。」
シンドウは、向けられた眼差しを正面から受け止めた。
きっと、この子は堪えられない。
姉妹であるなら、離ればなれにされても今の環境よりはマシな生活になることを甘受できるかもしれない。
だが、母親なら別だ。
自分の胎内で育て、分け与えた命を切り離される痛み。
その痛みに堪えられる母親など、居はしない。
「いずれ、どこかの夫婦に養女としてもらわれていくことになるだろう・・。」
少女の口は相変わらず閉じたままだった。
だが、彼女の瞳が嫌だと訴えていた。
ガイシャを滅多刺しにしてまで守ろうとした赤ん坊だった。
その子と引き離される。
それが我が子であるなら堪えられるわけがない。
「そうなれば、二度と君に会うことはできない・・」
鼻の頭が赤くなり、見る見るつぶらな瞳に涙が滲んでいった。
「あの子に会いたいか?・・」
シンドウの問いかけに、少女は唇を噛みしめた。
じっと見つめたままだった。
あどけない顔は、天使のように愛らしい。
その愛らしい顔の上を、大粒の涙がぽとりぽとりと落ちていく。
「君の、子供なんだな?」
少女は唇を噛みしめたまま目を閉じた。
観念したかのように、唇をきつく結んだまま、小さく頷いた・・・。
※元投稿はこちら >>
 (無題) - パイチンは嫌い? 01:17 レス数:70 HOT:69
(無題) - パイチンは嫌い? 01:17 レス数:70 HOT:69  見られてみたい - 私の大事なところを職場の男性に見られる...見てもらいたい... 02:50 レス数:43 HOT:42 ↑↑↑
見られてみたい - 私の大事なところを職場の男性に見られる...見てもらいたい... 02:50 レス数:43 HOT:42 ↑↑↑ 眺めてって - 気のせいかさっきよりも少し乳首立ってるね興奮してるんだやらし 02:49 レス数:37 HOT:37 ↑↑↑
眺めてって - 気のせいかさっきよりも少し乳首立ってるね興奮してるんだやらし 02:49 レス数:37 HOT:37 ↑↑↑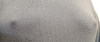 (無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:32
(無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:32