――第38話――
最初から、わたしたちは父の手のひらの上で踊らされていただけなのだ。
父には、初めからなにもかもすべてお見通しだった。
久しぶりにシンドウに付き添われて、取り調べのために署を訪れたときのことだった。
シンドウがちょっと席を外した隙に、あの男は入ってきた。
ミコシバだった。
顔が青ざめていた。
「この日に迎えに行くそうだ・・・。仕度して待っとけとよ・・・。裏の木戸口のところだ。そこからお前とあの赤ん坊を連れだすとさ・・・」
日付と時間の書かれたメモを渡された。
「どうして、あなたが?・・」
信じられなかった。
味方だとずっと思っていた。
ミコシバは苦渋の表情を浮かべていた。
「俺だって定年が近えんだ・・。それに家族だって・・・」
そこまでいって彼は口を噤んだ。
わたしにはすぐにわかった。
きっとこのひとの家族に父が何かをしたのだ。
「脅されてるの?」
苦々しい顔でミコシバは奥歯を噛みしめた。
「定年後は孫娘と一緒に暮らしたいだろう・・だとよ。あのクソ課長もお前らのショーバイに一枚噛んでたとはな・・。どおりでボロを出しやがらねえはずだ。あのクソ課長がすべて情報を流してやがった。野郎は俺のこともすべて知ってやがったよ。お前らのことだって最初から向こうに筒抜けだったのさ・・・。」
「じゃあ、わたしたちがあすなろ園にいることも?」
「ああ、奴はあの施設に火を付けてでもお前を奪い返すそうだ。」
足が震えた。
父ならば、やりかねなかった。
結局わたしたちは、父の手のひらの上で踊らされていただけなのだ。
「おめえが素直に帰れば、施設には手を出さないそうだ。だが、拒めばあそこは地獄になるぞ・・。」
足だけじゃなかった。
唇までもが震えていた。
「自分で決めろとよ。素直に帰れば許してやるそうだ。拒めばその時は・・どうなるかは自分で考えろ・・・。」
苦々しい顔だった。
それはわたしを恨んでいるというよりも、すべてを恨んでいるといいたげな顔だった。
「何を・・されたの?」
父がこのひとの家族に何かをしたであろう事は薄々わかった。
「ああ?なにをだと?別に何もされちゃいねえよ。ただな、あのクソ課長からこういわれたのさ。お前にも生まれたばかりの孫娘がいるんだよな?あのクソガキがその住所を知ったら大変なことになるぞってな。オメエに刺されたあのガキだよ。俺は野郎が入院した病室でもねちねちとやったからな。野郎もさぞ恨んでたんだろうよ。あからさまに俺を罵りもしやがった。でっち上げまでして野郎をぶち込もうとしたのに、それにも失敗して、結局無罪放免になっちまいやがった。まったく政治家ってえのは恐ろしい力を持ってやがるもんだ・・。たんなる被害者になっちまったんだから拘束なんてできるはずもねえ。」
彼の肩が震えていた。
「俺だけなら、どうなったってかまやしねえ。だが、孫だけは駄目だ。あの子だけは絶対に駄目だ。地獄なんか見せられるわけがねえ・・・。お前の赤ん坊みたいにさせたくねえんだ!」
恨みに血走った目で睨まれて、わたしは息を飲んだ。
「あのガキが無罪放免になってすぐだよ。トリヤマって野郎が俺の前に現れて、テメエを逃がすための手引きをしろとよ。おとなしくいうことを聞けば、あのガキを孫には近づけねえと約束した。あのガキが無罪放免になった時点で俺は負けてんだよ。俺に選ぶ答えなんか残されちゃいねえのさ。」
彼が自嘲気味に笑ったのは、自分の無力さを呪ったからかもしれない。
「わかったら、おとなしくその日付にあの園を出ろ。そうすりゃすべてが丸く収まる・・・。」
彼は、最後までわたしの目を見なかった。
「恨んでもらってもかまわねえよ・・・。だがな、薄汚れちまったオメエよりも、俺は孫を綺麗なまま守ってやりてえんだ・・。それだけは、わかってくれ・・・。」
ずいぶんとひどいことをいう。
でも、その時のわたしは、彼を恨む気持ちにはなれなかった。
「おじさん。トリヤマに伝えて。約束の日にわたしは園を出るわ。その代わり・・。」
父に会いたくなかったかといわれれば嘘になる。
確かに、もう一度可愛がってもらいたい気持ちは強かった。
でも、その時のわたしは、そんなことよりも違うことを考えていた。
結局、父からは逃げられない。
ならば、従うしかない。
おとなしく従う代わりにひとつだけ交換条件を出した。
それを父が呑むかどうかは、賭けだった。
約束の日、わたしは指定された時間に木戸口の裏に立った。
ひとりだった。
コトリは置いていくと決めていた。
あの子にはまだ早い。
それに誰も面倒なんて見てくれない。
連れて歩けば見つかる可能性も高くなるし、また同じようなことをする客が現れる危険性だってある。
だから、あの子は置いていく。
それが、父に出した条件だった。
施錠を外すなんてトリヤマ達には簡単なこと。
ガチャガチャと音がして、すぐに木戸口の戸は開かれた。
そこに待っていたのは、トリヤマとタンと父の3人。
「ずいぶんと遊んでたな・・・。客が首を長くして待ってるぞ・・。」
父は怒りもしなかった。
わたしがひとりなのを見ても、なにもいわなかった。
いずれ奪い返せる。
あの子は、父の子供。
なによりも大事な父の血を受け継ぐ、たったひとりの愛しい娘。
父にしてみれば、こんな所から奪い返すなんて、簡単なことと思えたに違いない。
だから、条件を呑んだ・・。
「ああっ!!お許しくださいっ!!・・・お許しくださいっ!!」
Thrushに戻って、最初に待っていた客は、あの男だった。
「この糞ガキがっ!俺のものを噛みやがってっ!ぶっ殺してやる!」
逆さ吊りにされて、鞭で打たれた。
膣が裂けそうなほど大きなバイブを押し込まれて、何度も気を失った。
「ぼっちゃん、その辺で許してやっちゃくれねえかい?これでも、うちじゃ一番の人気商品なんだ。代わりはちゃんと用意してやるからよ、その辺でもう勘弁してくれや・・。」
父が取りなして、ようやくわたしは許された。
「なにもさらうなんてコトしねえで、最初からいってくれりゃよかったんだ。あんたのオヤジさんには、うちも世話になってるからよ、いってくれりゃ、ちゃんと用意してやったんだ。まあ、今回は痛み分けってことで、おとなしく引いてくれや・・・。」
すごんだ父に、あんな卑屈な男がかなうはずがない。
「テメエのせいで大事な商品をひとり持っていかれた・・・。あんなクズ野郎に手塩に掛けた娘をみすみす渡すハメになっちまったんだ。この代償はデケえぞ・・・。」
声も出ないほどぐったりとなっていたわたしの髪を掴んで、父はすごんだ。
「今まで以上に働け・・・、死にものぐるいで客を取れ・・。」
狂気を宿した瞳に睨まれて、わたしは唇を震わせながら頷いた。
素直になれば、父は怒らない。
「そうだ・・。良い子だ・・。お前は良い子なんだ・・。ちゃんとパパのために尽くせる子だ・・。そうだな?」
「はい・・・。」
「パパのためなら、なんでもできるだろう?」
「はい・・。」
「パパのことが、大好きでならないんだよな?」
「はい・・。」
知らず知らずに涙が溢れていた。
ずっと小さな頃から、父にささやかれてきた言葉。
父のためならば、なんでもする。
どんなことでも、我慢する。
わたしたちはそうやって、幼い頃から躾けられてきた。
泣いたのは怖かったからじゃない。
優しい父が、目の前にいたからだ。
「痛かったか?」
「うん・・。」
「パパに可愛がってもらいたいか?」
「うん・・。」
「パパに愛してもらいたいなら、愛してるというんだ。」
「愛してます・・」
「どのくらい?」
「世界中の誰よりも愛してます・・。」
「パパが一番いいか?」
「はい。」
「お前は、誰のものだ?」
「パパのものです・・・。」
父に愛してもらうための通過儀礼。
絶対服従を近い、心を込めて懇願する。
そうしなければ、愛してもらえない。
「パパっ!パパっ!!」
痛みなんかなかった。
背中の痛みも、アソコの痛みも、父に愛してもらえるなら、すべてが消える。
それだけの気持ちよさを与えてくれる。
「ああっ!!パパっ!気持ちいいよっ!気持ちいいよぅっ!!!」
どうしようもないほどに狂わされて、愛された。
そうやってずっと父に飼われていたわたしたちに、逆らう術なんてありはしなかった。
「なんでもしますっ!パパのためなら、なんでもしますっ!」
わたしたちは父の奴隷。
「なんでもするからもっと愛してっ!どんなことでもするから、もっと可愛がってっ!!」
父のためなら、なんでもするセックスドール。
それが、あのホテルにいたわたしたち・・・。
それからの4年間、あの重丸の手引きで逃げ出すまで、わたしは父に尽くし抜いた。
命じられるままになんでもした。
疑問に思い、躊躇ったこともあるけれど、父に愛されたあの時間は、確かにわたしにとって、幸せと呼べるひとときだった・・・。
※元投稿はこちら >>
 (無題) - パイチンは嫌い? 01:17 レス数:70 HOT:69
(無題) - パイチンは嫌い? 01:17 レス数:70 HOT:69  見られてみたい - 私の大事なところを職場の男性に見られる...見てもらいたい... 02:50 レス数:43 HOT:42 ↑↑↑
見られてみたい - 私の大事なところを職場の男性に見られる...見てもらいたい... 02:50 レス数:43 HOT:42 ↑↑↑ 眺めてって - 気のせいかさっきよりも少し乳首立ってるね興奮してるんだやらし 02:49 レス数:37 HOT:37 ↑↑↑
眺めてって - 気のせいかさっきよりも少し乳首立ってるね興奮してるんだやらし 02:49 レス数:37 HOT:37 ↑↑↑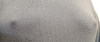 (無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:32
(無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:32