――第37話――
あのホテルでの事件から2ヶ月ほどが経っていた。
わたしとコトリは、「あすなろ園」という、特別養護施設に送られていた。
そこは犯罪に関係した子供や、緊急に避難を必要とする特殊事情のある子供たちばかりが集められた養護施設で、生後間もない子でも不自由することがないようにと、保育器や授乳の設備も完備された特別な施設だった。
他の養護施設と比べても、ベテランの職員ばかりが配置された比較的規模の大きな施設で子供たちの数も多かった。
犯罪に関わっていても、特別な事情があっても、やっぱり子供の中にいれば子供は子供らしくなる。
わたしは久しぶりに笑顔を取り戻していた。
コトリは保育ルームに預けられて、ベテランの職員たちが毎日面倒を見てくれていた。
だから、わたしは安心して授業にだけ専念すればよかった。
知能検査をされた後に、わたしだけが特別授業を受けることになった。
まだ12歳だったけれど、知能はすでに大学入試ができるほどのレベルにあった。
客を待っている間は、何もすることがなかったから、父に頼んで勉強することを許してもらっていた。
それまで以上に客を取るという条件付きだったけれど、あのThrushの中でわたしだけが活字を読むことを許された。
わたしは父が買ってくれた本を、暇さえあれば貪るように読み耽った。
気のいいお客さんのときは、セックスをしながら本を眺めたりもした。
中には内緒で、こっそりと本の差し入れをしてくれるお客さんもいた。
暗記が得意で、計算も速かった。
だから、その才能に気付いた父は、途中からわたしに帳簿を任せるようになった。
おかねの出入りは、すべて把握していた。
お客の名前から住所から電話番号まで、全部暗記していた。
だから、父がわたしをあのまま放っておくはずなんてなかった。
でも、なかなか父はアクションを起こさなかった。
あの人にはわかっていたのだ。
わたしが堪えきれなくなることを・・・。
重丸が妙な噂を耳にするようになったのは、シホとコトリをあすなろ園に預けてから、まだひと月も経たない頃だった。
「不純異性交遊?」
「え、ええ・・、職員の間で噂になっています。」
児相のオフィスで、いつものように事務仕事をしているときに同僚の職員からその話はもたらされた。
「シホちゃんが子供たちと?」
重丸の問いかけに、その職員は困ったような顔をしながら、バツが悪そうに答えた。
「それが、どうも子供たちばかりではないらしくて・・・」
歯切れの悪い彼を追求してみると、シホと関係が囁かれているのはどうにも子供たちばかりではないらしく、園の職員も複数関係しているようだという。
「それが事実ならとんでもないことだぞ!」
重丸は、にわかに気色ばった。
子供を擁護するべき立場にあるものが、彼らを食い物にしている。
断じて見過ごせる話しではない。
「まだ、事実関係ははっきりしていませんが、取り敢えず主任には報告しておきます。」
部屋を出て行く部下の背中を苦々しい思いで眺めながら、重丸は早急にあすなろ園に足を運ぶ必要があると考えた。
だが、やはりここでも重丸は後手を踏むのだった。
心が平和になると、ひとは新たな刺激を求めるものらしい。
園での生活に不満なんて何もなかったけれど、その頃のわたしにたったひとつだけ枯渇しているものがあった。
男だった。
まだ子供のくせに、身体は毎晩のように男を欲しがった。
わたしは、そんな女の子になってしまっていた。
自分で慰めて我慢できたのも最初のうちだけで、すぐに物足りなさ覚えるようになると目星をつけた年上の男の子たちを誘うようになった。
夜中に彼らに教えたりもしたけれど、それにもすぐに満足できなくなってしまうと、今度は男性職員を誘うようになった。
彼らは恐る恐るだったけれどわたしを抱いてくれた。
屈強に拒んでいた職員は色仕掛けで無理矢理落とした。
男なんてみんな同じだ。
どんなに高邁な職業を選んでいたって結局したがる事はなにも変わらない。
中年のベテランだっていたし、若い男性職員もいた。
初めは恐る恐るだった彼らも、わたしとのセックスに慣れてくると、それほど罪悪感も持たなくなり、そこそこ乱暴なセックスもしてくれるようになった。
けれど、わたしはそれでも満足できなかった。
いつも頭の片隅にあったのは父の姿。
彼の逞しいものを思い出すだけで、わたしは濡れた。
他の男に抱かれながらも、頭の中ではいつも父に犯される自分を思い描いていた。
わたしを完膚なきまでに陵辱し、支配してくれたひと。
畏れと郷愁に苛まれたあの時期を、ひとはなんと呼ぶのかわからない。
決して帰りたいと願っていたわけじゃなかったけれど、でも、父に抱いてもらいたいと願う気持ちは日に日に強くなっていき、わたしを父の幻影から逃さなかった。
あのひとには、いずれわたしがそうなるのがわかっていたのだ。
禁断症状が現れるように、わたしが父を欲しがりだすのがわかっていた。
だから、静観することができた。
そして、父は頃合いを見計らい、いよいよ仕掛けてきた。
わたしは為す術もなく、それから間もなくしてコトリを残したまま園を脱走することになる。
※元投稿はこちら >>
 (無題) - パイチンは嫌い? 01:17 レス数:70 HOT:69
(無題) - パイチンは嫌い? 01:17 レス数:70 HOT:69  見られてみたい - 私の大事なところを職場の男性に見られる...見てもらいたい... 02:50 レス数:43 HOT:42 ↑↑↑
見られてみたい - 私の大事なところを職場の男性に見られる...見てもらいたい... 02:50 レス数:43 HOT:42 ↑↑↑ 眺めてって - 気のせいかさっきよりも少し乳首立ってるね興奮してるんだやらし 02:49 レス数:37 HOT:37 ↑↑↑
眺めてって - 気のせいかさっきよりも少し乳首立ってるね興奮してるんだやらし 02:49 レス数:37 HOT:37 ↑↑↑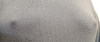 (無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:32
(無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:32