――第36話――
目があの人によく似ていた。
レンズ越しだったけれど、本当に彼女にそっくりな瞳だった。
だから、思い出してしまった。
そして、思わず彼女の誕生日と名前を口にしてしまった。
「7月22日・・・シホ・・・」
何度も彼はつぶやいていた。
もしかしたら、本当にシホお姉ちゃんのお父さんだったのかもしれない。
そんなことを心の中で少しだけ思ったりしたけれど、それは自分で打ち消した。
この絶望的な世界にそんな奇跡的なお話しなんてあるわけがない。
でも、彼の中に彼女の面影を見いだしていたのは確かだ。
わたしをずっと守ってくれたあの優しい瞳に再び出会えて、嬉しかった。
だから、わたしはこの人たちを信用する気になったのかもしれない。
「あの男が君を買ったんだね?」
それからも病室での取り調べはつづいた。
わたしは素直に応じた。
事件のことは、主にシンドウと名乗る若い刑事が訊いてきた。
コトリが乱暴されそうになったことも、あいつが先にナイフを出したことも、刺しているときのことはよく覚えていないなんて、ちょっとだけ嘘もついたけれど、話せることはすべて話した。
「なぜ、あの部屋に行ったの?」
正直にセックスをしに行ったと答えた。
「誰かに命令されたの?」
そう訊かれて、わたしは黙った。
「君以外にも、同じようなことをしている子はいるのかい?」
それにも答えなかった。
無理強いはしないと決めていたのか、わたしが答えに詰まると、二人は顔を見合わせるだけで深く追求したりはしなかった。
「コトリちゃんのお父さんは誰?」
シホお姉ちゃんと同じ目をした彼が訊ねた。
わたしは唇を結んだまま、それにも答えなかった。
でも、彼はわたしの表情から何かを読み取ったのかもしれなかった。
「コトリちゃんのお父さんは、君のお父さんかい?」
隣りのシンドウが驚いた顔になった。
驚いたのは彼ばかりじゃなかった。
心の中を読まれたような気がして、思わずわたしも彼を見つめていた。
その時のわたしは、本当に父のことを考えていたからだ。
「そうなんだね?」
わかってるといいたげな顔だった。
思わず頷いてしまったのは、父がこのまま大人しくしているわけがないと恐れていたからだ。
きっと、わたしたちを奪い返しにやって来る。
力ずくでわたしとコトリを、またあの地獄へ連れ戻しにやってくる。
だから、彼らに守ってもらいたかった。
「お父さんの命令で、こんなことをしているのかい?」
胸に染み入るような優しい声だった。
わたしは自然と頷いていた。
「そのお父さんは、どこにいるんだい?」
答えてしまいたかったけれど、それだけはできなかった。
そんなことをしたら、わたしだけじゃなくコトリまで殺されてしまう。
「なんて父親だ!」
押し黙ってしまったわたしを見て、若いシンドウという刑事があからさまに怒りを露わにした。
「シンドウ君、今日はここまでにしよう。この子もいきなりでは疲れてしまう。そろそろこの辺で休ませてあげよう・・」
シホお姉ちゃんと同じ優しい目をした彼は、いつでもわたしのことを気遣ってくれた。
でも、彼に気を許してはならないと思ったのは、聞き取りを終えてシンドウという刑事が部屋を出て行った後に、そっと彼がわたしに耳打ちしたからだ。
「シホちゃん。今はそう呼んでおくよ・・・。いずれ本当の名前を教えてくれると嬉しいな・・・。その日が来るのを楽しみにしてる・・・。そして、シホという女の子のことを君が教えてくれる日もね・・・」
彼は、にこりと微笑むとわたしの頭をそっと撫でた。
「僕の名前は重丸だ。これから君とコトリちゃんの面倒を見させてもらう」
迷いもせずに、じっとわたしを見つめていた。
「困ったことがあったら、遠慮しないで、なんでもいってくれ。僕には絶対に君たちを幸せにしなければならない義務がある」
絶対といういい方が気になった。
どうして?と訊いた。
彼とは出会ったばかりで、深い関わり合いなんてなかった。
わたしの問いかけに重丸と名乗った男は躊躇うことなく答えた。
「僕は、君たちのお父さんだからだ」
彼女と同じ、慈愛に満ちた瞳の男は、わたしの頭をひと撫ですると、にこりと笑って部屋を出て行った。
それからも病室での取り調べはつづいた。
コトリは、わたしと同じ部屋で眠ることを許されて、わたしは束の間幸せだった。
シンドウと重丸が聞いてくることに、答えられることは答えた。
でも、Thrushの存在や、そこでわたしたちが何をしていたのかは黙秘しつづけた。
売春は父親に強制されたものと判断され、質問は次第に父親の所在とホテルでの刺傷事件に関することだけに限定されるようになっていった。
驚いたことに、彼らは父たちの犯罪にまったく気付いていなかった。
だから、わたしがうっかり口でも滑らせようものなら、それはたちまちセンセーショナルな事件に発展していったのかもしれない。
何度か警察署にも連れて行かれて、わたしは調書を取られた。
取り調べは、主にシンドウが行った。
都合の悪いことはすべて黙秘した。
父への恐怖が、わたしに口を開かせなかった。
コトリに乱暴しようとしたあの男だけは、どうしても許せなかったから、話せることはすべて話した。
「ミコシバ」と名乗る刑事が立ち会ったとき、無理矢理じゃなかったのか?とおかしなことを訊ねた。
そして、トランクは奴が持ち込んだんだろう?とわたしに同意を求めた。
わたしは、あいつにつけられた首筋の傷を見せた。
そして、いきなり部屋に連れ込まれて乱暴されたのだといって泣いた。
ミコシバは、その証言を絶対に覆すな、と泣き伏せるわたしを見ながら笑っていた。
シンドウは、その場にいなかった。
わたしとコトリは、重丸に付き添われて養護施設に預けられることになった。
まだ取り調べは残っていたけれど、ひとまず平和な日々がわたしたちに訪れた。
このまま無事に過ごせればいい、なんて思っていたけれど、結局わたしは父の元に帰ってしまった。
あの人が奪い返しに来たとき、わたしは自分の意志で父の元に走ってしまったのだ。
※元投稿はこちら >>
 (無題) - パイチンは嫌い? 01:17 レス数:70 HOT:69
(無題) - パイチンは嫌い? 01:17 レス数:70 HOT:69  見られてみたい - 私の大事なところを職場の男性に見られる...見てもらいたい... 02:50 レス数:43 HOT:42 ↑↑↑
見られてみたい - 私の大事なところを職場の男性に見られる...見てもらいたい... 02:50 レス数:43 HOT:42 ↑↑↑ 眺めてって - 気のせいかさっきよりも少し乳首立ってるね興奮してるんだやらし 02:49 レス数:37 HOT:37 ↑↑↑
眺めてって - 気のせいかさっきよりも少し乳首立ってるね興奮してるんだやらし 02:49 レス数:37 HOT:37 ↑↑↑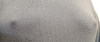 (無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:32
(無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:32