――第35話――
お腹が大きくなっても、誰もわたしをいたわってなんてくれなかった。
それを理由にお客を拒むことも許してはもらえなかった。
迫りだしたお腹を面白がり、客は減るどころか、かえってわたしを指名する男たちは増えていった。
中には、わたしを責めながら、お腹の赤ちゃんを突き殺してやると脅す客さえいた。
無事に産めるなんて思ってなかった。
あのひとがいてくれなかったら、コトリはこの世に誕生していなかったかもしれない。
彼女だけが味方だった。
『シホよ・・』
とても綺麗な人だった。
ちょうどお腹が膨らみ始めた頃、わたしを救ってくれるかのようにThrushに現れた女神。
『よろしくね』
やって来たその日から、とても素敵な顔で彼女は笑った。
あんなに素敵な笑顔ができるひとを、わたしはあそこで初めて見た。
『大丈夫。ちゃんと産めるわよ』
まだ二十歳ぐらいのひとだったけれど、彼女には、わたしとたいして歳の違わない大きな子供がいた。
産んだのは、わたしと同い年くらいの頃だったと彼女はいった。
『よく覚えていないの・・・』
まだずっと小さかった頃、公園で遊んでいた彼女は、見知らぬ男に連れ去られた。
10年以上もの間、その男とふたりだけの暮らしを強要され、その間に彼女は女の子を産んでいた。
押し入れの中で苦しみながら、たったひとりきりで産んだのだという。
『わたしが教えてあげるわ。必要な物はね・・・』
わたしのお腹が大きくなっていくと、彼女はトリヤマたちにいって必要な物を揃えてくれた。
お腹の膨らみが限界に達して破水が始まったときも、おろおろとするだけのトリヤマたちを尻目に、息の継ぎ方を教えてくれたり、手を握りながら励ましてくれたり、ずっとそばにいてわたしを助けてくれたのはシホお姉ちゃんだ。
死ぬような思いでようやく産んだコトリを取り上げてくれたのも、また彼女だった。
『わたしと同じ誕生日ね』
産湯に浸けたコトリを丁寧に洗い、まだ生まれたばかりのあの子を腕に抱きながら、ぼんやりとしか目を開けられないわたしに彼女が教えてくれた。
『よく頑張ったわね・・・』
優しい瞳に見つめられ、愛しむように彼女に髪を撫でられながら、その時のわたしは、コトリが誕生したことよりも、彼女が傍にいてくれた喜びのほうが強かった。
すごく優しい瞳をしたお姉さんだった。
だからかもしれない。
レンズ越しだったけれど銀縁のメガネを掛けた男の瞳が彼女とよく似ていた。
ううん、似ているなんてものじゃなかった。
同じだった。
彼が誕生日からわたしの素性を探ろうとしていたのは気付いていた。
だからデタラメな日付を言おうとしたのに、口に出していたのはシホお姉ちゃんの誕生日だった。
彼の目が、あまりにも彼女と同じだったから、思わずいってしまったのかもしれない。
『マリア様の誕生日?』
小さなときにさらわれた彼女は、聖名祝日を誕生日と勘違いしていた。
『うん。でも聖母マリア様じゃなくてね、マグダラのマリアのほうよ』
『マグダラのマリア?』
『そう。マグダラのマリアはね、キリストの復活を見届けた女性といわれているの。キリスト、つまりイエス様が本当に愛した唯一の女性ともいわれているのよ。』
『そうなんだ。』
自分のことはあまり覚えていない彼女だったけれど、誕生日の由来だけは、はっきりと覚えていた。
母親から、絶対に忘れてはならないと、ずっといわれていたのだという。
『マグダラのマリアはね、愛してはならない人を愛してしまい、イエスの子供を産んだともいわれているの。それが聖杯伝説につながるんだけど、わたしも同じなのよね。』
『どういうこと?』
『わたしね、お父さんがいないの。お母さんが愛しちゃいけない人を愛してしまって、それでわたしができちゃったんだって。』
『じゃあ、お母さんのこと恨んでるの?』
『ううん、まさか。もう、はっきりとは覚えていないけれど、大事にしてもらった記憶があるわ。いつかお父さんに会わせてくれるって約束してくれたけど、でも・・・。』
彼女は涙ぐんだ。
『もう、お父さんに会えなくなっちゃった・・・。』
『どうして?』
『こんな汚れちゃった娘なんて、お父さんいらないよ。』
彼女は泣いた。
子供のように泣いた。
いつも笑顔を絶やさなかった彼女が、声を上げて泣きじゃくる姿を見たのは、そのときが初めてだった。
『お父さんに、会いたかった・・・。』
大粒の涙を流しながら、そういった彼女を見つめて、わたしは心底お父さんに会わせてあげたいと思った。
だから、彼女とあまりにも似た目をする銀縁メガネの男が、もしかしたら彼女のお父さんかもしれないと思ったときは、少しだけ心が揺れた。
けれど、わたしはその考えを自分の中で打ち消した。
彼女は暖かいところで生まれたといっていた。
だったら、こんな北の寒いところに、あの人のお父さんがいるわけはない。
『向こうから、連絡してきたのさ。』
シホお姉ちゃんがThrushへ来た理由をわたしは知っていた。
『女が邪魔だったのさ。』
父が教えてくれたのだ。
彼女は小さな頃にさらわれてから、以来、ずっと男のオモチャにされてきた。
押し入れの中に閉じ込められ、そこから出されるときは必ずセックスを強いられ、それを撮影したビデオを売ることで、男は生活の糧を得ていたという。
小心で卑屈な男だったけれど、それだけに用心深く、逃げるように転々と引っ越しを繰り返したそうだ。
『どうして逃げなかったの?』
シホお姉ちゃんに聞いてみたことがある。
外に出るチャンスがあったのなら、逃げ出すことはいくらだってできたはずだ。
でも、彼女は逃げられなかった。
『ずっと暗い部屋の中で暮らしているうちに、外の世界が怖くなってしまったの・・・』
自分でも呆れたように笑っていた。
部屋に鍵を掛けたりしなくても、彼女は逃げだすことができなかった。
どれほど年齢を重ねて大人になっていっても、それは変わらなかった。
逃げだすことができないままに男との生活を続け、その間も引っ越しを繰り返した彼女たちは、10年以上の歳月を掛けてこの地にやってきた。
そして、ある日突然、彼女は父に売られたのだ。
うちに来た頃の彼女は、すでに二十歳を幾つか超えていた。
彼女をさらった男は、それまで彼女を散々オモチャにして、子供まで産ませたくせに、大人になってしまったら無用になったらしい。
娘のほうは男にとってまだ魅力的な年齢ではあったけれど、大人になってしまったシホお姉ちゃんは邪魔な存在なだけだった。
だから、彼は彼女を売ることにした。
誘拐までして目的を果たそうとする過度の小児性愛者であった彼が、父たちの創るビデオの存在を知らないわけがない。
当然、彼も顧客のひとりだった。
ビデオを買う客には、必ず連絡ができるように約束させる。
それは共犯というよりも、連帯意識を持たせて情報の流失と無用な拡散を防ぐためだった。
顧客には販売サイトを通じれば、向こうからもアクセスができるようにしてあった。
彼らのリクエストに応えるのが目的で、より強い嗜好を満足させる商品を提供してやれば、自ずと彼らは自分たちの聖域を守るために口を噤むようになる。
目的は果たされ、父たちの商売は順調に売り上げを伸ばし、そしてある日、そのシステムを利用して男は接触を図ってきたのだ。
母子を提供する代わりにビデオの売れ筋商品であった幼い女の子を手に入れたい。
それが、彼からの申し入れだった。
彼には、どうしてもその女の子が欲しかったらしい。
その子は父のお気に入りで、まだ小学校に上がる前にも関わらず、彼女は幼い性器に男を受け入れることができた。
大人の女のようにお尻を振りながら、舌っ足らずな拙い声で欲しがったりもした。
父が教え込んだからだ。
同じ性癖を持つ好事家の間では、とても有名な女の子で非常に人気の高い子だった。
その少女を、彼は独り占めしたいと考えたらしかった。
それが目的で、彼はこの地を目指したのだ。
シホお姉ちゃんが邪魔なだけなら、途中で放り出せばよかった。
娘は、彼にとってまだ魅力的な年齢であったのだから、邪魔な存在だけを排除してしまえばそれで済む。
それをしなかったのは、彼女たち親子を最初から売るつもりだったからだ。
ネット社会には通じていたらしく、わたしたちの本拠地が青森にあることに男は気付いていた。
青森には顧客に配信するためのサーバーがあり、そこに彼は、犬のように鎖に繋がれて傅くシホお姉ちゃんたちの画像を証拠サンプルとして送ってきた。
その頃の父たちにとって、単品の商品よりもダブルで売春をさせることのできる母子連れのほうがより魅力的だったのはいうまでもない。
『えげつないビデオだったぜ。ガキの腹からガキが出てくるビデオを証拠として送ってきたんだ』
無論、父たちにしたところで単純に彼を信用したりはしなかった。
足跡を辿られないように用意したダミーサーバーに違う証拠を送るように再度指示した。
そして男が父を納得させるために、送ってきたのが彼女の出産シーンを収めたビデオとその後の数年間の一部を記録した動画だった。
まだ幼き日の彼女は、狭い物置の中で暴れることができないように手足を大の字に縛られ、声も出さぬようにと猿轡までされていた。
煌々と照明の焚かれたその狭い空間の中で出産の痛みに藻掻きつづける彼女を、固定されたビデオは延々と写しつづけていた。
男の姿は一切なかった。
放置しつづけたのだ。
たとえ彼女がそこで死んだとしても、男にはきっとかまわなかったのかもしれない。
たんなるイベントとしての記録。
そんな印象が強かった。
苦しみに苦しみぬいた挙げ句、シホお姉ちゃんは赤ちゃんを産みきった。
膣が異常に拡がり、血塗れの黒い頭が押し出されてきたときは、それを眺めていたわたしも気が遠くなりかけた。
父に見せられたのだ。
その頃のわたしは彼女と同じ経験をしなければならない運命にあった。
だから、後学のためと称して、父はわたしにも彼女の出産シーンを見届けるように命じたのだ。
そこには感動や興奮なんてまったくなかった。
あったのは狂気とひたすらおぞましいだけの悲惨な光景だけだった。
ぬるっ!と小さな赤子が飛び出すように彼女の膣から押し出されてきたとき、はち切れんばかりに膨らんでいたお腹が、のっぺりと平らな状態に戻ったのがひどく印象的で、覚えているのはそれくらいしかない。
彼女は、まだ胸も膨らみきらない年齢で子供を産みきった。
それは、まさしく命を賭けた作業だったと思う。
あんな未熟な身体で子供を産んで、よく死ななかったものだと驚くしかない。
そして、後にわたしも同じ体験をすることになる。
『さほど、苦労しそうにもねえな』
商談が成立して、彼女たちがThrushに送られてきたのは、まだ雪解けも終わりきらない初春のことだった。
当然、彼女たちに待っていたのは、「仕込み」と称する、父やトリヤマたちの陵辱に次ぐ陵辱の洗礼だった。
しかし、父が彼女たちを仕込みながら、真っ先に持った印象は「手こずらせない。」それだった。
小さな頃から、さらった男によってオモチャにされつづけてきた彼女は、そこが何のために用意された場所か理解していたし、その運命をあっさりと受け入れもした。
わたしと一つ二つしか年の離れていなかった女の子もそれは同じで、すでに処女ではなかった彼女は、シホお姉ちゃんと二人で男に傅くことにも慣れていた。
もちろん、父たちは念入りに二人を仕込んだけれど、でも、女の子のほうは父たちとするよりも、シホお姉ちゃんとするほうを喜んでいたような気がする。
シホお姉ちゃんの飼い主であった男の手によって、娘に対する早すぎる陵辱が始まると、シホお姉ちゃんは、せめて少しでも娘が苦しまないようにと、押し入れの中で、その幼い肢体を時間を掛けて愛撫するようになった。
指を使い舌を使い、早く娘の性感が目覚めて悦びを得られるように努力したのだ。
それは地獄に生きながらも尚ひとの心を失わず、慈愛に満ちた彼女に出来た精一杯の慈しみであったのかもしれない。
二人の行為はThrushに来てからもつづけられ、それは鼻白むべき行為ではあったのかもしれないけれど、わたしの目には、とても羨ましい光景にしか映らなかった。
裸で絡み合いながら娘を見つめる彼女の瞳には、いつも慈愛の光りが溢れていたし、娘が狂わなかったのもそんな母親の愛情をしっかりと感じていたからだと思う。
わたしにお母さんはいなかった。
だから、シホお姉ちゃんを欲しがったのかもしれない。
シホお姉ちゃんは、わたしが子供を産んでからも、部屋を訪れては甲斐甲斐しく面倒を見てくれた。
まだ起き上がることの出来なかったわたしの代わりに、コトリにミルクを与えてくれたのもシホお姉ちゃんだ。
そして、そのコトリの名前を付けてくれたのも、また彼女だった。
『コトリ?』
『そう。ほら、ここにはお母さんと一緒の子は小鳥の入れ墨があって、お母さんのいない子は蝶でしょ?だから、この子はずっとあなたと一緒にいられるように「コトリ」って名前にしてみたら?』
彼女はわたしのお母さんのようなものだった。
だから、わたしはお母さんのいったことに従った。
『いいなコトリは・・・。お母さんに名前を付けてもらって、おまけに誕生日まで一緒で・・・』
『お母さん?わたしが?』
『うん、シホお姉ちゃんは、わたしとコトリのお母さん。』
『あら、こんな可愛い子供が二人も増えちゃったのね。』
シホお姉ちゃんは笑ってくれた。
『ねえ、お母さん・・』
『なあに?』
『元気になったら、わたしも可愛がってくれる?』
驚くほど素直に口から出ていた。
彼女はすぐに理解してくれた。
愛しそうにわたしの髪をひと撫ですると、自分の娘にするように優しく口付けてくれた。
それから数日後には、わたしは彼女の温かい肌に包まれることになった。
彼女に可愛がられながら、性の手ほどきを受けていると、どうしようもない幸せな気持ちになれて、このままコトリとここで暮らすのなら、いずれは同じ事をこの子にもしてあげようと思った。
ずっと、お母さんと一緒にいたかった。
彼女と暮らせる日々がいつまでも続くものと信じていた。
でも、ある日突然、お母さんはいなくなってしまった。
自分の娘と一緒に忽然と消えてしまったのだ。
※元投稿はこちら >>
 (無題) - パイチンは嫌い? 01:17 レス数:70 HOT:69
(無題) - パイチンは嫌い? 01:17 レス数:70 HOT:69  見られてみたい - 私の大事なところを職場の男性に見られる...見てもらいたい... 02:50 レス数:43 HOT:42 ↑↑↑
見られてみたい - 私の大事なところを職場の男性に見られる...見てもらいたい... 02:50 レス数:43 HOT:42 ↑↑↑ 眺めてって - 気のせいかさっきよりも少し乳首立ってるね興奮してるんだやらし 02:49 レス数:37 HOT:37 ↑↑↑
眺めてって - 気のせいかさっきよりも少し乳首立ってるね興奮してるんだやらし 02:49 レス数:37 HOT:37 ↑↑↑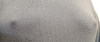 (無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:32
(無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:32