――第57話――
「ここがタカの家なの?」
すぐにでもシホの奪還に向いたい気持ちは強かった。
だが、コトリをひとりにしておくわけにはいかない。
「ああ。」
思案した挙げ句、タカはしばらくの間コトリを実家に預けることにした。
「おっきな家だね。」
ふたりはタカの実家の前に立っていた。
心なしか、コトリの表情が明るい。
「そっか?」
コトリと手を繋ぐタカの表情にも不思議な明るさがあった。
「大丈夫か?」
ついさっきまでベッドの中にいたふたり。
朝はデカさも増し増しだから、さぞ辛かったろうに、最後までコトリは我慢して、ずっとタカにしがみついていた。
「なにが?」
照れているのか、コトリは敢えてクールをよそおい、とぼけるように視線を逸らす。
ベッドの中では、玩具のような愛らしい性器からタカの精液を溢れさせていた。
タカを見上げる瞳にうっすらと涙を浮かべていたのは、痛かったからか、それとも嬉しかったからかは、わからない。
どちらにせよ、コトリはちゃんとタカを愛してやれる体になった。
それが、多少なりともコトリには嬉しいことらしく、その嬉しさが、コトリの顔からわずかながらも憂いの表情を消している。
「えっと・・ふつつかものですが・・。」
てなわけで、本気でタカの戸籍に入るつもりになったらしい。
「なにしてんの、お前?」
「あいさつの練習。もうすぐ家族になるんだから、ちゃんとお父様とお母様に、あいさつしなきゃだめでしょ。」
今の時代、そんなこといわねえぞ。
ほんと、つまんないことばっか覚えやがって・・・。
「ほれ、行くぞ。」
タカは、コトリの手のひらをギュッと握りしめた。
コトリも強く握りかえしてくる。
それも面白えかもな・・・。
タカにしたところで、このままコトリと家族になってもいい気がした。
となりにいるのは、たった9歳の女の子。
でも、ちゃんとタカを愛してくれる女の子。
二度と手放せなくなった大事な宝物。
ずっと一緒にいるさ・・・。
「ただいま。」
タカはコトリと手を繋ぎながら、久しぶりの我が家へと帰った。
繋いだ手のひらは、離さなかった。
しっかりと握りあったふたりの手が、永遠に離れることはないと教えあっているようだった。
朝から、いきなり幼気な女の子を連れて帰ってきたバカ息子に母親が目を丸くして驚いたのは言うまでもない。
「は、早く戻してきな!」
玄関に立っていたタカとコトリを見るなり、悲鳴を上げそうな顔で開口一番にほざいたのが、それだった。
どこによ?・・・。
「ちょっと、その子はなんなのさ?」
不審の目を向ける母親に、タカは真顔で「オレのヨメ。」とだけ答えた。
コトリはむちゃくちゃ嬉しかったらしく、玄関を上がるなり、いきなり膝を折って三つ指を突くと、「お母様、ふつつか者ですが」とか、ほんとにやっていた。
リビングに向かい、我が家の主を探した。
定年後はこれといった職にも就かず、気ままな毎日を過ごしていた親父はステテコに腹巻と純オヤジチックなスタイルで新聞を読んでいた。
「どうしたんだ、それ?」
コトリを目にするなり少し驚いた顔をしていたが、コトリが膝を突いて「お父様、ふつつかものですが・・」とか、またやり始めると、愉快そうに笑って可愛らしい珍客を手招いた。
すぐに膝の上に乗せて満面の笑みを浮かべる。
チンチンのないのが欲しかったって、ずっといってたもんな。
オヤジキラーのコトリは慣れたもん。
「二、三日預かってくれねえか?」
親父に向かって、それだけをいった。
「わかった。」
親父の返事は、至極短いものだった。
深くは訊かなかった。
長年、家族なんてやってりゃ、顔を見ただけで腹の中が読めるようになる。
たぶん、まだ犯罪者にはなってないと踏んだんだろう。
そんなところだ。
「ちょっと、この子大丈夫かい?」
とりあえず、コトリにはタカの部屋を使わせることにして、朝飯がまだだったから、遅い朝食タイム。
フラダンスババアが心配していたのは、コトリの素性じゃなくて小娘の胃袋。
「おいしぃっ!!!」
まあ、食うわ食うわ。
見事に炊飯器は空に。
だし巻き玉子やひじきの煮物なんて日本人にしてみれば当たり前のメニュー。
しかし、オーソドックスな朝食さえも、シホの手料理に比べれば、ごちそうに早変わりしてしまう。
ほんと不憫なヤツ・・・。
「じゃあ、いい子にしてろよ・・・。」
シゲさんとの約束の時間が迫っていた。
今後のことを話し合わなければならない。
「ママを・・・ママを必ず連れて帰ってきてね・・・。」
あの生意気なおてんば娘が、目にいっぱい涙を溜めて懇願していた。
「任せろ。」
タカの自信満々の返事に、涙と鼻水でくしゃくしゃになっていた笑顔。
家を出るときは、さっそくジジイに抱っこされて玄関先で見送ってくれた。
ジジイ、イタズラすんじゃねえぞ。
外に出ようとしたところで「タカ。」と呼ばれた。
振り返った。
コトリの顔が近づいてきて、チュッとキスをしてくれた。
「あ、あんた、まさかほんとに・・・。」
それを見て驚いていたババアの顔。
親父は愉快そうに笑ってたっけ。
「だからヨメだって、いったろ。」
にやり、と笑って、タカは玄関をあとにした。
※元投稿はこちら >>
 (無題) - パイチンは嫌い? 01:17 レス数:70 HOT:69 ↑
(無題) - パイチンは嫌い? 01:17 レス数:70 HOT:69 ↑ 妊娠9ヶ月 - ここに上げる事で出産費用になるの?ただの欲求不満?教えて〜 22:33 レス数:56 HOT:51
妊娠9ヶ月 - ここに上げる事で出産費用になるの?ただの欲求不満?教えて〜 22:33 レス数:56 HOT:51 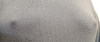 (無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:32
(無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:32  埼㊙️サ㊙️住民他人妻晒し【時限】 - 馬鹿? 00:39 レス数:22 HOT:22
埼㊙️サ㊙️住民他人妻晒し【時限】 - 馬鹿? 00:39 レス数:22 HOT:22