――第45話――
(ハツ、いいか?)
(はいよ・・・。)
オジキが言った通り、鍵は電気メーターの裏側に隠してあった。
タンが取りだして、さっそく鍵穴に通した。
サムターンのシリンダー錠を音を立てないようにゆっくりと回した。
カチリ、と小さな音がして施錠が解けた。
静かにドアを開けて、素早く巨体を中へと滑り込ませた。
こんなことなら朝飯前だ。
これまでにも幾度となくやってきた。
今までにさらってきた人間は数知れない。
男もいれば女もいた。
さらった奴らが、その後どうなったかなんて知ったこっちゃない。
だが、好みの女がいれば少しだけ悪さはさせてもらった。
泣き叫ぶ女の首を絞めて黙らせるのは、何とも言えない愉悦がある。
細い首をちょっと握っただけで、恐怖に顔を引きつらせながら女どもはすぐに黙る。
喉元まで突っ込んで、しゃぶらせる。
首を掴んでいるから、どんな女も必死になる。
白目を剥くまで続ける。
存分に愉しんでから、喉の奥深くに流し込んでやる。
押し込んだままだから、息ができずにむせ返る。
激しくむせって、鼻から精液を噴き出すこともある。
まったくおかしすぎて笑いがとまらねえ。
ガキだって同じだ。
首を握れば、もう逃げられない。
タンもハツも拐かしのプロだ。
女とガキをさらうくらい、俺たちにはなんでもねえ。
(ハツ、目は慣れたか?)
(おう。)
タンもハツもすぐには押し込まなかった。
目が慣れるまで玄関の上がり框に身を屈めて潜んでいた。
見つめる先には、わずかばかりの薄明かり。
豆電球の淡い灯りだけがリビングに残っている。
暗闇にいたから目が慣れるのは早い。
見える範囲に素早く目を走らせて、中の様子をさぐった。
とりあえず、リビングにひとの気配はなさそうだった。
奥に引き戸の閉まった部屋がひとつある。
右手の横に、もうひとつ。
おそらく、そのどちらかが寝室だ。
タンがハツに目配せした。
タンが正面に行く。
ハツは右だ。
足音を殺して前に進んだ。
ふたりとも体重が100キロを越える巨漢なのに足音がしない。
どういうわけか、ミシミシと床の軋む音もしなかった。
タンが、正面の引き戸をわずかに開ける。
中から光が漏れてこない。
なおも開いて隙間から覗く。
薄闇に慣れた目は、そこに住人がいないことをすぐに教えてくれる。
ベッドは置かれているが、いるべきはずの家人の姿がない。
留守か?・・・。
嫌な予感が頭をもたげた。
さらいに行って留守だったことは、まれにある。
拐かすのは素早いが、このふたりに計画なんてものはない。
いつも行き当たりばったりだ。
これが地元なら仕切り直しもできるが、車で数時間以上もかかる場所では簡単に出直すこともできない。
チッ!まずいな・・・。
後ろを振り返った。
ハツの姿がなかった。
どうやら右手の部屋にうまく入ったらしい。
引き戸が開けっ放しになっていた。
出てこないということは、誰かがそこにいるということだ。
少なからずホッとした。
手ぶらでオジキの元に帰れば、何をされるかわからない。
きびすを返して、タンも右手の部屋に入った。
ハツがこちらに背中を向けていた。
じっと、なにかを見おろしている。
(どうした?・・・。)
声をひそめて訊ねた。
ハツの見つめる先に、あどけない顔で眠る少女の姿があった。
期待した家人を見つけて、タンは安堵に胸を撫で下ろす。
とりあえずティラノサウルスに殺されることだけは免れた。
これでなんとか目的のひとつは達成したことになる。
(なにやってやがる?)
ハツが、娘をじっと見つめたまま動かない。
(こ、これ・・・。)
首だけをタンに向けて、嬉しそうに娘の顔を指さした。
(なんだ?)
(か、かわいい・・・。)
目がだらしないほど笑っていた。
「ばっ!!・・・。」
怒鳴りそうになって慌てて声を呑み込んだ。
(バカ野郎、なにマヌケなこと言ってやがる。さっさと仕事しろっ!)
ハツは、ごつい顔をした大男のくせに、とんでもない少女趣味のオカマチックなところがある。
少女そのものはもちろん好きだが、それよりもさらに少女が好きそうな物を好む嗜好がハツには強い。
ハツのプライベートルームには、人形やぬいぐるみが腐るほど飾ってあることをタン以外誰も知らない。
裸にして犯すよりも、着飾らせて眺めるのを好むハツだった。
きっと、ガキの寝顔でもじっくりと眺めながら、頭の中でコスプレでもさせていたのだろう。
(こんな可愛いの、久しぶり・・。)
ごつい顔が嬉しそうに、にやけていた。
気色悪いんだっての!
そりゃそうだろう、こいつはツグミの娘なんだ。
オジキが愛してやまなかった、あのツグミが産んだガキなんだ。
可愛らしいのは当然のことだ。
しかし、確かに見れば見るほど愛らしい顔をしている。
タンも釣られるように上から覗き込んだ。
「タカ・・・タカ・・・。」
ひとの気配を感じたからか、不意に娘の口から寝言がもれた。
なにかを欲しがるようにゆっくりと腕を伸ばしていく。
寝ぼけてやがる。
伸ばした腕の先にあったのは、ハツのごつい顔。
細い腕を巻きつけるように首に絡みつかせて、尖った唇を突き出した。
「タカ・・・チューして・・・。」
ああ?
ずいぶんとませたガキだな。
娘の顔が徐々にハツに近づいていった。
(おっ!おっ!)
ハツが興奮して、鼻息を荒くする。
(こ、こらハツ!お前、手を出すんじゃねえ!オジキに殺されるぞ!)
ハツから引っぺがそうと、娘の細腕を掴んだときだった。
いきなり、デカい目ん玉が開いた。
ハツと娘は、鼻と鼻がくっつくほどの距離でしばらく見つめ合っていた。
「あんた誰?」
聞いたのは娘のほう。
普通の声だった。
「ハ、ハツ・・・・。」
ハツが赤面しながら答えた。
「なにバカ正直に答えてんだ!さっさとずらかるぞ!」
気付かれたんなら仕方ねえ。
このまま、かっさらっちまうだけの話しだ。
こんな小娘ひとり、担ぎ出すなど造作もない。
その時だった。
「キャアアアアアアアアアアアアアアアアアァァァァァッァァッッ!!!!!」
ものすごい悲鳴が、ふたりの鼓膜に襲いかかった。
※元投稿はこちら >>
 妊娠9ヶ月 - ここに上げる事で出産費用になるの?ただの欲求不満?教えて〜 22:33 レス数:56 HOT:56
妊娠9ヶ月 - ここに上げる事で出産費用になるの?ただの欲求不満?教えて〜 22:33 レス数:56 HOT:56  (無題) - 閉じビラビラを接写して見せてください我慢汁がだらだらですよ 23:28 レス数:39 HOT:39 ↑↑↑
(無題) - 閉じビラビラを接写して見せてください我慢汁がだらだらですよ 23:28 レス数:39 HOT:39 ↑↑↑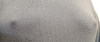 (無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:32
(無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:32