――第43話――
夜が深い。
闇が濃かった。
トリヤマは、ハンドルに乗せた腕にあごをひっかけて、ダッシュボード越しに眺めていた。
するすると真っ黒なハマーが横を通り過ぎていく。
ハマーの向かう先には、小さなアパート。
夜のとばりに建物の陰影が薄く溶けていた。
ハマーは、ヘッドライトもテールランプも点けていなかった。
黒い車体も闇に溶けている。
見上げる空には月もない。
誘拐には絶好の夜。
「はう・・・・うん・・・・あは・・・・。」
ひどく辛そうな息づかいが、背中から聞こえていた。
トリヤマは、ルームミラーにチラリと目を向けた。
タンたちに捕らえられて気を失うまで玩具にされていた少女は、今は和磨の膝の上で意識を覚醒させている。
「あは!・・・ぅん・・・・・ふん・・・。」
薄く開いた唇から、荒い息が漏れていた。
だらりと垂らした前髪の奥で、少女は何かを我慢するように硬く目を閉じている。
後部座席の上に膝で立ちながら助手席のバックシートに薄い胸を合わせる姿は、必至に何かに縋ろうとしているようにも見えた。
「はぁあ・・・うん!・・・・・・あは!・・」
わけのわからない快楽に取り憑かれて、自分でもどうしていいかわからない。
そんな感じだった。
畏れているはずなのに、針金のような細い背中を湾曲にしならせ、小さな尻を和磨に差し出すように突き出してしまう。
まん丸の尻は、淫らにくねって止まらなかった。
小さな手のひらが助手席のバックシートを強く握っている。
「いい子だ・・・ほら、もっと気持ちよくしてやるからな・・・。」
苦しげな呻きに溶けていた呪詛のささやき。
まったくできそうにもない少女の股間に突き刺さっていたのは、血塗れになっていた和磨の指。
相変わらず、すげえな・・・。
顔を俯かせながら呻くだけで、少女に痛がる素振りはなかった。
泣き出しもしない。
ルームミラーの中で妖しく尻をくねらせる小柄な肢体が、まるで操り人形のように見える。
操られているのだった。
和磨の手に掛かったら、どんな少女でも一晩で使えるようになる。
仕込みには悪魔的な技を持つ、和磨だった。
ツグミたちの誘拐が失敗に終わるなど考えていないかのように、和磨は少女の仕込みに熱を入れている。
膨らむ兆しなどまったくない胸をした娘だが、明日の朝には、あの幼気な膣にも和磨のものが深々と突き刺さっていることだろう。
必ず、そうなる。
トリヤマはルームミラーから目を戻した。
暗闇に溶けたハマーが、もうすぐアパートにたどり着く。
車道の端に停めたベンツの中から事の成り行きを見守っていた。
向こうからの合図ひとつで、トリヤマたちも突っ込んでいく。
だから、エンジンは切ってない。
馬力が600近いベンツAMGは、アイドリングだけでも野太い咆吼音を響かせる。
その太い音は車内まで聞こえている。
問題はなかった。
ここに来てから10分ほどが経っているが、すれ違う車は一台もない。
閑散とした住宅街だ。
ツグミは発見を恐れて人目を避けるためにこんな所を選んだのだろうが、返ってそれが仇になった。
ちょっとやそっと騒いだくらいじゃ、誰も飛び出してきそうにない。
問題となるのはアパートの住人だけ。
部屋の数は4つ。
アパート前の駐車場に止まっていた車は3台。
追撃を警戒するなら、タイヤをパンクさせておく必要がある。
考え過ぎか・・・。
粛々とさらう。
誰も気付くはずはない。
ツグミは、今夜のうちに人知れずこの街から消えることになる。
あの日、ツグミが俺たちの街から消えたのと同じように。
あれは、まったく予想外だった。
和磨が逮捕されたことに浮き足立っていた隙を突いて、逃げられた。
やってくれたもんだ。
小娘ひとりで、できる芸当じゃねえ。
陰で糸を引いていた奴はわかっている。
あの銀縁メガネ野郎・・・。
ツグミをさらって落ち着いたら、必ず復讐しに戻ってきてやる。
舐められたまま大人しくしてるほど、俺たちは甘くねえ・・・。
暗闇からハマーが現れた。
アパート前の外灯下に姿を出して、すぐにまた闇の中に消えていく。
灯りの下に停めるほど、あいつ等もバカじゃない。
わずかに通り過ぎてから、ストップランプが明滅する。
停まるのと同時に、ハマーから走り出した三つの影。
車体のドアは開けたままだった。
さすがにあいつ等は慣れてやがる。
大柄なふたつの影が素早く階段を駆け上がっていく。
タンとハツだ。
階段の下で止まっている影がミノ。
タンとハツが目的の部屋の前に辿り着いた。
あとはドアをそっと開けるだけ。
(鍵は電気メーターの裏側にある。それを使って、中に入れ・・・。)
隠し場所は、あらかじめタンたちに教えてあった。
さすがにオジキだ。
鍵の隠し場所まで知っているとは恐れ入る。
ここに来るまでに、ツグミを見つけたカラクリを教えてくれた。
「たまたま偶然だったのさ・・。」
無駄な争いごとを好まないオジキは、ムショの中では模範囚で通っていた。
模範囚として一定の期間が過ぎると、ある程度行動にも自由が与えられ、官の許可する新聞や雑誌の閲覧が許されるようになる。そして、いよいよ出所が近付いてくると、これから出ていく社会に対して免役を持たせるためにテレビ鑑賞なども許可されるようになる。
今年の初めのことだ。
オジキがなにげに眺めていたローカルのニュース番組で、大学のイベントを紹介する放送が流れていた。
とある大学のキャンパスクイーンが、どこかの市長を表敬訪問する内容だった。
ほんのわずかな短いニュースだったが、その中でオジキは見つけたのだ。
一瞬だったが、見逃しはしなかった。
忘れようとしても忘れられない顔。
高校時代からの因縁のライバル。
そして、オジキをこの監獄へと送り込んだ裏切りの男。
重丸伊左久は、確かに画面の中にいた。
たとえほんのわずかでも、あいつの顔を見間違えるわけがない。
あっという間に番組は終わってしまい、子細を確かめることはできなかった。
オジキは、放送を流していたローカル局に手紙を書いた。
放送日の時間や内容から、どこの大学であるかを確かめようとしたのだ。
本当は表敬を受けた市庁舎を聞き出したいところだったが、それでは政治思想を疑われて手紙は受理されない。
だから、大学と書いた。
官には、景観のよいところだから出所したら訪れてみたい、とだけ告げた。
なんの疑いも持たれずに封書は受理された。
そして、返ってきたのが出掛けに見せてくれたあの手紙だ。
表には「如月和磨様」
裏には、テレビ局の名前の入ったスタンプ。
そして、封書の開封部分には検閲済みを示すマル検の赤い文字。
上白紙の便せんには、放送された大学名とその所在地が記載されていた。
親切心のつもりだったのか、わざわざ番組で紹介されていたキャンパスクイーンの名前までもがご丁寧に書いてあった。
その名前を目にしたオジキは、笑いが止まらなかったに違いねえ。
すぐに弁護士を呼んで、調べさせた。
場所がわかってるんだから、難しいことがあるはずもねえ。
じっくりと時間を掛けて丹念に調べた。
そしてツグミの居所を突き止め、習性を知った。
あいつはガキの頃から隙間に物を隠す癖があった。
大人になった今でもそれは変わってなかったらしい。
俺たちが血眼になっても見つけられなかったツグミを、オジキはムショの中から見つけ出しちまいやがった。
さすがにオジキだ。
感心するしかねえ。
だが、不満なこともある。
「なんで、あっし等には教えてくれなかったんですかい?」
車中で、トリヤマはいささか憮然とした表情を浮かべながら和磨に訊ねた。
ツグミを捜していたのはトリヤマ達も同じことだ。
教えてくれれば、すぐに奪い返しに行くことだってできた。
「重丸の野郎が、なにも手を打たずに逃げ出すわけがねえと思っていたからさ・・・。オメエたちが動き出せば、必ず奴は敏感にそれを察知して、なにか別の手を打つに決まっている。俺がいれば別だが、お前らだけであいつの相手は無理だ。だから、俺が出るまで教えなかったのさ・・・。」
和磨には苦い経験がある。
自分の不在中に組を乗っ取られた。
あの忌々しい記憶が、和磨をいやが上にも慎重にさせる。
決してトリヤマ達を信用していないわけではない。
だが、絶対的な信頼を寄せるほどの信用があるわけでもない。
最後は自分で仕留める。
それが和磨という男の哲学となっていた。
「あ・・・うぅ!・・・・あっ!・・・・。」
後ろから聞こえる小娘の呻きが大きくなった。
見据える先では、タンとハツが玄関ドアの解錠に成功したらしい。
ゆっくりと扉を開けて、ふたりが中に入っていく。
「あひ!・・・・ひっ!・・・あっ!」
ガキの声が、しきりに大きくなっていく。
痛みを訴えてるわけじゃない。
わけのわからない気持ちよさに戸惑っているだけだ。
それを証拠に唇の端からは止め処もなくよだれを垂れ流している。
気持ちよすぎて口を閉じることさえ忘れてしまっている。
こんなガキまでよがらせるとは、まったくオジキの腕前には感心するしかない。
このガキも、最後はオジキにとどめを刺されることになる。
仕込みの仕上げは、必ずオジキと決まっていた。
オジキは自分の手で仕上げなければ気が済まない。
俺たちじゃ、「デキソコナイ」しか作れないことを知っているからだ。
俺たちは、オジキにはなれねえ。
だが、それでいい。
「みこし」として担ぐからには、それくらいのお人でなけりゃ担ぎ甲斐もない。
今夜はタンとハツが、ツグミとその娘を肩に担ぐことになるだろう。
あいつ等はプロだ。
あいつ等にかかれば、人をさらうことなど造作もない。
さらっちまいさえすれば、こっちのもんだ。
またオジキがしっかりと仕込んでくださる。
二度と逃げださねえように、ツグミは念入りに仕込まれるこったろう。
もちろん、娘のほうもだ。
あのツグミの娘ならば期待が持てる。
だからこそオジキだって執着するんだ。
後ろから聞こえてくる可愛い声を耳にしながら、トリヤマはほくそ笑んだ。
車内には、重厚なエンジン音と小娘のよがる声だけが聞こえている。
もうすぐここに、ツグミが加わる。
重丸・・・テメエには何も出来ねえ・・・。
腹を抱えて笑い出しそうになるのをトリヤマは必死に堪えた。
※元投稿はこちら >>
 妊娠9ヶ月 - ここに上げる事で出産費用になるの?ただの欲求不満?教えて〜 22:33 レス数:56 HOT:56
妊娠9ヶ月 - ここに上げる事で出産費用になるの?ただの欲求不満?教えて〜 22:33 レス数:56 HOT:56  (無題) - 閉じビラビラを接写して見せてください我慢汁がだらだらですよ 23:28 レス数:39 HOT:39 ↑↑↑
(無題) - 閉じビラビラを接写して見せてください我慢汁がだらだらですよ 23:28 レス数:39 HOT:39 ↑↑↑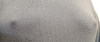 (無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:32
(無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:32