穢れを知らない少女のようなまゆみの唇が、秀則のペニスの幹を這う。仰向けになった秀則の両脚の間にまゆみは四つん這いになり、その右手の指先は、黒い毛が密生した根元を軽く摘まみ、時折下へ向けてやさしく動かす。小さなピンクの舌が、肉棒の表面をなめらかに滑る。
秀則の胸が上下し、目はかたく閉ざされ、手がシーツを掴む。次第に固さが増してくる。まゆみのよだれで幹が光る。ペニスがぴくんと脈打ち、先端から秀則自身の液体がとろりと流れ出た。
「――気持ちいい?」
目を細めて、まゆみは悪戯っぽくささやく。
「――うん――。」
先端に口づけ。秀則の大きなため息。透明な液体を、口で吸い取ると、ゆっくりと、まゆみは秀則の亀頭に唇を被せてゆく。秀則が腰を浮かせる。深く、もっと奥へ。ペニスの大きさがどんどん増して、固くなる。ほぼ完全に勃起した陰茎を小さな口に精いっぱい頬張ると、まゆみは、舌をその周囲に巡らせる。唾液と愛液にまみれた唇で、ペニスを軽く閉めつけながら。
秀則の手が蒲団の端を握りしめる。
「――ああ、だめ、先生――、きもちよすぎる――」
「――まだ――」
もごもごと不明瞭な声がまゆみの喉から発せられる。
「――だめよ――。」
まゆみが顔をゆっくりと上下させると、秀則はその頭を両手で挟み、懇願する。
「ああっ――、だめ、先生――でちゃうよ――!」
指を動かしながら、まゆみは涎に濡れた顔を上げる。前髪が目にかぶさっている。
「――さっき出したばかりなのに?」
熱く輝くその目に向かって、秀則は救いを求める人の表情で、必死に訴える。
「――だって、よすぎる、先生――、きもちよすぎて――」
まゆみの顔に、いじわるな、それでいて子供のような笑みが広がる。
「――ふふ、だめよ、山岡くん。今度は先生を満足させてくれるんでしょ?」
まゆみの指の動きに応えて、秀則のものはもう完全に復活していた。まゆみは上体を起こし、腰を浮かせると、きれいな太ももを持ちあげて秀則の胴体を跨いだ。ふわっとした縮れ毛の先端に、雫がきらりと光る。少女のような白い裸体。それと似つかわしくない、むっちりとした腰と太ももを見て、秀則のペニスがまたどくんと反応する。まゆみは大きく両脚を拡げ、腰をかがめた。そそり立つ肉の棒を求めて、その先端を探して、ふっくらとした割れ目が、少しずつ降りてくる。
信じられないほどやわらかな、ピンク色に開いた花びらが、秀則の男根の先に触れた。まゆみは目を閉じ、固く眉を寄せる。半開きの唇から大きなため息が漏れた。そのまま少しずつ体重をかけ、ゆっくりと身を沈める。ずぶ、ずぶ、と太いペニスを徐々に受け入れるまゆみの性器から、蜜があふれ出た。
「――はあ――!」
「あああっ――」
二人が同時に声を上げる。甘い苦悶の表情を浮かべて、まゆみは大きく仰け反った。
「――んっ――! す、すご――、すごいよ、山岡くん――」
目に涙さえ浮かべ、まゆみは身悶えた。
「――こ、――ああっ――、ふ――太い――、すご――、あ、――ああっ、山岡くん――!」
「――先生――!」
小さな花びらを押し広げ、秀則のペニスがついに根元までまゆみの中に入った。まゆみは口を開けたまま宙を仰ぐ。声にならない。
髪を振り乱し、必死の面持ちでまゆみは秀則の顔に手を伸ばした。秀則の手がそれを迎える。指と指が互いに絡みつく。
「――あぁ、――やま、おか、くん――、奥まで、入ったよ――」
まゆみは秀則に覆いかぶさると、彼の両脇の間に手をついた。顔と顔が近くなる。まゆみは真っ赤だった。そしてゆっくりと、腰がグラインドする。秀則の陰茎を中心に、両脚をM字に拡げたまゆみの腰が、ねっとりと円を描く。秀則の右手はまゆみの腕を、左手が彼女の細い腰をつかむ。
「――っ! ――せ、――だめ、そ――そんなに、動いちゃ――」
悩ましげな視線を秀則に投げかけ、まゆみはなおも腰を動かす。
「――はあ、――ああ、――いやよ、まだ――終わっちゃ――」
「――あぁ、――だって――」
「――我慢するのよ ――山岡くん、――お願い――」
秀則の全身が硬直した。指がまゆみの腕に食い込む。汗ばんだ顔でニッと笑うと、まゆみは腰をゆっくりと浮かせた。二人の口からため息が溢れる。まゆみの秘所から、蜜に濡れた男根が半分現われる。そしてまた下へ――ピンクのひだが、飢えた生き物の唇のように、ペニスをゆっくりと咥えこんでゆく。秀則が大きく喘いだ。まゆみの薄い乳房に咲いた乳首が、大きくふくらんでいる。びくん!とペニスがうごめいた。
「ああっ!」
仰け反って、天井を仰ぐまゆみは、しなやかな、妖しい魚のようにぴちっとはねた。
「――ああん、おちんちん、――また、大きくなったよ――」
ゆっくりと、ゆっくりとまゆみの腰が上下した。秀則は、自分の腹の上で悩ましく踊り続けるまゆみの美しい身体に目を奪われている。必死でその目を放そうとする。その姿を見ているだけで爆発しそうだ。他の事を考えなくては。
目を閉じる。まゆみの切ない鳴き声。――いや、無理だ。これ以上ないほどに固く太くなったペニスを捕まえて離そうとしない、濡れた、やわらかい罠。
秀則は両手でまゆみの腰をつかむ。なんて細くしなやかな腰だろう。何かに突き動かされるかのように前後に動こうとする彼女の身体を、力いっぱい押さえつけた。息を止めたまま、数秒が経過する。まゆみの切ないため息。秀則の下半身の圧力が、ある一点を通過する。秀則は大きく息を吐きだし、指の力を緩めた。そしてまゆみと向かい合うように、上体を起こす。
何て小さいんだろう、幼い子供のようだ――と秀則は、まゆみの真っ白な薄い乳房とすんなりとした肩を見て、またため息をつく。しかし、互いに向き合ったまま秀則にまたがったその下半身は、艶めかしく肉付きのよい、立派に成熟した紛れもない大人の女性の肉体だった。
まゆみの細い腰を両手でつかみ、ゆっくりと回し始める。まゆみは秀則の肩に手を伸ばした。
紅い汗ばんだ顔が目の前だ。
「――あぁ、――あ、――き――、ああ、す、すごい――」
まゆみは驚くほど軽かった。秀則はまゆみの身体を少し持ち上げ、上下に動かす。苦悶に近い表情を浮かべたまゆみの目が潤み、小さな鼻の穴がぴくんとふくらんだ。
「――ああ、あ、――山岡くん――」
「――先生、――きもち、いい?」
「――あ、――うん、――あぁ、――うん、すっごく――!」
今は秀則の方が主導していた。両腕をまゆみの開いた両腿の下にまわすと、抱き寄せ、結合したまま彼女の身体を持ち上げた。まゆみは秀則に抱きつき、しがみつく。秀則は蒲団に片ひざをつき、そのまま立ち上がる。まゆみの頭が電灯のひもに触れた。部屋の中央に立ったまま、秀則は両腕に抱えたまゆみの腰を、自分の下半身に押しつける。秀則の首に抱きついたまま、まゆみが鳴き声をあげる。二階の洗濯機の音はいつの間にか止まっていた。秀則の激しい息遣いと、まゆみの喘ぐ声がのどかな昼下がりの静かな部屋に、響き渡った。
やがて秀則はゆっくりと腰を下ろし、片ひざをついた。そしてもう片方も。まゆみを大切そうに抱きかかえたまま、その小さな体を蒲団の上に仰向けに横たえる。白い太ももを拡げて腕に抱えたまま。秀則は今度は上からのしかかるように、肉棒を打ち込む。彼女の圧倒的な支配からいつの間にか逃れ、今や彼は荒々しい自信を持って、太いペニスをまゆみの陰部に深々と差し込んだ。まゆみは目をぎゅっと閉じ、秀則の腕に自分の細い腕を巻きつける。口が勝手に開く。
「――ああっ、――ああ、あ、ああ、だめ、――ああ――!」
「――先生、――すてきだよ、――先生――!」
秀則を迎えるまゆみの腰は、彼女の意思と関係なく動き続ける。その泉から溢れでる恥ずかしい蜜は白い肌をつたって流れ、蒲団に染みとなって広がってゆく。まゆみの身体が仰け反り、緊張する。
「――ああっ、あっ、――あ、――い、いく、いっちゃうう――!」
秀則の腰のピストン運動が、より一層速くなる。まゆみの呼吸が止まった。口を大きく開き、固く目を閉じたまま、両手が秀則の腕を握りしめる。秀則は、ぐいっとペニスをまゆみの奥深くに突き挿れた。肉の棒がどくん、と脈を打つと、まゆみの身体がぴくんと跳ね、その口から「あ!」と悲鳴が漏れる。
肩で息をしながら仰向けに横たわるまゆみの谷間にまだペニスを入れたまま、秀則は顔を近づけ、ささやく。
「先生、もっとしたい――。今度は後ろからさせて。」
まゆみはとろんとした目を秀則に向け、ゆっくりとうなづいた。秀則はまゆみの左脚を持ちあげると、その身体をやさしく回転させる。互いの陰部をぴったりと押し付け合ったまま、まゆみを腹ばいにさせ、今度は背中側から両手で腰を支えて、まゆみを四つん這いにさせた。滑らかな肌に覆われた、真っ白な背中。引き締まった腰から、大きな桃のような、これも純白の、ふんわりとした尻へと曲線が続く。その姿を見て、秀則の口からはため息がこぼれ、そのペニスは再び大きな鼓動を打ち、まゆみは声をあげて仰け反る。
「――ああん――、だめ、大きく、しないで――。これ以上、おちんちん大きくなったら、先生――」
秀則は腰をゆっくりと後ろへ引く。むっちりとしたゴムのようなまゆみの花びらと、ゆっくりと姿を現すペニスの継ぎ目から、透明な蜜がとろりと流れでる。
「――はあっ――!」
ぱんぱんに膨れた幹と、固くなった鬼頭の境目のくびれた部分を、まゆみの膣の入り口近くで、止める。まゆみの全身がびくんと動き、いやらしい下の唇が、ペニスをぎゅっと締めつけた。
「――んんっ――、――はぁ、――あぁ、」
「――はあ、――先生、――すごいよ、――すごく、いい――」
再びゆっくりとペニスが奥へ差し込まれる。秀則の指が、ほんのりとピンク色に染まったまゆみのマシュマロのような尻に喰い込んだ。
「――ああ、――ああっ、――だめ、また、大きくなったよ――、山崎くんのおちんちん、また――大きくなった――」
陰茎に血液が送り込まれるたびに、まゆみの身体を衝撃が走る。そのたびに、どんどん幹が太くなってきくかのように、まゆみは感じられるのだった。
隣りのアパートのテレビの音が消えた。
思春期にみんなの憧れだった、加賀谷先生が今、この小さなアパートの一室で、蒲団の上に全裸で四つん這いになり、尻を突き上げている。そして股間に咲いた妖しい花からは蜜があふれ、その中央を、固く勃起した自分のペニスが深々と貫いている。その姿は、狂おしい情欲に燃える、発情しきった一頭の、牝。あの美人でやさしい、清楚な、加賀谷先生。そして、旦那の留守中に、十才年下の男の部屋を訪れ、かつての教え子の陰茎を咥え、しゃぶり、自らまたがり、腰を振る、淫乱な加賀谷先生。これは夢だろうか。混乱した頭を横に振り、秀則はいきり立つ陰茎を更に深くまゆみのひだの間に挿し込む。深く――もっと深く。
「――ああん、あ、――あああっ――、やま――、あ、ああっ、――す、すご――、ああ、
――山岡――くん――、すごい、――ああ、だめ――、お――おか――、おかしくなる――、
先生、おかしくなっちゃう――!」
じゅるっ、くちゃっ、という音が激しくなる。シーツを握りしめるまゆみの指。彼女の白い太ももを蜜がつたい降りる。秀則の腰がまゆみの尻を打つ、ぱん、ぱん、という音がどんどん早くなる。打つたびにぷるんぷるんと揺れる尻の肉がほんのりと紅く染まり、まゆみの背中が弓のようにしなった。
「――んんっ――、はぁ、――あ、ああ、――ああっ! ――せ、――ああん、
――先生― もう――、ああ、山岡くんっ――」
「――はあ、は―、せ、先生――」
秀則が歯を喰いしばって天を仰ぎ、腰を更に激しく振ると、まゆみは全身を硬直させ、シーツを握りしめて、絶叫する。
「あああああっ――!」
二人の呼吸が同時に止まり、時間も静止した。そして次の瞬間、秀則が腰を後ろに引き、ぬらぬらと光るペニスが引き抜かれた。サイレント映画のように口を開けたままゆっくりと蒲団の上に崩れ落ちるまゆみの背中に、愛液にまみれた陰茎が向けられたその瞬間、先端から真っ白い液がほとばしる。ふっくらとした尻の上に、真っ白な背中の上に、どろりとした精液が、ぼたぼたと落ちた。その生温かい感触を待っていたかのように、まゆみが深いため息をついた。
「――ああ――、――はあ、――はぁ、」
背中を曲げた秀則も、まゆみの傍らにひざをつき、大きく長い息を吐く。ペニスがぴくんと揺れ、また数滴、白いものがまゆみの尻に落ちる。まゆみの全身に鳥肌が走った。目を閉じ、激しい息遣いで、左手がゆっくりと隣りをさぐる。その手を握り、秀則はまゆみの横に転がった。
無言のまま、二人は肩で息をする。まゆみは秀則の方へ顔を向けた。汗ばんだ額、肌に貼りついた髪の毛、熱っぽくぼんやりとした目。秀則も呼吸を整えられないまま、まゆみの疲れ切った顔を見つめ返した。しばらくして、まゆみは半分だけ開いた目を更に細め、秀則に笑顔を送る。秀則は唇をまゆみのそれと重ねた。
「――よかった――。すごく。」
「――僕も。すごく、きもちよかった――」
互いを胸に抱きしめあい、それ以上何もしゃべらず、まゆみと秀則はゆっくりと眠りに落ちていった。
幻のような夢と現実が交互に過ぎてゆく。
暖かい風が吹く季節、秀則はいつものように会社を出る。携帯の電源を入れると、彼の手の中でそれは低く唸り、振動する。画面に浮かぶ「加賀谷先生」の表示。
明日の午後、会える?
拒めるわけがない。
まゆみの名前を見ただけで、股間のものが疼き、ジーンズが膨らむ。まゆみの姿を思い浮かべるだけで、生温かいものが下着を濡らす。家に帰り着くと、いてもたってもいられず、ジーンズを下ろし、秀則は、もはやあのからだの虜になってしまった自分の性器が、彼女を求めて固く大きくなっているのを呆然と見下ろす。
またまゆみに会える、その期待に、すでに透明な液が滴りはじめている。もはや、まゆみの名前、姿、ただ一片の面影だけでも、ペニスを瞬時に勃起させるようになっていた。
明日まで精力をとっておかなければ、そう頭では思うが、我慢できない。我慢なんて、出来るはずがない。目に焼き付けられた、美しいまゆみの裸身。あの冬の日以来、この部屋で、この数ヶ月の間、何度も繰り返された、愛欲の行為。
テーブルに座らせて―― バスルームで壁に手をつかせて背後から――互いのものを口で――
その記憶が、秀則と、秀則の陰茎を支配する。
秀則の指が自分のペニスをしごく。――このまま明日までなんて、待てない。あのからだが、今すぐ欲しい。
加賀谷先生、早くここに来て。早くこれをしゃぶって。早く挿れさせて。加賀谷先生――、
――早く――。
< おしまい >
※元投稿はこちら >>
 吸引してデカ乳首♡ - すごいエッチなコメントありがとうございます…♡公衆トイレとかで無理矢理オチンポ入 11:59 レス数:36 HOT:33
吸引してデカ乳首♡ - すごいエッチなコメントありがとうございます…♡公衆トイレとかで無理矢理オチンポ入 11:59 レス数:36 HOT:33  彼撮り動画 - 茜さんが、そう言うなら…夜にお待ちしていますブラ姿もお願いしときます 10:40 レス数:134 HOT:28
彼撮り動画 - 茜さんが、そう言うなら…夜にお待ちしていますブラ姿もお願いしときます 10:40 レス数:134 HOT:28 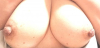 (*ˊ˘ˋ*)。♪:*° - おっぱい星人だけど自分もすっきりしたいな 03:13 レス数:21 HOT:20
(*ˊ˘ˋ*)。♪:*° - おっぱい星人だけど自分もすっきりしたいな 03:13 レス数:21 HOT:20  デカパイダンス - 会いたい(^^) 12:18 レス数:18 HOT:17 ↑
デカパイダンス - 会いたい(^^) 12:18 レス数:18 HOT:17 ↑ 58歳ザーメン処理 - 58歳て、サバ読みすぎ(笑) 11:50 レス数:17 HOT:17
58歳ザーメン処理 - 58歳て、サバ読みすぎ(笑) 11:50 レス数:17 HOT:17