長い冬に突然割り込んできた、春のような陽ざし。駅へ向かう秀則の足は綿毛のように軽かった。
今日はいつものような、ありふれた土曜日じゃない。改札口の前に立つまゆみを見つけると、秀則の胸の鼓動は一段と高まった。アパートからは徒歩二分の距離なので、秀則は室内着のままだった。まゆみも春のような軽い装いで、白いブラウスの上に淡いピンクのジャケットを羽織り、ひざの見える黒いスカートとスニーカーを履いている。秀則を見つけると笑顔で手を振った。
「おはようございます!」
「おはよう。」
息を切らせて走り寄ったが、すぐに次の言葉がでずに、秀則はまた自分の顔が紅くなるのを感じた。まゆみは照れた素振りも見せなかった。
「休みなのに、こんなに早く、ごめんね。」
「いいんです。先生のほうこそ、遠いのに。」
「あたしは平気。いつも早いのよ。おばあちゃんみたいでしょ。」
まゆみの笑顔は屈託がなく、秀則は再び、昨夜のカラオケでの出来事が夢ではなかったのかと、我を疑った。
いや、夢じゃない。その証拠に、まゆみがなんのためらいもなく、秀則の腕をとった。
「――ねえ、あたしのこと、頭が変になったかと思ってない?」
「――まさか。」
「――昨日時間があったのもね、主人が出張に出てるからなの。でももちろん、一応家には帰らないといけなくてね。主人からメールが入ってたらチェックしとかなきゃ困るし、家の電話に留守電が入ってたら、そっちから返事しないと変に思われるかもしれないでしょ。」
「――うん。」
秀則はまゆみと、アパートへ向かって歩いた。穏やかな日差しだった。まだ午前11時を過ぎたばかり。
「でも先生、大胆だな。」
まゆみはうつむき、スニーカーを履いた二人の足を見下ろした。
「――昨日のこと? ――そうね。自分でもびっくりしたわ。でも、山岡くんもそうでしょ?」
「でも、先生から――」
急に秀則は小声になった。
「――キスしてきたんだもん。」
「――そうよね。いけなかった?」
「ううん。」
まゆみは顔を上げた。
「ね、誤解して欲しくないの。あたしね、あんなことしたの初めてよ。」
「――うそ。」
「嘘じゃないよ。結婚してるし――、それに、主人とだって、若い頃だって、あんな場所であんなことしたことなんてなかったわ。」
「ほんとに?」
「本当よ。」
秀則はまゆみの手を強く握った。
「――僕も、カラオケボックスは、初めて。」
「あたし、だめね。――あんなことする気なんてなかったのに。しかもね、お店を出た時も、そのあとお茶してた時も、あんなことはもうしないって決めてたのに。」
二人は木造の古いアパートの前に来た。無言のまま、秀則は一階の一室のドアを開いた。まゆみが滑り込む。秀則がそれに続き、ドアを閉めた。薄暗い部屋の中には目もくれず、靴も脱がないまま、まゆみは爪先立ち、秀則の首に両腕を投げかけた。乾いた、熱い唇が、秀則の舌を貪った。真剣な眼差しで、まゆみがささやく。
「――でもね――」
再び、秀則の目の前で、少女が牝に変貌した。
「――我慢できなくなっちゃったの。――電車に乗って一分も経たないうちに。明日も時間があるのになって、ずっと思ってたのよ、歩きながら。そうしたらやっぱりどうしても会いたくなって。」
秀則の身体に腕を巻きつけ、まゆみは顔を彼の胸に押し当てた。
「――したくなって。もっとちゃんと、山岡くんとしたくなって、我慢できなくなったの――」
畳に敷いた布団の上で、互いの舌が、額を、首を、まぶたを這う。唇が耳たぶを挟む。舌が耳の中へ入り込む。秀則はまゆみの、まゆみは秀則の衣服を、次々と、何かにとり憑かれたように剥ぎ取ってゆく。素肌を熱い手が、指がまさぐり、互いの荒い呼吸が一つになる。
隣りの部屋から、テレビの音が聞こえる。天井からは洗濯機の振動が微かに響いてくる。わずかなカーテンの隙間から、休日の日差しが入り込む。枕元の畳の上に置かれたまゆみのメガネが、全て他人事とでも言うかのように冷たく光る。まゆみの薄いセーターが脱がされ、乱暴に引き下ろされたスカートと共に部屋の隅に転がった。古びた部屋の暗がりの中で、まゆみの白い裸身がまばゆい輝きを放った。純白のやわらかいブラジャーと、同じく真っ白な薄いパンティーだけの姿になったまゆみを見ると、秀則は蒲団に膝をつき、夢中でまゆみを抱きしめ、その小さくふくらんだ胸に顔を埋めた。まゆみはその顔を見下ろし、愛しげに髪に指を走らせる。熱い吐息が何度も何度もまゆみの口からもれる。
すっきりとした首、細い肩、やわらかな線を描く腕。控えめにふくらむ乳房は、乙女のような恥じらいを装っている。贅肉のかけらも見られない、滑らかな腹部。しなやかに引き締まったその腰は、上半身とは一見別人のように成熟した印象をもつ豊かな尻へと、なだらかな曲線を描いていた。むっちりとした臀部から、二本の太ももへ、身長の割に長い見事な両脚へと、美しいカーブが続く。そしてその全てが、しっとりと滑らかな、白い肌で覆われていた。
「――先生――!」
秀則の頭から、最期に残っていたわずかなためらいと恥じらいが消え失せた。
「――はぁ、――山岡くん――、」
このまばゆいばかりの裸身が女神でないとしたら、むしろそれは小悪魔に違いない。秀則は、まゆみを蒲団の上に引き倒すと、ブラジャーを乱暴に脱がせ、覆いかぶさった。大きな両手で、露わになったまゆみの乳房をわしづかみにする。意外に大きく、茶色っぽい乳首が、少しふくらんでいた。秀則は夢中でしゃぶりついた。
「――あ、――ああんっ――、」
両手で胸を強く揉みながら、秀則は右の乳首を口に含み、吸った。舌は乳首を舐めまわし、唇がその根元、乳輪近くを甘く締めつけた。
「――はあ、――はあ――、――恥ずかしい――、小さいでしょ、先生のおっぱい――」
両方の乳首を指先でつまむと、まゆみが背中を反らせた。
「――あん――!」
「――先生、きれいだよ、先生の胸、すっごくきれい――」
「――うれしい、山岡くん、やさし――、ああっ!」
これ以上とても待てなかった。秀則は右手を伸ばし、まゆみのパンティーに指をかけると、一気に引き下げ、足首から外して放り投げた。自分の下着も、転びそうになりながら乱暴に脱ぎすてる。その股間に、すでに透明な液を垂らしながら、褐色のペニスが雄々しくそそり勃った。まゆみのふっくらとした割れ目をじっくりと見ている余裕は、秀則にはなかった。完全に発情した秀則は、まゆみの白い肉体に狂ったように欲情し、その男根は破裂する一歩手前だった。
白い谷間にきらりと光る露に一瞥を投げ、秀則はまゆみの両脚を開くと、間に腰を入れて覆いかぶさった。まゆみが秀則の舌を吸う。ペニスの先が、まゆみの花びらを探す。まゆみが大きく息を吸った。やわらかな茂みを掻き分け、固くなった頭が、ひだの間をまさぐった。
「――はあ、はあ、ああ、――ああ――」
まゆみは腰を動かし、秀則を迎え入れようとする。秀則のペニスが秘密の入り口を探し当てた。
「――あ、そ、そこ――」
蜜をあふれさせ、ぬるっ、と先端が膣に入り込んだ。
「――あっ―――!」
まゆみの細い腕が秀則の背中を抱きしめた。秀則が腰を沈めると、ペニスはあっけなくまゆみを貫いた。
「――あああっ――、あ、――ああん、はあ、――はあ――」
大きく開いたまゆみの口をついて、あとからあとから、叫び声が響く。隣の部屋のテレビはまだ聞こえる。秀則は夢中で腰を振る。どくん、と男根が脈打つたびに、まゆみは悲鳴をあげる。
「ああっ! ――ああん、――大きくなった――」
「――先生――」
「はあ、あ、――ああっ、大きくなったよ、――山岡くんの、おちんちん、また大きくなった――!」
「――先生、すごい――、いいよ――」
大きく拡げた両脚が揺れ、まゆみの腰も前後に動き続けた。眉を八の字にぎゅっと寄せ、泣き出しそうな切ない目を秀則に向け、まゆみは首を振った。
「ああっ――、いい、山岡くん、いいの――!」
「――先生、だめ――そんなに動いたら、すぐいっちゃう――」
まゆみは秀則の首を抱き寄せた。そして夢中で唇を吸い、教え子の熱に浮かされた顔に、まっすぐささやいた。
「――ああ、――はあ、――いいよ、――いっていいの。我慢しないで――ああ、あ、いって!」
「――先生――、もう、だめ――!」
秀則が歯を食いしばった。一瞬動きが止まる。息を止めたまま、彼は腰を引き放すと、片ひざをつき、まゆみの真っ白な腹部にペニスを向けた。それと同時に、白い液体がほとばしった。お腹の上に、薄い乳房に、肩甲骨の上にも一雫、精液が飛び散った。長いため息をつく秀則。その男根の先から、ぽたり、ぽたりと、まゆみの茂みの上に、白い雫が落ちた。秀則は、ゆっくりとまゆみの身体の上に倒れ込んだ。まだ息を切らしている。まゆみの小さな鼻がふくらんで、うっとりとした目は謎めいた光を宿していた。ぐったりと、眠るように目を閉じた秀則の背中をまゆみは左腕で抱き、右手でやさしく髪の毛を梳いた。
「――先生――」
小さな、ため息混じりの声だった。
「なあに?」
「――死んじゃいそう――」
「――まあ、そんなに?」
「――すっごい――、よかった。」
「――うふふ、先生もうれしいな。お世辞じゃない?」
「――まさか。」
秀則はまゆみの隣りにどさりと横たわり、その半身をまゆみに被せた。右脚をまゆみの下半身の上に。そして右の掌を、しっとりと汗ばんだまゆみの右の乳房に載せた。
「――こんなちっちゃなおっぱいで、もの足りないでしょ。」
秀則はまゆみの頬にキスをした。そしてティッシュを手に、まゆみの身体に残る精液を拭き取る。
「ううん。そんなまさか。先生のおっぱい、すごくかわいい。すごくきれい。――さわっても、きもちいいよ、すごく。夢みたい。」
まゆみは目を細め、まぶたで頷いた。隣の部屋から、テレビ番組の笑い声が聞こえる。
「聞こえちゃったかしら、お隣に。」
「僕なら平気。」
「評判落ちるわよ。」
「全く女っ気がないより、いいんじゃないかな。」
二人は、今は穏やかに、互いの身体に腕を回し、唇を合わせた。
「ねえ、あたしのこと、がっかりしてないよね。」
「――ううん。どうして?」
「真面目な、固い人だと思ってたでしょ。」
秀則は少し考えると、ゆっくりと答えた。
「うん。でも――、がっかりはしないな。どうしてだろ。」
「人妻なのに?」
「――そうだね――」
「あのね――」
まゆみは秀則の肩に頬を寄せた。すべすべの身体を、秀則にぴったりとくっつけた。
「――あたし――、先生はね、教師だし、結婚してるけど、それでもね、生身の女なの。」
秀則は黙ったまま、まゆみの髪に唇を寄せた。
「――修道院に入ったわけじゃないし――」
まゆみは秀則の指に自分の指を絡ませた。
「――性欲だって、あるの。――あたしね、もう何年も、ないのよ、主人との間に。」
「――そうなの?」
「もう五年になるかな。」
「――五年!」
まゆみが微笑んだ。
「そうよ。長いでしょ。今の言葉で言うと、セックスレスってやつね。」
秀則はまじまじとまゆみを見詰めた。
「いやね、そんなに見て。――長いでしょ。五年よ。――うちの人、お酒飲むのよね。――酔った勢いだけで抱かれてるような気がすることって、あるのよ。わかる? 雑な感じがしたのね、ある日。お酒臭いのも嫌だったし。もうその時、結婚してから五、六年たってたから、そもそもそういうことをする回数が減ってたし、お酒飲んだ時しかセックスをしようとしなくなってたのね、彼。だからそれが嫌になって、ある時、言っちゃったの。お酒臭いのイヤだって。酔ってる時はさわらないで、って。」
まゆみは深いため息をついた。秀則はその細い肩を抱いた。
「――すっごく険悪な空気になって。後悔したわ。彼は彼で、マンネリになってきてて、慣れ合いすぎてて、素面の時にあたしを求めるのが照れくさくなってたのかもね。後でそう思ったの。――それからは、意地の張り合いよ。飲んで帰った時も、そうでない時も、あたしに見向きもしなくなったの。」
「こんなにきれいなのに?」
「――ありがと。――ほんとは背が高くて胸の大きな人がいいのかもよ。――あのね、どんなものにも人は慣れて、当たり前になって、感動しなくなっちゃうのよ。十年以上連れ添っている夫婦で、結婚当時の気持ちのままでいるのって、珍しいと思うな。うまくいってる人、仲良くしてる人は、もちろんいるわよ。でも、エッチなことしたい、そういう気持ちを――そういう関係を長年保ってる夫婦って、どれぐらいいるのかしら。」
「先生みたいな人といて我慢できるなんて!」
まゆみはじっと秀則の瞳を見つめた。
「その気持ちも、意外にあっけなく無くなるのよ。――それに、もうかなり前から、東京に来た頃から、主人とは別々の部屋に寝てるの。でもね、不思議なもので、表面は何事もなかったように、仲良くしてるのよ。近所づきあいも、会社の同僚とも一緒にご飯食べたり。彼の親も、何も気付いてないわ、きっと。元々子供も出来なかったし。――ただ、とにかく、ロマンティックなムードとか、エロティックな感覚は、とうに感じなくなったわ。あたしの側も。」
秀則は、天井を見つめるまゆみの美しい横顔を、盗み見た。大学生の時も、卒業してから地元を離れる前にも、恋人がいたことはあった。そう、彼の人生で身体を知っているのはその二人だけだったのだ。彼はまだ基本的な性の快楽しか学んでおらず、男と女が人生を連れ添うということの難しさについて、今この瞬間まで真剣に考えたこともなかった。
「ねえ、主人以外の人とこんなことをした言い訳をするわけじゃないけど、女の人にもね、欲求はあるのよ。男の人とはちょっと違う種類の欲求かもしれないけど、女性も――あたしも、やぱりセックスがしたいの。必要なの。――わかる?」
「うん、わかると思う。」
「昨日の夜――」
まゆみの頬が赤らんだ。
「――自分の指以外で――さわられたの――、すっごく久しぶりだった。男の人の――」
鈴の音のような細い声が、かすれた。
「――おちんちんを見たのも。――だからもう、さっきなんか――」
紅くなった笑顔を、まゆみは左手で覆い隠した。
「僕も久しぶりだった――。四年ぶりぐらいじゃないかな。――ねえ、先生――」
上目遣いで、まゆみは秀則の顔を覗いた。
「さっき、たりなかったでしょ。」
「――え?」
「先生、いかなかったでしょ、さっき。」
まゆみは小さくうなづいた。
「――うん。」
「してあげる。」
「――してくれるの。」
まゆみの鼻息が秀則の肩をなでた。秀則は手を伸ばすと、まゆみの太ももの付け根をさぐった。
「もちろん。先生も昨日、僕にも終わらせてくれたじゃない。」
まゆみの手がその腕をそっとつかんだ。
「――ね、こっちでして欲しいな。」
彼女の小さな手が、秀則の手を、彼のペニスに導いた。
「出来るかな。」
「もちろんよ。まだ若いんだし。すぐに元気になるわ。」
ひんやりとした細い指で幹をさすられ、秀則のペニス少し弾力が戻った。頭がわずかに持ち上がる。まゆみが上半身を起こした。神秘的な笑みを浮かべて、まゆみは秀則にささやきかけた。
「――先生に、まかせて――。」
※元投稿はこちら >>
 吸引してデカ乳首♡ - すごいエッチなコメントありがとうございます…♡公衆トイレとかで無理矢理オチンポ入 11:59 レス数:36 HOT:33
吸引してデカ乳首♡ - すごいエッチなコメントありがとうございます…♡公衆トイレとかで無理矢理オチンポ入 11:59 レス数:36 HOT:33  彼撮り動画 - 茜さんが、そう言うなら…夜にお待ちしていますブラ姿もお願いしときます 10:40 レス数:134 HOT:28
彼撮り動画 - 茜さんが、そう言うなら…夜にお待ちしていますブラ姿もお願いしときます 10:40 レス数:134 HOT:28 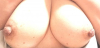 (*ˊ˘ˋ*)。♪:*° - おっぱい星人だけど自分もすっきりしたいな 03:13 レス数:21 HOT:20
(*ˊ˘ˋ*)。♪:*° - おっぱい星人だけど自分もすっきりしたいな 03:13 レス数:21 HOT:20  デカパイダンス - 会いたい(^^) 12:18 レス数:18 HOT:17 ↑
デカパイダンス - 会いたい(^^) 12:18 レス数:18 HOT:17 ↑ 58歳ザーメン処理 - 58歳て、サバ読みすぎ(笑) 11:50 レス数:17 HOT:17
58歳ザーメン処理 - 58歳て、サバ読みすぎ(笑) 11:50 レス数:17 HOT:17