夫と娘は鹿児島へ旅立ちました。娘は私が行けないと知って、最初、半べそをかきました。そんな姿をみると、思わず、私もこみ上げてくるものがあって、涙が止まりませんでした。『香奈・・・ゴメンね・・・だらしない母親で・・・』時計の針は午後4時を指していました。一人、残された家の中は、まるで火が消えた暖炉のようで、私はソファに座りながらしばらくの間、ボーッとしていました。とにかくもう、何もする気が起きませんでした。それからどれくらい経った頃でしょうか・・・部屋の中がもうとっくに暗くなっっていました。『もう・・・いやだ・・・いっそのこと・・・死んでしまいたい・・・』突然、そんな思いが胸に沸き起こると、先の見えない絶望感と孤独感が同時に襲ってきました。それはもう、自分ではどうにもコントロールできない感情でした。一人、家の中にいることに対する不安が心をかき乱し、自分を見失った私は夜の街に飛び出したのでした。その手には、佐藤からの手紙が握られていました。それから、どこをどう歩いたのか、確かな記憶はありませんが、気がつけば、見知らぬ街、そして見知らぬアパートの部屋の前に私はたたずんでいました。表札に「佐藤」と書かれた部屋の前に・・・。『来ちゃった・・・』その時の私は、結局、ここしか行く場所が思い当たらなかったのです。とにかく、誰か私の傍にいて欲しかったのです。幸い、部屋には明かりが点っていました。部屋の前に5分ほど立ちつくし、私は呼び鈴のボタンを押すのを躊躇していました。そうするうちに、部屋の中で人が動く気配がしました。私は、思い切ってボタンを押しました。部屋の中で呼び鈴が鳴るのが聞こえました。しばらくすると「ハイ・・・」という声がして、目の前のドアが開きました。私は俯いたまま、顔を上げることができませんでした。「・・・なんだ・・・どうした?」懐かしい声が耳に入りました。「・・・」「そんなとこにいつまで立っているんだ・・・さあ、入れ・・・」それは懐かしいだけではなく、妙に温かい声に聞こえました。以前は絶対にそんなこと感じたことがなかったのに・・・。
※元投稿はこちら >>
 妊娠9ヶ月 - お会いしたかった! 21:16 レス数:55 HOT:55 ↑
妊娠9ヶ月 - お会いしたかった! 21:16 レス数:55 HOT:55 ↑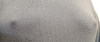 (無題) - ちょっと遅れて無事届きました♪配達員さんに対して横向いて印鑑押してる間じっと見ら 21:19 レス数:23 HOT:23 ↑↑
(無題) - ちょっと遅れて無事届きました♪配達員さんに対して横向いて印鑑押してる間じっと見ら 21:19 レス数:23 HOT:23 ↑↑ 埼㊙️サ㊙️他人妻晒し【時限】 - 晒しサイトは画像チャットのパーティーチャットです。https://gazo-ch 21:09 レス数:20 HOT:18 ↑↑
埼㊙️サ㊙️他人妻晒し【時限】 - 晒しサイトは画像チャットのパーティーチャットです。https://gazo-ch 21:09 レス数:20 HOT:18 ↑↑