タクシーが僕の住むマンションの手前にある信号で止まった。
僕は窓の外を眺めた。
そこには、先ほど親父と行為に及んでいたさおりさんが一人で歩いていた。
僕はタクシー運転手に「ここで降ろしてください。」といいお釣りももらわずにタクシーから降りた。
「こんにちは。」
実は、さおりさんのことをあまりよく知らない僕は当たり障りのない挨拶でしか声をかけることが出来なかった。
「あっ、お隣の、、、」
「石井です。」
「こんにちは。こんな時間にどうしたのですか?」
「僕は大学生なので時間は結構余裕があるんです。」
など他愛もない話をしながら、自分たちが住んでいるマンションに戻った。
僕は早速先ほど撮った動画を確認するためにスマホを開いた。
さおりさんと会話をしている時、彼女の体からはほんのりと石鹸の匂いがしていた。
その匂いを嗅いだだけで僕のジュニアは硬度を増し始めていた。
今はどんな動画なのだろうかという想像でジュニアがはちきれんばかりの大きさまで形を変えていた。
僕は固唾を飲んでスマホの画面に集中した。
画面に映る親父の身体の下に、色白の手足が伸びていた。
さおりさんは服を着ているようだった。
だが、そこに映し出されている服はコンビニで見かけた時の服とは異なっていた。
国民的アイドルグループが着そうな服装をしたさおりさんが全裸の親父に覆い被さられていた。
親父の汚いケツがさおりさんの身体に一定のリズムで上下していた。
僕はその映像を見ながら、ジュニアの先から流れる先走り液の量が半端ないことを知った。
それをジュニアに塗りたくってシゴキ立てていた時にチャイムが鳴った。
「ピンポーン」
もう少しでイキそうだった僕はチャイムの音を無視して、ジュニアを握った手を激しく上下に擦った。
「ピンポーン、、、滝川です。」
僕はその声にビックリし危うくジュニアを暴発させてしまう所だった。
滝川とはさおりさんの苗字であるからだ。
僕は急いでインターホンを押し返事をした。
「お昼ご飯を作り過ぎたので、よかったら食べ助けしてくれませんか?」
僕はその言葉に嬉しくなり急いで玄関の扉を開いた。
そこにはツインテールをした、とびっきりの笑顔のさおりさんが両手に鍋を持って立っていた。
「カレーを作ったんですけど、ちょっと量が多過ぎたので。」
そう言ってさおりさんは鍋に視線を向けながら鍋ごと僕に手渡そうとした。
先ほどまで鍋を胸の前で抱えていたさおりさんだったが、鍋を僕に渡したことで視線を向けていた所に遮るものがなくなった。
さおりさんはその遮るものがなくなった先にあるものに目を奪われていた。
そこにはズボンの中にしまうことを忘れた僕のジュニアが顔を出していた。
(ぁあ、なんていう失態を犯したのか、、、)
さおりさんの顔が一気に紅潮し、くるりと踵を返して自宅へと戻っていった。
予期せぬ出来事に僕はこれをうまく活用できないかと考えた。
だが、親父の存在が気になっていた。
(親父にさおりさんを諦めさせるには、、、)
僕はあることを思いついた。
急いで部屋の中に入り、僕は手に持った鍋をテーブルの上に置いた。
※元投稿はこちら >>
 ご主人様、皆様 - じゃあしよう。 05:37 レス数:114 HOT:109 ↑↑↑
ご主人様、皆様 - じゃあしよう。 05:37 レス数:114 HOT:109 ↑↑↑ わお - もっと見たいなー 黄色きてmoko0415 04:56 レス数:85 HOT:84
わお - もっと見たいなー 黄色きてmoko0415 04:56 レス数:85 HOT:84  (無題) - パイチンは嫌い? 01:17 レス数:70 HOT:69
(無題) - パイチンは嫌い? 01:17 レス数:70 HOT:69 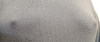 (無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:32
(無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:32