今日は本当に色々な女性から迫られる日だなぁと感心していると、席の横で速水聡美がむすっとした顔で、
「さっきの子と何かあったでしょう?」
と尋ねてきた。
「あっ、、、いやっ、、、今朝の電車でたまたま前に立っていた女性だったので、びっくりしたんです。」
「ふーん、、、そうなんだぁ、、、」
まだその目には疑いの眼差しがあったのだが、僕は無視して仕事に勤しんだ。
ようやく就業時間が終わり帰りの支度をしていると、部下の前田から声をかけられた。
「藤田課長、今日もご成約おめでとうございます。僕と課長のように契約を取れるように頑張ります。」
「あっ、、ありがとう。前田君も頑張ってるじゃないか。お互いに売り上げを伸ばそうな。」
「はいっ」
部下の後輩はそれだけ言うと足早に会社を立ち去った。
(ふぅ、、、占いのように今日は何でもすごくいくんだな。よし、これからは毎日占いを見よう)
今日は自分へのご褒美のために近所に出来たバーに行くことにした。
「いらっしゃいませ。お一人ですか?」
元気のいい挨拶が店内から聞こえてきた。
奥のカウンターに導かれ、そっとメニュー表を差し出された。
カウンターの中には数人のバーテンダーがいた。
その中の一人に目を奪われた。
それもそのはず、中高と憧れだった同級生の石川まどかがそこにいたからだ。
「もしかして藤田君?」
石川さんに覚えられていたことが嬉しく声も裏返りながら「は、はいっ」と返事をした。
「マスター。ごめん。私今から上がってもいいですか?」
急に石川さんは店長らしき人に声をかけてカウンターの中から出てきて僕の横に腰をかけた。
「まどかちゃん、、、はぁはぁーん、、、この人がまどかちゃんの昔の想い人だったんだね。」
店長らしき男は厭らしい笑みを浮かべながら石川さんに呟いた。
「マスター。しっしっ。」
石川さんは両手で店長らしき男を追い払って僕に話しかけてきた。
「随分見ない間にますますいい男になったね。」
そう言いながら、彼女の右手は僕の左手の上に重ねてきた。
「今日はこの後用事あるの?」
突然の申し出にしばし困惑したが、
「いや、特に用事はないよ。しかもまだ独身だし。」
「あっ、そうなんだ。藤田君ほどの男前だったら美人な奥さんと結婚されてるのかと思ってた。うふふっ」
「じゃあ石川さんは、、、」
と質問をしようとする僕の声を遮り、彼女の右手の人差し指を僕の唇にそっと当てた。
「今日はせっかく久しぶりに再会したんだし、遊びに行こっ」
僕は彼女の左手の薬指にキラリと光るシルバーリングを一瞬確認した。
次に彼女の指を見たときには、シルバーリングは外されていた。
どうやら、独身時代に戻りたい気分なのかなとその時は思った。
「藤田君、ビリヤードまだやってるの?」
「最近は忙しくて突いてないよ。」
「私にビリヤード教えてくれる?」
「ああ、僕でよかったら。」
「ちょっと待ってて。私服に着替えてくるから。」
会計を済ませて店の外で石川さんがくるのを待った。
「おまたせ。」
彼女は先ほどまでとは違って淡いブルーのカーディガンに薄い黄色のフレアミニを着ていた。
下ろされていたセミロングの髪の毛は、サイドアップされてちらりと見えるうなじが妖艶な女の色気を漂わせていた。
通りに出てタクシーを拾い、僕が先に後部座席に乗り込み、その後彼女が続いて乗り込んだ。
「運転手さん、、、まで」
と目的地を告げると、彼女は右手を僕のズボンの上から内腿を撫でてきた。
「こんなところで藤田君に会えるだなんて、、、」
その表情は明らかに恋する少女が見せる恥じらいのあるものだった。
だが、表情とは裏腹に彼女の手は卑しくも大人の手つきを見せたのだった。
彼女はタクシー内にも関わらず、僕のズボンのファスナーを開けると、その中に右手を差し込み、僕の愚息を握りしめた。
「はぁ、、、おっきい、、、あの頃見たのよりもさらにおっきいかも、、、」
「えっ、あの時って、、、?」
「覚えてないの?高校の文化祭でみんなで劇をしたの覚えてる?その時、更衣室がないって女子が騒いだから、男子が廊下で着替える事になったんだよね。藤田君の役がちょうど海パン一丁で踊るダンサーっていう役だったじゃない?その時女子は密かに藤田君のおち、んちんを見れるんじゃないかとドキドキしてたんだよ。で、案の定藤田君は周りをキョロキョロしながら廊下で着替えたんだよね。私たち女子はこっそり覗いてたんだよね。」
(あ、あの時か、、、確かに周りに誰もいないと思ってたから隠さずに着替えたよな、、、)
「その時からずっと藤田君のおち、んちんが気になってたの。で、今触ったら想像以上におっきくて、、、」
「お客さん、着きましたよ。」
「えっ、あっ、はいっ、、、お釣りはいりません。」
そう言ってタクシーから降りて、2階にある通い慣れたビリヤード場に入った。
店内にはビリヤード台が3台置かれていた。
珍しく客は誰もいず、暇を持て余してタバコを吹かせていたマスターだけが店内に佇んでいた。
「おっ藤田ちゃん。久しぶり。横の綺麗な女性は彼女?」
「同級生なんてす。偶然バッタリ出会ったもんで彼女がビリヤードをしたいと言ったので連れてきました。」
「そっかぁー、藤田ちゃんにも彼女が出来たのかと、、、それより俺今から用事があって3時間ほど店開けるけど頼んでいい?」
「大丈夫ですよ」
「助かるよ。藤田ちゃん。彼女も好きに遊んでって。」
そういうとマスターはそそくさと店外に出ていった。
「藤田君、ビリヤード教えてくれない?」
石川さんはビリヤード台に覆いかぶさるようにキューを持った。
「ほぉ、さすが運動神経抜群だった石川さん。さまになってるねぇ。」
「手取り足取り教えてくれない?」
僕は彼女の背後に立ち、彼女に覆い被さるようにしてキューの持ち方を指導した。
「やだぁ、藤田君の固いキューがお尻に当たってるよ。」
その一言で僕は我慢が出来なくなり、マイキューを石川さんのお尻の割れ目に強く押し付けた。
「ぁあん、、、あつい、、、それに固い、、、藤田君のキューで私のポケットにぶち込んで」
僕は石川さんのスカートをたくし上げた。
白いレースのパンティから美しいお尻の割れ目が薄っすらと透けていた。
僕は右手を彼女の前側に移動させ、彼女の秘部を弄った。
そこはすでにくちゅくちゅと音をあげるほど潤っていた。
指でパンティを横にずらし、とどまることを知らない源泉の元に指を差し込んだ。
「むぁあああ、、、ふん、、、ぁあん、、、お願いだから早く藤田君の固いキューを私のあそこにぶち込んで、、、」
僕は左手で彼女の左胸を優しく揉み始めた。ゆっくりと円を描くように揉み上げ、時折人差し指で乳首であろう場所を押した。
「はふん、、、やだ、、、早く挿れてよ、、、」
僕は右手の人差し指を彼女のあそこから引き抜き、パンティの淵に指をかけた。
お尻側からゆっくりとパンティをずらしていった。
そのまま膝までパンティを手でずらしていき、パンティに足をかけて一気に足首までずり下ろした。
彼女の右足を浮かせ、パンティを足から取り去った。
僕は両足を彼女の両足の中に突っ込み、股を広げさせた。
右手で彼女の背中を押していき、ビリヤードの台の上に顔をつけるように前屈みの姿勢をとらせた。
お尻を上に突き出すような格好になった彼女の秘部からは、透明の液体が床まで滴り落ちていた。
30とは思えないほど綺麗なピンクをしたあそこに釘付けだった。
「藤田君、、、お尻の穴に、、、あなたのぶっとくて固いキューをぶち込んで、、、」
「えっ、、、」
僕は石川さんの口から発せられた言葉に一瞬息が止まった。
「私の愛液をあなたのキューですくい上げて、私の厭らしいお尻の穴をあなたのキューで汚して。」
僕は言われるままにマイキューに彼女の愛液を塗りたくった。
テカテカに光ったマイキューはこの上なく大きく黒く光っていた。
両手で彼女のお尻を掴み、少し手に力を入れて両尻の肉を円を描くように揉み上げた。
両手が外側を揉み上げるたびに、彼女のお尻の穴は広がり中身が見えるほど強く揉み上げた。
お尻の括約筋も緩み、挿入が可能な状態へと近づいた。
マイキューをお尻の穴の入り口にそっと当てた。
「ぁあん、、、こんなに太いの入るかしら、、、」
と言いながら、彼女はお尻を突き出してきた。
「ヌルン、、、」
一瞬の出来事であったが、すんなりとマイキューは彼女のお尻の穴へと吸い込まれた。
「ぁあん、、、お尻の穴、、、壊れちゃう、、、もっときて、、、お願い、、、」
僕は両手で彼女の腰を掴み、一気にマイキューを彼女の奥までぶち込んだ。
「ぁあああああ、、、、こんなの初めて、、、ぉう、、、漏れちゃう、、、」
僕はゆっくりと腰を前後に振ってみた。
「ぁあん、、、お尻の中が熱くて狂いそう、、、もっと速く突いて、、、」
彼女の腰を持った両手に力を入れて、手前に引きつけるかのようにしながら激しく腰を振り、マイキューを彼女の奥までぶち込んだ。
「こんなの、、、ぁあん、、、死ぬ、、、いっちゃう、、、」
彼女のお尻の穴からはマイキューに塗りたくっていた彼女の愛液と僕のカウパーが混じり合いつ、何ともいやらしくなった液体がおち、んちんを抜くたびに溢れてきた。
「もぅ、、、ダメ、、、いっちゃうけど、、いついい?、、、藤田君も私のお尻の中で出して、、、」
僕は一層激しく腰を打ち付け、がむしゃらに腰を振った。
「あっあっあっ、、、もうだめ、、、ぃくぅ、、、」
その声と同時にマイキューから熱い粘性のある液体がお尻の穴奥に大量に発射された。
「ドクン、、、ドクン、、、ドクン、、、」
あそこと違う締め付け具合に、マイキューは一向に小さくなる気配はなかった。
ぐったりしている彼女の衣服を剥ぎ取り、彼女を持ち上げてビリヤード台の上に仰向けで寝転ばせた。
両ポケットの穴にそれぞれの脚を突っ込ませ、脚を閉じられないようガムテープで固定した。
さらに両手も同じように反対側の両ポケットの穴に手を入れガムテープで固定し、ビリヤード台の上で大の字の姿勢を取らせた。
マスターがSM愛好家であることは昔からよく話を聞いていた。
僕は店内に飾られているハウスキューの横に備え付けられているロッカーに目をやった。
ロッカーに近づき扉を開けるとそこには無数のおもちゃが入っていた。
ローター、電マ、アナルプラグ、革手錠、ムチ、、、など
僕は電マ、アナルプラグ、ムチ、それとローター3つを手に取り、サージカルテープをポケットの中に入れた。
ビリヤード台の上で大の字になっている彼女の元に行き、ローターを両乳首に当ててサージカルテープで固定した。
最後の1個は彼女のお豆さんに固定した。
右手を彼女の腰の下に手を入れ少し体を浮かせ、アナルプラグを先程拡張されたお尻の穴に差し込んだ。
それぞれのスイッチをONにすると彼女の感覚は一気に目を覚まし快感に身を悶えさせた。
「いやぁ、、、ぁああ、、ダメ、、おかしくなる、、、」
言葉にならないほどの喘ぎ声が店内にこだまする。
僕は構わず彼女の体に電マを添わせた。
「はぁああん、、、感覚がおかしくなる、、、い〝ーーっ、、、あ〝あ〝ーーっ、、、出ちゃう、、、ぁああ、、、吹いちゃうよ、、、」
僕は左手に持ったムチで彼女の身体に向かって上げた手を振り下ろした。
「パシン、、、ペチンッ、、、」
「はぅ、、、あ〝っ、、、あぅん、、、」
痛艶めかしい声が店内を駆けずり回った。
彼女の口からはよだれを垂れ流され、あそこからは大量の潮を吹かれ、ビリヤード台の上に敷かれたラシャには大きなシミが浮かんでいた。
お尻の穴をスッポリと覆っているアナルプラグを引き抜き、そのかわり電マを押し当てた。
「ぃや、、、それは、、、ぁあん、、ぐっ、、、」
僕は彼女の声に一切耳を傾けず、電マに力を入れグッとお尻の穴に押し込んでいった。
大きな電マの頭がスッポリと彼女のお尻の穴に入った。
振動の強さを強にして、電マを抜き差ししながらグリグリと回し始めた。
「むぐっ、、、ぁあ、、ぐっ、、むむっ、、、」
苦悶に満ちた彼女の表情の中に恍惚な笑みを感じ取れた。
僕は手を休めることなく、ひたすら電マを彼女のお尻の中で暴れさせた。
「ヒィ、、、フゥ、、、ぁあ、、、おかしくなる、、、あ〝あ〝、、、い〝ぐぅ、、、ぁああああ、、、」
声にならない声で彼女は体をバタつかせながらのたうち回っていた。
僕は容赦なく彼女の胸にムチを振るった。
「あ〝っ、、い〝っ、、ぐうっ、、はぁん、、、」
彼女の穴という穴すべてから、液体が溢れ始めていた。
汗、よだれ、体液、、、そして、、、
お尻の穴からは茶色いドロっとした粘性のものが溢れて始めていた。
彼女の動きが一層速く大きくなった。
ビリヤード台が動くほどの力で彼女は体をよじっていた。
最後の仕上げとして僕は電マをお尻の穴の奥まで突っ込んだ。
「やだぁ、、、ヒッ、、、グゥ、、、お腹が膨らむ、、、やっ、、、ダメ、、いくぅ、、、」
彼女の声が一段と大きくなり、店内は阿鼻叫喚のごとく様々な声で響き渡った。
「ぁああああ、、、」
彼女のあそこから、大きな放物線を描きながら透明の液体が空高く舞い上がった。
それは公園の噴水かのように綺麗な放物線を描いていた。
「はぁはぁはぁ、、、うっ、、、はぁん、、はふん、、、」
彼女は大きく呼吸をし、体の沈静化に努めた。
彼女の目は何か妖しげな雰囲気を感じさせるほど、快楽に狂わされていた。
僕は固定した両手両足からガムテープを取り去り、彼女の腰に手を回し体を起こさせた。
床に落ちていた彼女のブラとパンティを彼女のカバンに詰め込み、ノーパンノーブラのまま服を着させた。
店内を掃除し、マスターがいつも鍵を隠しているカウンターの下の箱からキーを取り出し店を閉めた。
鍵はフロアマットの下にそっと忍ばせ、彼女は僕の腕に体を寄せるような格好で街に出た。
外は強い風が時折二人に吹き付けた。
ヒラヒラのフレアミニを風は容赦なく吹き付けた。
その度に街行く人が振り返って彼女の下半身に目をやった。
そこには闇を吸い込むようなほどパックリと開かれたお尻の穴が、人々の欲望を惹きつけていた。
※元投稿はこちら >>
 わお - 俺の元嫁21歳まで処女で同じ綺麗なマンコでした。 06:52 レス数:87 HOT:86
わお - 俺の元嫁21歳まで処女で同じ綺麗なマンコでした。 06:52 レス数:87 HOT:86  (無題) - パイチンは嫌い? 01:17 レス数:70 HOT:69
(無題) - パイチンは嫌い? 01:17 レス数:70 HOT:69  おはよう御座います - 身体疲れてる時の方がチンポビンビンの時ありますので分かります(笑)旦那さんとはど 07:06 レス数:30 HOT:29 ↑↑↑
おはよう御座います - 身体疲れてる時の方がチンポビンビンの時ありますので分かります(笑)旦那さんとはど 07:06 レス数:30 HOT:29 ↑↑↑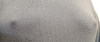 (無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:26
(無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:26