就業時間から5分経った時にようやく会社に辿り着いた。
「藤田ーーーっ、おまえまた遅刻かぁ」
上司の怒鳴り声が聞こえてきたが、聞こえないふりしてデスクに座った。
「あっ、そこ私のデスクです」
そう声をかけてきたのは入社2年目の速水聡美だった。
ショートカットがよく似合う聡美は昨年結婚したばかりの新婚さんであった。
黒色のストッキングを紺色のスカートから覗かせ、ブラウスの一番上のボタンは外すといった営業にはあるまじきスタイルの女性だった。
「藤田さんの席は隣」
「んっ?なんで?課長の席に?」
「おめでとうございます。藤田さんの売り上げが3ヶ月連続1位だったんですって。」
「な、な、な、なんとっ」
入社してから8年、ようやく僕に運が向いてきたようであった。
「一体全体今日はどういうことだ?」
僕は普段なら絶対に見ない占いをネットで検索してみた。
1月生まれのあなたは、今までの努力が実を結びまたとない幸運な日々を過ごされることでしょう。
この日ばかりは占いを信じることにした。
「藤田課長よろしくね」
そういって頭を深々と下げた聡美を見ると、大きく開かれた胸元から見事な乳房が顔を覗かせていた。
ものの2、3秒であったが、あまりの見事さに見惚れてしまっていた。
「もぉ課長のえっちぃ」
頭をあげた聡美は笑いながら、自分のデスクに座った。
カバンをロッカーに置き、課長席に腰をかけた僕は隣で黙々と仕事をしている聡美をちらっと横目で見た。
スラリと伸びた脚が若奥様らしい色気を漂わせていた。
不意に聡美が脚を組んだ瞬間、スカートの奥が一瞬丸見えとなった。黒色のストッキングに包まれたパンティは薄っすらと白色が浮かび上がっていた。
ハッとして顔を上げると、聡美がニヤニヤとこちらを見ていた。
「見たいのですか?」
僕は小さく頷くと、聡美は組んでいた脚を元に戻して膝と膝を少しずつ開いていって僕の方に脚を向けた。
太陽の光がスカートの奥を照らし、黒色のストッキングの奥に眠る白色のパンティがはっきりと写し出されていた。
「課長、2番にお電話です。」
部下の声にハッとして、急いで電話に出た。
(今日は何故こんなにもついているんだ?)
そう思いながら午前中を過ごしていた。
中古車屋で働く僕は平日にはほとんど仕事らしい仕事はなかった。
たまに来るお客様の相手をしたり、修理や車検に訪れるお客様の対応をするぐらいだった。
時計の針が12時を指すと一斉にみんなが立ち上がって昼休憩となった。
「藤田課長、一緒にランチしませんか?」
聡美が初めてランチに誘ってきた。
「いいよ、何食べたい?この前美味しいパスタの店を見つけたから、そこに行くかい?」
「やったー」
そんなやりとりをし終えた後、二人でパスタ屋へと向かった。
その店は各テーブルが簡単なカーテンで仕切られている個室形式のパスタ屋さんであった。
洋食にも関わらず、畳の座敷といった風変わりなスタイルと値段の割に美味しいと評判のお店であった。
「いっただっきまぁす」
屈託のない笑顔で口いっぱいにパスタを頬張る聡美を見ていると、家庭も幸せなのかなぁと思わずにいられなかった。
「速水さんはなんで僕をランチに誘ったの?」
その疑問をストレートに聡美にぶつけてみた。
「実は、、、」
どうやら、夫婦生活がほとんど無いようであった。
前から気になっていた僕が上司になったことで嬉しくてつい僕を誘ったようであった。
聡美はパスタを食べ終わると脚をM字にして両手を後ろについてリラックスした体勢をとった。
「んっ?」
よく見ると先程まで履いていた黒色のストッキングは脱いでおり、生足が顔を出していた。
さらに、スカートの奥を見ると白色のパンティが眩しく輝いているようにこちらを向いていた。
「あぁ美味しかったぁ」
そう言いながら聡美はどんどん脚を開いていった。
僕は自然と彼女のパンティに目を奪われていた。
テーブルの下で足を伸ばしていた僕の足に、聡美はその股間を近づけてきた。
足の裏に彼女の股間の生暖かさが伝わってきた。
いたずら心が芽生えてきて、足の親指を軽く曲げて彼女の股間を擦るように動かした。
「んんっ」
聡美の口から微かに声が漏れた。
今度はゆっくりと足の親指を彼女のパンティの上から割れ目を擦ってみた。
目をしっかりと閉じ、足の指先から伝わる動きを全て感じ取るかのように集中しているようだった。
彼女は腰を浮かせ、履いていたパンティを目の前で脱ぎ去った。
そこにはキラキラと光る液体が割れ目の周りに溢れていた。
ピンク色をしたビラビラに申し訳ない程度に生えた陰毛、そして恥ずかしそうに顔を覗かせているお豆さん。
さすが22歳の若い子のあそこは綺麗だった。
僕は足の親指に力をギュッと込めて、彼女の割れ目の入り口に当てた。
「ぁん」
艶かしい声とともに足の親指がニュルっと中に入っていくのがわかった。
僕は足の親指を何度も曲げ伸ばしして彼女の中を掻き回してみた。
聡美は自ら腰を前後に動かして、足の親指を奥へ奥へと入れようとしていた。
僕はもう片方の足の親指で彼女のお豆さんに触れてみた。
「ぁあああ」
一際大きな声を上げて背中を仰け反らせた。
丸見えになった彼女の秘部には、2本の太い足の親指が休む間もなく動かされていた。
「か、課長、、、もっと、、、お願いします。」
そういっておもむろに立ち上がり僕の横に座った。
彼女の細い指がズボンの上から僕の股間を抑えた。
「あつい、、、」
聡美は僕のズボンのファスナーをゆっくりと開けていき、僕の股間に顔を埋めていった。
勢いよくズボンから顔を出したマイサンを口で咥えると、ジュルジュル音を立てながら頭を上下に振って、僕の愚息を刺激した。
聡美のホッペが程よくすぼんでいやらしい顔を作っていた。
聡美が上下に頭を動かすたびに愚息がどんどん硬度を増していった。
「ぁあ、、、この硬くて太いのが欲しかったの、、、」
そういって聡美は口で愚息を含みながら、タマタマを揉みしごきながらフェラを続けていた。
「ここのカーテン薄いから周りから見えるよ?」
僕は彼女の行動を制止しようと言葉をかけたが、彼女は無視して一向に動きを止めようとしなかった。
「ぷはぁ、、、ほんと課長のおち、んちん硬くてふとーい、ねっいいでしょ?」
その言葉を発した聡美の顔はすでに発情したメスの顔になっていた。
返事を戸惑っていた僕に聡美は急にまたがり、僕の愚息を右手でつかんで自分の秘部に押し当てた。
「ズブブブブっ」
「あ、、、あつい、、、それにおっきい、、、ぁあん、、、これだけでいっちゃう」
聡美はゆっくりと腰を落として、秘部の中に愚息を沈めていった。
「課長の、、、奥まで当たる、、、そこ刺激されると弱いの、、、」
そう言いながら聡美は腰を前後に振り始めた。
対面座位の姿勢をとりながら、彼女は両手を後ろについて仰け反った。
「ぁあん、、、気持ちいいところにあたるぅ、、、」
聡美の腰の動きがどんどん速くなり、
「あっ、、、ダメ、、、いっちゃう、、、」
彼女は苦悶の表情を浮かべながら、パックリと咥え込んだ愚息を美味しそうに味わっていた。
僕は右手を彼女の腰に手を回し、左手の親指を彼女のお豆さんに手を添えた。
「ひっ、、、それ、、、ダメ、、、いっちゃう、、、いってもいい?」
僕は左手の親指の動きを速め、少し腰を上下に動かして聡美の奥を突こうとした。
「だ、、、だめ、、、いっちゃう、、、ぁああああ、、、」
その声は遠慮気味に小さな声だったが、僕の耳にはしっかりと聞こえていた。
腰に回した右手に力を入れて彼女の身体を僕の体のほうに引き寄せると、
「もぅダメっ、、、いくぅ、、、いっちゃう、、、」
そういって下半身を痙攣させながら、僕の愚息を強く締め付けてきた。
どうやら彼女はいったようだった。
彼女の中に収まっている僕の愚息はまだまだ硬度も大きさも十分すぎるほどだった。
ぐったりと肩で息をしている彼女を尻目に僕は小刻みに腰を上下に動かした。
「あっ、、、あっ、、、あっ、、、そんなことされたら私、、、」
聞こえないふりをしながら、時に強く彼女の中に愚息を打ち込んだ。
「ぁあああ、、、」
店内に喘ぎ声が広がった。
僕は慌てて彼女の口を手で覆った。
周りに声が漏れないように手でしっかりと口をガードすると、呼吸が出来ないのか、急に彼女のあそこが締まり始め愚息を何度もギュッギュッと締め上げてきた。
彼女は何度も首を横に振って動くのを止めて欲しいとは懇願したが、歯止めが効かなくなった僕の愚息は聡美の奥に濃い白色の液体を放出する準備に入った。
亀頭がどんどん膨れ上がり、愚息がMAXになったところで彼女の腰を掴み一気に奥までぶち込んだ。
「あああああああああ、、、、」
僕の手で口を押さえられているにも関わらず、その声が手の隙間から漏れるほど大きな声を上げて身体全体をビクつかせた。
「うっ、、、出る、、、はぁぁぁ、、、」
聡美のあそこの奥に大量の液体を放出したと同時に、彼女は大量の潮を吹いて白目をひん剥いて仰け反った。
ドクン、、、ドクン、、、
彼女の中に大量の液体が送り込まれた。
「はぁはぁはぁ、、、か、課長、、、すごすぎます、、、」
目に涙を浮かべながら、こちらを艶めかしく眺める聡美の顔が近づいてきた。
そっと唇と唇が重なり合い、お互いの唇を軽く噛んだり吸ったりしていた。
「藤田課長、、、毎日してもらえませんか?」
彼女の目には本能のままに生きるメスの姿が現れていた。
彼女にもう一度キスをして会社に戻った。
※元投稿はこちら >>
 わお - 俺の元嫁21歳まで処女で同じ綺麗なマンコでした。 06:52 レス数:87 HOT:86
わお - 俺の元嫁21歳まで処女で同じ綺麗なマンコでした。 06:52 レス数:87 HOT:86  (無題) - パイチンは嫌い? 01:17 レス数:70 HOT:69
(無題) - パイチンは嫌い? 01:17 レス数:70 HOT:69  おはよう御座います - 身体疲れてる時の方がチンポビンビンの時ありますので分かります(笑)旦那さんとはど 07:06 レス数:30 HOT:29 ↑↑↑
おはよう御座います - 身体疲れてる時の方がチンポビンビンの時ありますので分かります(笑)旦那さんとはど 07:06 レス数:30 HOT:29 ↑↑↑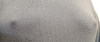 (無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:26
(無題) - あおいさん!大変良いものをありがとうございました。もし良かったら、また見せにいら 22:01 レス数:32 HOT:26