ぼんやりと開いた視界の中に見慣れた家具を認めて、そこが仏間であることに気が付いた。
畳の上にはやわらかい布団が敷かれており、どうやら夕べ夫は、八重を寝室に運ぶのを諦めて、この仏間の中に来客用の布団を用意してくれたらしい。
切り裂かれた衣服はすっかり着替えさせられて、いつもの着慣れたパジャマに袖を通していた。
慣れ親しんだ匂いに安堵感を覚えもしたが、下着も替えられていることに気付いて少しだけ複雑な気持ちになった。
わずかな性毛が残っているだけの赤子のようにされた性器を、夫はどんな気持ちで眺めていたのだろう。
タオルで丁寧に拭ってくれたのか、京介に汚され抜いた股間やお尻の狭間にも、特に気にするような不快感はなく、顔に掛かっていた血も綺麗に拭き取られていた。
夕べ切った額には手厚く包帯までも巻かれており、胸にも大きなガーゼを何枚も当てた丁寧な処置がなされている。
相変わらず優しい夫に申し訳ない気持ちにもなったが、同時に彼がどんな態度に出てくるかと考えると気が重かった。
そろそろと周りを見回してみたが、その夫の姿はなく、家の中はしんと静まりかえっている。
どのくらい寝ていたのだろう、と壁の時計に目を向ければ、針は10時を少し過ぎたところだった。
この時間ならば仕事に出ているのかも知れないとも考えたが、こんな状態の八重を残して仕事に出掛けてしまうような夫ではなかった。
どこに行ったのだろうと不安な気持ちのまま、八重はしばらく布団から出ることができなかった。
ぼんやりと天井を見つめながら、そう言えば、京介はどうしたのだろう?と愛しい息子のことを思い出した。
車を取りに行くと言ったまま、それから彼の姿を見ていない。
あれから、京ちゃんはどうしたのかしら?・・・・。
頭の中に霞が掛かったように記憶がぼやけてよく思い出せない。
確か、河原を駆けていくのを見送って、それから・・・
必死に思い出そうとしているうちに、ぼやけていた記憶がはっきりとしてきて、不意にその光景は脳裏に蘇った。
途端に、ぞわぞわと冷たいもの背中を這い上がってきて、歯がカチカチとなる。
どうしようもないまでに身体が震え、ものすごい吐き気に八重は口元を押さえた。
はっきりと思い出していた。
血塗れの顔を苦悶に歪め、すべてを呪うかのように目を見開いて女は天を見上げていた。
生にしがみつこうとしたのか、はたまた、犯人を逃すまいとしたのか、枯れ枝のように曲がった指が必死に何かを掴もうとするかのように宙を掻いていた。
足はあらぬ方向に曲がり、大きく開けたロからは、だらりと舌まで出していた女が死んでいるのは明らかだった。
その女の剥いた目玉が記憶の中で、ぎろり、と八重を睨んだ。
「ひ・・・きゃあああああああっっっ!!!」
八重は声の限り叫んでいた。
沈鬱な面持ちで車から降り、玄関に向かって歩いていたところに、突然、家の中から八重の引き裂くような悲鳴が聞こえた。
「ど、どうした!?八重っ!?」
慌てて玄関を駆け上がり、仏間の障子を開いて中に入っていくと、そこに寝ていたはずの八重の姿がない。
布団がもぬけの殻になっていた。
「八重!八重!」
辺りを見回すと、点々と吐濡物のようなものが床に落ちていて、それが廊下へとつづいている。
不安な気持ちで跡を辿っていくと、それはトイレまでつづいていた。
取っ手を握って開けようとしたが、中から鍵が掛けられていて開かない。
中からすすり泣く声が聞こえた。
「八重!開けろ!ここを開けるんだ!」
「いや!来ないで!来ないでぇ!いやぁー!」
どうやら錯乱しているらしいとわかって、京太郎は舌打ちした。
無理もなかった。
河川敷の強姦魔に酷い目に遭わされたのだ。
どれほどのショックがあっただろう。
しかし、その犯人がまさかあいつだなんて・・・。
「八重!ここを開けろ!俺だ!京太郎だ!わかるか!?お前の夫の京太郎だ!」
中から鍵と一緒に取っ手を押さえているらしく、まったくドアは動かない。
「いやあっ!!来ないでっ!来ないでぇっ!!!」
苦々しい思いを振り切り、妻を取り戻すことに努めてみたが、八重は激しく泣きながら叫ぶばかりで、まったく応えようとしなかった。
何度出てこいと言ったところで話しを聞かず、大きな声で叫ぶばかりで埓があかない。
「いい加減にしろ八重!京介が警察に捕まったんだぞ!こんな事をしてる場合じゃないんだ!」
いい加減、業を煮やした京太郎は、伝えるべきか伏せるべきか悩んでいた事実をドア越しに言い放った。
連絡を受けたのは、今朝の7時を過ぎた頃だった。
朝早くから済まねえな、で始まった気の合う同僚からの電話は、実はお前さんの息子が、とさも言いづらそうな話に変わり、申し訳ねえが、こっちへ顔を出してくれ、と最後は半ば強制的な出頭要請で終わった。
八重を残していくことに不安はあったが、内容が内容なだけに無視するわけにも行かず、八重が深い眠りにあるのを確かめてから家を出た。
京太郎が署に辿り着いた頃は、まだ京介の身分は関係者であったが、日の出とともに始められた鑑識の現場保存の際に押収された凶器と思われる血塗れの石から京介の指紋が検出されると、すぐさま被疑者へと切り替えられた。
京太郎は関係者となり、前夜からの行動とここ最近の京介の行動について簡単な調書を取られた。
妻の具合が悪いのを理由に、一時帰宅したのがついさっきである。
強姦のショックを受けている八重に、さらに追い打ちを掛けるような事実を伝えることに躊躇いはあったが、状況が状況なだけにやむを得なかった。
しかし、八重に聞かせるタイミングを計りかねていただけに、ちょうどよい機会だったのかも知れない。
トイレの中から聞こえていた泣き声が止んだ。
しばらく待っていると、カチャリと鍵を外す音がして、向こうからドアが開いた。
「どうして?・・・どうして京ちゃんが警察に捕まったの?・・・」
八重には、やはり自分のことなどよりも京介のほうが大事らしい。
顔が青ざめていた。
化粧などしなくても十分に美しい女だが、放心したように顔を青ざめさせている今はそれが見る影もない。
目は赤く腫れていて、顔は涙と鼻水でぐちゃぐちゃになっていた。
「お前も知っているな?この近所で起こっていた例の強姦事件だ。あの犯人として、夕べ京介が捕まった。現場に戻ってきたところを逮捕されたんだ・・・。」
「現・・場?」
咄嵯に、血塗れの女が転がっていた葦の薮を思い出した。
あの女の目が脳裏にこびりついて離れず、思い出しただけで喉の奥から叫び声が飛び出しそうになる。
必死に堪えた。
「嘘よ・・・京ちゃんは、そんなことはしないわ・・・そ、そんなの嘘よ・・・・。」
あの子に限って、そんな大それたことなどできるはずがない。
しかし・・・。
「俺も嘘だと思いたい。だが、証拠があるんだ。」
「証拠?」
「ああ・・・。」
「どんな、証拠なの?・・・」
そんなもの、あるはずがない。
夕べ京介は八重とずっと一緒だった。
八重の胸を切り裂き、好き放題弄んでいた。
他の女にかまっている時間などあるはずがなかった。
証拠などないことは、八重が一番よく知っている。
「石だ・・・。」
京太郎が重々しげにロを開いた
「石?・・・石って?」
「凶器に使われた石だ。その石から、京介の指紋が出た・・・。」
言い終えて、京太郎は辛そうに目を伏せた。
石ですって?・・・。
石・・・・・・・・。
いし・ ・ ・ ・・・。
あっ!
八重は思い出した。
京介が拾ったあの血塗れの石だ。
八重の額を割ったものだと京介は思い込んでいた。
あの石は、八重に見せてくれたあと確か・・・・放り投げたのだ!
あの子は無造作に放り投げてしまった。
だから指紋が・・・。
「あれは、ちが!・・・」
そこまで言いかけて、咄嵯にロをつぐんだ。
なんて言えばいい?
どうやって説明する?
京介と一緒だったのがわかってしまう。
何のためにあそこに二人でいたのか、夫に知られてしまう。
「何が違うんだ?」
怪訝な目を向けていた。
「い、いえ‥あ、あの子のはずがないという意味で、その違う、と・・」
「俺だってそう思いたいさ」
夫は疑わなかったようだった。
「だったら、早くあの子を!」
夫は、県警に勤める警察官だ。
この人なら、京介の無実を証明することなど容易い。
鑑識課員だった。
三十数年の警察官人生の実に三分の二以上の年月を、夫は鑑識課員として勤務してきた。
最後は課長というポストまで辿り着き、後進に道を譲るという形で今年の夏に定年する。
定年後は、とある大学の客員講師に雇われることがすでに決まっていた。
彼の鑑識課員としてのこれまでの実績を高く評価してくれた大学があり、是非にと破格の待遇を提示して彼を呼んでくれたのだ。
それほど京太郎の鑑識課員としての腕は確かだった。
京太郎には、八重の言いたいことがわかったらしかった。
彼は暗い目を八重に向けた。
「捜査からは、はずされたよ・・・お前にだって、わかるだろ?」
加害者が親族であった場合、情実を避けるために近親者は捜査からはずされる。
警察官の常識だ。
ましてや京太郎は鑑識課員だった。
証拠の特定をする者が容疑者の近親者では、ねつ造や隠蔽などをやられかねない。
捜査に参加できるはずがなかった。
だから、今朝も出頭要請があるまで、京太郎には連絡が来なかった。
「じゃあ、あの子は?・・・あの子はどうなるの?・・・」
八重が、震える声で聞いた。
「心配するな。このままみすみす手をこまねいたりはせんよ。あいつにそんなことができないことは一番俺がよく知っている。」
そうだ、京介のことならば誰より俺が一番よく知っている。
八重よりも、あいつのことなら俺のほうがわかる。
「取り敢えず手は打ってある。だがその前に、お前にも聞かなければならないことがある。」
京太郎は、震える八重の両肩に手を掛けると、真摯な眼差しで見つめた。
「夕べ、お前に何があった?それを全部俺に話せ。それがわからないことには何もはじまらん。辛いだろうが全部俺に話してくれ。それが、京介を助ける近道になるんだ。」
ぐっ、と痛いくらい肩を掴まれて、八重は京太郎を見上げた。
頷くしかなかった。
しかし、頷いたところで、本当のことなど言えるはずがない。
どんな答えを返すべきか、八重は夫の強い眼差しに晒されながら、これからつくべき嘘を必死になって考えていた。
※元投稿はこちら >>
 今日もチクニーしてます - オホ声とオモチャの排泄音、排泄完了してゴトっと下に落ちる音ってエロ声聞かせたいっ 00:51 レス数:55 HOT:53
今日もチクニーしてます - オホ声とオモチャの排泄音、排泄完了してゴトっと下に落ちる音ってエロ声聞かせたいっ 00:51 レス数:55 HOT:53  生理前はムラムラしちゃう……。 - 生理中でもクンニ出張しますよヽ(´∇`)ノ 08:02 レス数:39 HOT:37 ↑
生理前はムラムラしちゃう……。 - 生理中でもクンニ出張しますよヽ(´∇`)ノ 08:02 レス数:39 HOT:37 ↑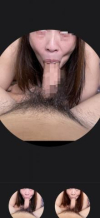 おばさん便女 - 素晴らしい便女ですね。公園便所で使いたい 07:10 レス数:18 HOT:18
おばさん便女 - 素晴らしい便女ですね。公園便所で使いたい 07:10 レス数:18 HOT:18  タコ足おもちゃで - 凄いねイッきながら何度もかけてくれ 07:42 レス数:15 HOT:15
タコ足おもちゃで - 凄いねイッきながら何度もかけてくれ 07:42 レス数:15 HOT:15  オカズセフ - ムチムチですねヘアを見せて 07:51 レス数:14 HOT:13 ↑
オカズセフ - ムチムチですねヘアを見せて 07:51 レス数:14 HOT:13 ↑