2時間前・・・・
開いた足の間に、腰が入っている。
緩慢なリズムで動いていた。
深く入ってくると自然とお尻が浮く。
ぐいぐいと奥まで押し込んできて、それは、ちょうど一番深いところで止まる。
不思議と計ったようにそこから先は入ってこない。
奇妙な気持ちよさがあった。
膣は十分に濡れていた。
おかしなもので、八重の意志など無視して勝手に濡れてしまう。
確かに気持ちよさはある。
濡れてもいる。
でも、快感と呼べるほどの陶酔感はない。
恐怖心のほうが、はるかに強かった。
分厚い手のひらが顔半分を塞いでいた。
影は横にした手のひらに体重を掛けて八重の口を覆っている。
叫ばないようにしているというよりは、逃げられないようにしている。
たぶん、それが正しい。
チリチリと灼けるような胸の痛みがずっとつづいていた。
八重は奥歯を噛みしめた。
最初は首からお腹に向かっていた。
今は、右から左へ流れている。
影は一切しゃべらず、熱心な彫刻家のように八重の白い肌に記念の烙印を刻み込んでいた。
腰を動かしながらの作業に均一さはない。
わずかにナイフが深く入り、八重は痛みに身を捩らせた。
「動くな・・・。」
叱咤するくぐもった声が頭上から落ちる。
八重に命令するときだけ、影は口を開く。
他は何も話さない。
三流ドラマの悪役みたいな卑猥なことも言わない。
八重の胸を刻みながら、ひたすら犯すだけだ。
影は、一生懸命八重を犯していた。
気持ちいいの・・・?
ぼんやりと頭上の影を見上げていた。
顔は闇に溶けたままで、まったく表情はわからない。
目鼻のない黒い能面のようだった。
表情がわからなくて当然だ。
顔を隠すために頭からストッキングを被っている。
これでは、わかるはずがない。
口が大きく開けないのだから、声がくぐもるのも当たり前だった。
胸を横切っていく灼けつく痛みは、しばらくして終わった。
影は満足したように八重を見おろしながら、ナイフを畳むと、今度は犯すことに専念したようだった。
膝の裏を掴んで押し拡げ、ぐっと自分の腰に体重を掛けてきた。
動きに力強さが加わり、それまでの単調な往復運動から、円を描くような腰使いに変わる。
しばらく押し開いた部分を楽しむよう眺めていたが、それにも飽きると八重の頭の横に両手を付いてきた。
身を乗り出して八重を見おろす影は、あたかも声を出せと言っているようだった。
「ああ・・・う・・うん・・あはぁ・・・」
望み通りに声を出した。
大きなものが膣を塞いでいる。
腰の使い方に覚えがある。
影が本腰を入れていくと、胸の痛みよりも下半身の疼きのほうが強くなった。
影は八重の身体を知り尽くしている。
八重にも、もうわかっていた。
頭の痛みはつづいているし、耳鳴りはずっとやまずに、打たれた頬は熱を孕んで厚ぼったく腫れたままだ。
おまけに胸まで斬られて傷ものにもされた。
「あっ!・・いいっ・・・気持ちいい・・・」
こんなに酷いことをされても、まだ堪えようとする自分がいる。
「気持ちいいよ・・・・気持ちいいよ・・・」
喘ぎながら、眼前にある影の顔に腕を伸ばした。
影が被っているのは、おそらく八重のストッキングだ。
駅近くの駐車場に車を停めたとき、脱がされてそのままになっていた。
車の中に置き忘れたものと思い込んでいたが、京介がこっそりと隠し持っていたらしい。
八重のストッキングを頭から被り、別人になりすまして八重を襲っている。
それは八重を震え上がらせるための彼得意の演出だったのかもしれない。
でも・・・そうではないかもしれない。
殴打しているときの京介に憐憫の情はなかった。
母親の肌に恐ろしいナイフを突き立てもした。
震える八重の胸をあっさりと切り裂いた。
尋常な感覚の持ち主ではない。
おそらく京介には二つの顔がある。
ひとつは、どんなにひどく虐めても、必ず最後は八重を可愛がって大事してくれる京介の顔。
そして、もう一人の彼は、きっと八重が想像もできない冷酷な顔を持っている。
京介には、他人には理解しがたい激しい衝動が潜んでいるのかもしれない。
ナイフで斬りつけられながら、浅く斬ろうとしていることに気付いて、八重も気が付いた。
殺すつもりなら無造作に斬りつける。
柄に届くほどナイフを肌に突き立てれば、それで終わる。
刺そうとしたのだ・・・。
京介は無造作に斬りつけるつもりだった。
両手に握ったナイフを高く振り上げ、真下の八重に振り下ろそうとしていた。
状態を伸び上がらせながら、振り上げた腕の間から顔を覗かせた京介は笑っていた。
表情など見えなくとも断言できる。
きっと京介は何かに取り憑かれたように唇の端を吊り上げながら笑っていたのだ。
たまたま河川の水面に何かが跳ねて大きな水音がした。
それで正気に戻った京介は、踏みとどまった。
あれがなかったら、今頃八重はこの世にいなかったのかもしれない。
確かに京介は、八重を殺そうとしていた。
八重でなくても、いいのかもしれなかった。
八重は、伸ばして腕で影の顔に手を触れた。
愛しむように頬を撫でながら、弾力のある薄生地に爪を立てた。
「京ちゃん・・・京ちゃん・・・」
影の腰は、欲しがるように深く抉っていた。
腰から下が溶けそうになっている。
この子にあげたときに、地獄に堕ちてもいいと思った。
夫の鼾をすぐ傍に聞きながら、最後はこの子に責め殺されたいと願いさえした。
京介は、八重の願いに応えようとしただけだ。
この子は、何も悪くない。
悪いのは、私なのだ・・・。
ほんの少し爪先に力を入れただけで、弾力性のある薄生地はあっさりと裂け目を拡げていく。
指で掻きむしりながらさらに拡げていくと、裂け目の下から懐かしい顔が現れた。
「京ちゃん!・・」
ついさっきまで一緒にいたはずなのに、ずいぶんと会ってなかった気がする。
京介は、八重を見おろしながら笑っていた。
いつもの優しい笑みだった。
八重は夢中でしがみついて、我を忘れたように唇を重ねていた。
「気持ちいいだろう?母さん・・・」
唇を離すと、京介が耳元で囁いた。
首の下に彼の腕が入っている。
ヒリヒリと痛む胸の上に、温かい身体が乗せられている。
「気持ちいいよ!京ちゃん、気持ちいいよ!!」
精一杯の力でしがみつきながら、八重は声の限り叫んでいた。
「まったく、すごいね。」
京介はズボンを穿きながら眺めていた。
八重は力尽きたように横たわっていただけだった。
膣から精液が溢れている。
精液はアナルからも噴き出していた。
京介に3回犯された。
短い時間のあいだに、3度も八重の中に射精したのだ。
どういうわけか、この子は外でするのを好む。
外でするときは、異常に興奮もしている。
「ずいぶんと血が出てるね。」
ズボンを履き終えると、頭の上に屈み込みながら、確かめるように八重の額に掛かった髪を除けた。
額から血が出ているのは気付いていた。
しかし、その血もほとんど乾きかけている。
乾いた血のせいで頬の辺りに引きつるような感覚があった。
「リアルだよ、でも、そんなに切れてはいないかな?」
自分でしておきながら他人事のように言う。
八重にもわかっていた。
まだ痛みはあったが、すでに血は止まっている。
京介に浅い傷だと教えられて、あらためてホッとした。
やはり女だから、顔に傷は作りたくない。
「これに当たったんだね。」
辺りを見回していた京介が、傍にあった石を拾うと、それを八重に見せてくれた。
こぶし台の石は、表面にべっとりと血が付いていた。
妙だと思った。
こんなに出血した覚えはなかった。
「大丈夫?」
尋ねる京介に、かすかに頷いてみたが、身体にまったく力が入らず、しばらくは動けそうになかった。
口を開くことさえも辛い。
横になった身体が冷たかった。
水はけの悪い河川敷は、土質が泥濘化していた。
衣服はすぐに水を吸い取って、下半分が濡れていた。
暴れた八重と京介の足跡が、そこら辺に散らばっている。
強い風が吹いていたせいもあって、ほとんど半裸に近かった八重は、すぐに寒さに震えるようになった。
「ほら、帰ろう。」
京介は手にしていた石を放り投げると、八重の腕を取って抱え上げてくれた。
足下が定まらず、京介により掛かっていなくては立っていることもできなかった。
「いいよ、迫真の演技だ。」
いい気なものだ。
誰のおかげでこんな目に遭っていると思っているのか。
京介に抱えられながら、遊歩道に向かって数歩歩いてみたが、とても1キロ先の車の所までは歩けそうにない。
そんな無理をしたら、本当にお腹の子が流れてしまう。
まだ、無事でいるのが奇跡なくらいなのだ。
八重の辛そうな表情を見て、京介もあきらめたようだった。
「車を取り入ってくるからか、ここで待ってて。」
こんな真夜中の薄気味悪い河川敷に一人取り残されたくはなかったが、仕方なかった。
京介はその場に八重を座らせると、「すぐに戻ってくるから」と安心させるように笑顔を向けてから、軽快に河原を駈けていった。
八重は、うずくまるように膝を抱えて、葦の藪の中に身を潜めていた。
風が強く、葦のざわめく音がうるさいほどに聞こえる。
ここは強姦魔がよく出没すると噂になっているところだ。
数年来、騒がれているが、未だに犯人は逮捕されていない。
ここ久しく噂を聞いていないが、今ここでばったり出くわしたりしたら、八重は恰好の餌食になってしまうだろう。
そんなことを考えたら、背筋が寒くなった。
そう言えば・・・。
強姦魔のことを考えていたら、ふと妙なことに気が付いた。
いつも強姦事件が噂になっていたとき、京介は実家に帰っていたような気がする。
強姦など、自分とは縁がないものと思っていたから今まで気が付かなかった。
今夜、京介に強姦の真似事をされて当事者となり、事件のことを親身に考えたとき、どうしてか京介の顔が頭に浮かんだ。
豹変した京介は、憐憫の情など欠片もない力で八重を殴っていた。
この事件を調べている夫は、被害者女性の救われない窮状を嘆いていた。
子細は教えてくれなかったが、彼女たちも相当な暴力によって乱暴されたことだけは確かなようだった。
まさか・・・。
無理に考えを封じ込めようとした。
そんなわけはない。
あの子に、そんな酷いことができるわけがない。
しかし、額の痛みが八重にそれを強く否定させてくれない。
息子を疑っている自分に気が付いて八重はたじろいだ。
嘘よ、そんなこと・・・。
無理に否定しても、どうしても心にわだかまりが残る。
風が強い。
見上げる夜空には、雲が勢いよく流れていた。
聞いてみるべきか・・・。
そんなことを考えていたときだった。
八重の視界に、きらりと光るものが目に映った。
流れの速い雲のせいで、月が顔を出そうとしていた。
遮る物がなくなった月の光に、見る間に周りが明るくなっていく。
八重は目を凝らした。
わずか数メートル先にそれはあった。
細いチェーンのようなものが光っている。
ネックレスだった。
どうしてこんな所に・・・
八重は、這うように四つん這いになりながら近づいた。
そして見てしまったのだ。
葦の藪の中に無造作に転がされ、血塗れの顔を歪めさせながら見開いていた女の目を。
「きゃああああああっ!!!」
それからは、よく覚えていない。
どこをどう通って戻ったのかも、わからない。
気が付けば玄関に立っていた。
夫の京太郎が八重を抱きしめながら泣いていた・・・。
※元投稿はこちら >>
 今日もチクニーしてます - オホ声とオモチャの排泄音、排泄完了してゴトっと下に落ちる音ってエロ声聞かせたいっ 00:51 レス数:55 HOT:53
今日もチクニーしてます - オホ声とオモチャの排泄音、排泄完了してゴトっと下に落ちる音ってエロ声聞かせたいっ 00:51 レス数:55 HOT:53  生理前はムラムラしちゃう……。 - 生理中でもクンニ出張しますよヽ(´∇`)ノ 08:02 レス数:39 HOT:21
生理前はムラムラしちゃう……。 - 生理中でもクンニ出張しますよヽ(´∇`)ノ 08:02 レス数:39 HOT:21 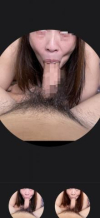 おばさん便女 - 素晴らしい便女ですね。公園便所で使いたい 07:10 レス数:18 HOT:18
おばさん便女 - 素晴らしい便女ですね。公園便所で使いたい 07:10 レス数:18 HOT:18  タコ足おもちゃで - 凄いねイッきながら何度もかけてくれ 07:42 レス数:15 HOT:15
タコ足おもちゃで - 凄いねイッきながら何度もかけてくれ 07:42 レス数:15 HOT:15  オカズセフ - ムチムチですねヘアを見せて 07:51 レス数:14 HOT:12
オカズセフ - ムチムチですねヘアを見せて 07:51 レス数:14 HOT:12