◯タワーマンションの夜(前)
東京の空に群青の幕が降りる頃、私はその高層マンションのエントランスに立っていた。
都心の一等地にそびえ立つ、総戸数三百を超える超高級タワーレジデンス。その最上階に、私の勤める会社の社長である篠田雅哉の住まいがある。
招かれたのは休日の夜だった。入社してまだ二年目の私が、社長の私邸に呼ばれる理由など皆目見当がつかない。ただ、誘いの電話口で社長の声は妙に穏やかで、時折後ろで女の笑い声が混じっていた。
フロントで名乗ると、すぐにドアマンがエレベーターを案内した。最上階の表示にランプが灯ると、静かに扉は閉まり、吸い込まれるように上昇していく。心臓の鼓動が高鳴るのが自分でもわかる。
迎えてくれたのは、社長の妻、篠田怜子だった。
「まあ、いらっしゃい。ようこそ、おいでくださいました」
その声に、私は思わず息を呑んだ。怜子夫人は噂に違わぬ美貌だった。三十八と聞いていたが、その肌はまるで薄絹のように滑らかで、透き通るほど白い。切れ長の目はわずかに伏し目がちで、艶やかな黒髪が肩にかかっている。華奢な首筋に浮かぶ鎖骨の線まで、完璧な造形だった。
黒のノースリーブのワンピースが、細身の身体の線をあらわにしていて、その奥に潜む肢体を想像せずにはいられない。
社長は応接室で待っていた。グラスに琥珀色の酒を傾け、穏やかな笑みを浮かべている。
簡単な挨拶を交わし、用意された料理に箸をつける。イタリアンのコース仕立てで、怜子夫人が手ずから作ったという。どの皿も見目麗しく、口に含むたび芳醇な香りが広がる。
「彼ね、会社でも評判なのよ。よく働いて、誠実で……」
社長は怜子夫人ににこやかに、饒舌に私の話をし、私はつい恐縮する。
食事は和やかに進んだが、その空気が変わったのは、デザートの皿が下げられた直後だった。社長がふとグラスを置き、低い声で口を開いた。
「実は、君に頼みたいことがあってね」
私は驚いて姿勢を正す。怜子夫人もグラスを持ったまま、微かに俯いた。
「私の……身体がもう、女房を抱ける状態じゃなくてな。手術して以来、どうにも不能になってしまった。だが……怜子には子を産ませてやりたい。家の跡継ぎを」
その言葉に、私は息を呑んだ。
「そこで君に頼みたい。今夜、怜子と……」
言葉を濁したが、その意味は明らかだった。社長はまっすぐ私を見据えた。その瞳は微かな熱を帯びている。
私は迷った。だが、この場で断れるはずもない。私は多くを聞かず、ただ「わかりました」と答える。
社長が静かに頷き、小さな声で「ありがとう」と言うと、私にベッドルームへ行くように促した。
長い廊下を抜けて突き当りのドアを開ける。案内されたベッドルームは、天井までの大きな窓から夜景が広がり、薄暗い間接照明が室内を艶やかに照らしていた。中央のキングサイズのベッドの脇に備えられた椅子に、ガウンを纏った怜子夫人が切なげな表情で座っている。
怜子夫人は私の姿を見ると立ち上がり、ガウンの帯をするりと解き、胸元が露わになる。
黒いカップレスブラが丸出しの乳房の形をより強調しながらも、美しいレースが白い肌を縁取る。
透けるほど薄いショーツは前が開いており、秘肉の襞が隠されずに露出している。
怜子夫人が完全にガウンを脱ぎ捨てると、その肢体は更に美しさを増した。谷間も腹部も滑らかな曲線を描き、小ぶりの乳房は形よく膨らみ、その先端に鎮座する大ぶりの乳首は目視だけで硬く敏感になっているのが見て取れる。
「……お願い、しますね」
怜子夫人は微笑みながら、そっと私のネクタイに手をかけ、緩めた。その指先はかすかに震え、吐息が近い。私は思わずその身体を抱き寄せた。
怜子夫人の身体は驚くほど冷たく、空調が利いているにも関わらず、その背はじっとりと汗ばんでいる。
「緊張してますか?」
「ん…うん…」
私は不憫に感じ、怜子夫人の頭を引き寄せ、肩口で包むように抱き締めて髪を撫でた。
「そりゃそうですよね…」
「ごめんなさい…」
「良いんですよ…」
暫しの会話で緊張が解けたのか、視線が合うと怜子夫人は自ら唇を求める。唇を重ねると、怜子夫人はわずかに首を傾け、舌先を差し出してきた。私はそれを絡め取り、湿った舌と舌が溶け合う。
唇の端から、透明な糸が引き湿った音が二人の耳に届いた。
私は掌で怜子夫人の柔らかな乳房がふわりと包み、指で円を描くようにゆっくりと乳首を撫でる。
「あっ……」
怜子夫人は背を仰け反らせ、小さく喘ぐ。乳首を口に含んで舌で転がし、軽く甘噛みすると、ぴくりと全身が震えた。
「感じやすいんですね。痛くないですか?」
「んっ…気持ち良い…」
手は滑らかな太ももを経て付け根を撫で、布地の割れ目からはみ出した肉襞へ及ぶ。僅かに触れるだけで夫人は身をくねらせ甘い吐息を漏らす。肉襞の狭間に指を沈めると、膣口から漏れ出た強くぬめった夫人の愛液が指全体に絡んだ。
ショーツを膝下まで降ろすと、怜子夫人は恥じらうように太ももを閉じたが、私はその膝を割り、ゆっくりと秘部に顔を寄せた。
「だ、だめ……そんな……」
微かな声を振り切り、舌先でそっと割れ目をなぞる。怜子夫人の肉襞は薄褐色で僅かに開き、隙間から覗く真紅の淫肉を縁取っている。膣口からはすでに白濁した愛液が溢れ、小さく窄んだ肛門まで垂れていた。
私は舌で流れ出た蜜を掬い、中心に顔を出す大きめの陰核を口に含む。
「ああっ…いやぁ…あっダメっ…」
腰が跳ね上がり、指が私の髪をきつく掴む。唇で秘唇を吸い上げ、舌で真珠を転がし続けると、怜子夫人の喘ぎは甘い悲鳴に変わる。
身体を反らし、何度も足先を震わせながら、怜子夫人は達した。細い肩が震え、冷たかった身体に熱を帯びる。
私はゆっくりと自らの衣服を脱いだ。怜子夫人は薄く目を開け、潤んだ瞳でそれを見つめる。
唇を重ねながら、ゆっくりと身体を重ねた。秘部は濡れて熱く、私を吸い込むようだった。
「う、うれしい……」
怜子夫人は小さく呟き、腰をゆっくりと揺らす。私はその細い腰を掴み、硬く反り立った肉棒を充てがうと静かに奥へと沈ませた。
肉棒は怜子夫人の肉襞を押し破りながら進み、こつりと子宮の縁に触れる。
私達は唇を重ねながら無意識下で腰を動かし、夫人の体内で亀頭と子宮を擦り合わせる。熱と湿り気に包まれ、二人の身体が溶け合った錯覚に陥る。
「怜子さん…」
「慎二くん…」
私達は手を握り合い、何度も名前を呼びながら体液を混ぜ合わせ、怜子夫人の胎内に何度も精を注いだ。
夜景の向こうには、東京の街が瞬いている。
その光の下で、禁断の情事は夜明けまで続いたのだった。
※元投稿はこちら >>
 寝る前に - 終わってから見たけど、マジでいいカラダでビビった 02:00 レス数:68 HOT:68
寝る前に - 終わってから見たけど、マジでいいカラダでビビった 02:00 レス数:68 HOT:68 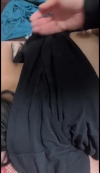 嫁に悪遊 - 是非お願いしますiianbai 06:24 レス数:20 HOT:12
嫁に悪遊 - 是非お願いしますiianbai 06:24 レス数:20 HOT:12