久しぶりに実家に帰ると、風呂あがりなのか、ワンピースタイプのローブをまとった姉がソファーに腰掛け、屈むようにして足の先を触っていた。
「どうしたの」
「足の指の先にトゲが刺さって抜けないのよ、お風呂に入ってふやかしたら、とれるかなと思ったんだけど」
姉の足を近づいて見ると左足の親指に小さなとげが刺さっていた。今年30歳になる姉の足は、思ったよりも小さくかわいらしく、紫色のペディキュアが塗ってあった。
「蜂蜜塗ればいいよ」
蜂蜜を塗って10分ほど経つとトゲの先が顔を出したのでピンセットでとってやった。姉の白くすらりと伸びた足を触っているうちに何故か妙な興奮を覚えた。
「蜂蜜とってあげる」
すべすべしたふくらはぎを両手で持ち、親指を口に含み舐めると、甘い蜜の味が口中に広がった。
「何やってるのよ。くすぐったいでしょ」
引っ込めようとした足をふくらはぎを押さえるようにして抱え込み、ひたすら舐め続けた。指、足首、足の裏。今までのセックスで、太腿から局部まではあっても女性の足先を舐めた事などなかった。
「やめてよ。変だよ」
姉は、ダメダメと言っていたのが、5分も舐め続け、舐めめ回す所がふくらはぎに達した時には、目をつぶり身をまかせていた。膝を舐めながら姉のすべすべとした弾力のある太腿に手をやり、ゆっくりと両手で挟み込むようにゆっくりと撫でまわした。
太腿を舐めるために、姉の足を持ち上げ、ソファに寝かすようにし体勢をかえ、ローブの裾を巻き上げ広げた。太腿の間に頭を入れると、いままで嗅いでほんのりとした石鹸の香り以外に、くらくらするような甘い香りが姉の股間から立ち上ってきた。
そう、ずっと姉の足に憧れていた。中学を卒業するまで続けていた、クラシック・バレエのすらりとした姉の足、高校時代にテニス部に入った姉の足。ずっと憧れていた。
「もう、ダメ。ね」
ソファから身をお越し逃げようとする姉の上に、覆いかぶさり、抱きしめた。顔を背けた姉の首筋に、吸い付くようにキスをし舐めあげていく。真っ白なうなじ、そして少し赤みを帯びた耳たぶを丹念に舐めあげていくと、姉の早くなった呼吸は、少しずつ喘ぎのようになっていった。
下半身のはち切れんばかりに大きくなったものを,姉の中心部にあてがいゆっくりと、こ擦り付けるように、動かしていく。
「だめなんだって・・・いけないんだって・・・あぁ・・・お願い」
喘ぎの中の姉の声は、興奮を大きくしていくだけだけだった。
胸を包んでいたローブを開き、姉の乳房を舐め始めた時には、着ていたものは、脱ぎ捨て生まれたままの姿で、白いショーツだけになった姉に重なっていった。決して大きくはないが、年相応のふくよかさのある乳房は、やわらかく上に突き出した乳首を口に含み、乳児のように吸い続けた。
「見せて」
姉のショーツを脱がそうと手をかけたが、姉は抵抗することはなかったが、両手で顔を隠した。真っ白な体の中心部に薄い草原が眩しかった。そこは姉の中心部から、流れ出た液体により潤い、光っていた。
口をつけ、舐めあげていく、突起の部分を舌でテイスティングするように舐めると、姉の喘ぎは、驚くような大きな声になった。
突然襲ってきた衝動のままに、予告すすることもなく姉の中に体をねじ込んだ。
「あーあ・・あーーーーーーーーだめだめだめ」
猛烈に狂ったように前後に体を動かしていた、幸福感に包まてている、人生で最高の幸福感。
唐突に叫びののような声とともに姉の体が熱くなると、動けないほどに強烈な締め付けが襲ってきた。
荒い息をしている姉を見下ろすと興奮の中に、ほんの少しの冷静な自分が顔を出したが、姉の締め付けがゆっくりと溶け出すとそれはどこかへ無くなってしまった。この幸福を離すことはできない、どんな罰、どんな犠牲を払っても、このために生きてきたんだ。
ゆっくりと動きを再開し、初めて姉の唇にキスをしようとしたとき、姉の手が首に巻きつき、姉の熱い舌が口の中に入ってきた。言い難いおいしさ、なんて素晴らしいキス。
2度目の姉の締め付けは、解き放った分身たちとともに体のすべてを吸い込まれるように長く極上の幸福を与えてくれた。
 (無題) - はじめまして素敵な体ですよ!かわいい声とピチャピチャ音で興奮させてもらってます。 08:45 レス数:72 HOT:71
(無題) - はじめまして素敵な体ですよ!かわいい声とピチャピチャ音で興奮させてもらってます。 08:45 レス数:72 HOT:71 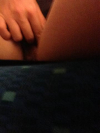 新幹線オナニーしました。 - 東京近郊民です便女さんを優しく抱いてあげたいのですが次はいつこちらに戻って来ます 09:30 レス数:49 HOT:48
新幹線オナニーしました。 - 東京近郊民です便女さんを優しく抱いてあげたいのですが次はいつこちらに戻って来ます 09:30 レス数:49 HOT:48  (無題) - この子動画に移動してますよめちゃくちゃえろい 04:16 レス数:45 HOT:45
(無題) - この子動画に移動してますよめちゃくちゃえろい 04:16 レス数:45 HOT:45