今日の舞台は、
女装子と純男が集まる発展場ーー
女装のボクが他の女装をオナホ扱いしてハーレムを築く。そんな話。
プレイルームに集まったのは、男も女装子も合わせて9人ほど。
照明は落とされ、ソファとベッドが散在するその空間は、淫靡な笑いと期待の空気で膨張していた。
ボクは最初、ただの「応援役」のつもりだった。
興奮とは裏腹に、緊張で萎えた誰かの竿を手コキや足コキで慰めてあげて、背中を押してあげるーー雰囲気を温める程度。
メスネコのボクはそういう、触れて甘やかす役割が一番しっくりくるから。
だが不意に飛んできた言葉で空気は一変する。
「銀河猫、竿やれるか?」
一瞬、場の視線が集まる。
断ろうとした。ボクの竿はレッドブル缶と同じ太さで、それはあまりにも危険すぎる。普段からボクのちんちんの大きさは皆んなに対してネタとして喋っていたからこそ、今は冷や汗をかいている。
けれど「やれない」とは言い切れず、息を呑むうちに雰囲気に呑まれて――竿対応させられてしまった。
そもそもメスモードのボクは中々勃たない。
これはボクの中のオスとメス、タチとネコで人格が異なるから制御が効かないのだ。
仕方なく、ポケットからバイアグラを取り出し、一錠をそのまま喉へと落とす。
十分も経たぬうちに、ボクの股間は血潮を集め、皮膚が裂けるような勢いで硬直していく。
布越しにもはっきりわかる、凶悪な膨張。
そして――勃てば勃つほど、ボクの中で変化が始まった。
ボクの中の甘えて奉仕するメスネコの人格は追い出され、
代わって、目を血走らせた獣のようなメスタチが奥底から這い上がってくる。
目の前の穴を壊すことしか考えられない。
薬でふらふらしながら心ここに在らずなボクを他所に、この凶悪そのものの具象化を皆んなが見て息を呑む。
ボクの中の理性は叫ぶ。「怪我をさせるな」。
だがこの獣は笑う。「玩具のように弄べ」。
その相克のまま、ボクは最初の女装子を寝バックで捕らえる。
逃げ場を封じ、肩を押さえつけ、背後から腰を打ち込む。
長いストローク、そして鼠蹊部ごと押し潰すような衝撃的なピストン。
「ひっ……! あ…あ゛あ゛っ……!」
挿れられた瞬間から、女装子は叫んだ。
悲鳴に近いその声。それでも「やめて」とは言わない。
――ならば、それは肯定だ。
だって、ボクのちんちんを拒む権利は、君の側にあるはずなのだから。
だから奥の奥まで。
戻らなくなりそうな太さと長さで蹂躙していく。
やがてボクの理性は霞み、腰は自動機械のように振られ続けた。
愛なんて欠片もない。
ただ自分の快楽を貪る獣。
周囲の視線を感じる。
純男も、他の女装子も、息を呑んで固まっている。
「銀河猫の凶悪すぎる禁忌の竿が挿し込まれたらどうなるのか」
――その答えを、彼らは恐怖をもって見せつけられていた。
湿った肉を叩く音、粘液の混じる打撃音。
部屋には言葉がない。
響くのは、ボクの腰と、穴の悲鳴だけ。
一つの穴が限界を迎え、ベッドに崩れ落ちる。
ボクは止まらない。
次の穴へ。さらに次の穴へ。
それは性交ではなかった。
自慰の延長、容赦のない道具の使用。
支配と蹂躙の物量。
やがて三人の女装子がベッドに転がる。
足は震え、膝は笑い、復活しても立ち上がれない。
「戦闘不能」という言葉が最もふさわしかった。
――苦しむか、死ぬか。
その二択を突き付けるかのように、ボクの竿はなおも硬直している。
その姿を見て、誰もが畏怖と崇拝を入り混じらせた目をしていた。
恐怖に支配されながらも、視線は逸らせない。
三回戦目を迎える頃には、正直、ボク自身が死にかけていた。
それでも、腰は動き、獣は吠える。
――そして。
蹂躙された三人の女装子は、戦闘不能になりながらも、なおボクに縋り付いてきた。
呻き声と共に執拗な求愛をぶつけてくる。
彼女たちの手がボクを絡め取る。
でもボクはそれを優しく愛で、そして引き離す。
それは甘露のように甘く、劇物のように危険。
だがボクの築いたこの空間では、それすら否定されない。
彼女たちの夢は、きっとこの夜に叶えられたのだろう。
支配に蹂躙され、壊され、なお抱かれることを願う――
そんな夢を。
 彼撮り動画 - ごゆっくり、おやすみくださいませ… 23:45 レス数:104 HOT:49
彼撮り動画 - ごゆっくり、おやすみくださいませ… 23:45 レス数:104 HOT:49  吸引してデカ乳首♡ - またねーー!!、、 03:37 レス数:32 HOT:29
吸引してデカ乳首♡ - またねーー!!、、 03:37 レス数:32 HOT:29  どうですか? - ちせちゃんの乳輪舐め回したいわ 01:21 レス数:29 HOT:24
どうですか? - ちせちゃんの乳輪舐め回したいわ 01:21 レス数:29 HOT:24 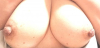 (*ˊ˘ˋ*)。♪:*° - おっぱい星人だけど自分もすっきりしたいな 03:13 レス数:21 HOT:20
(*ˊ˘ˋ*)。♪:*° - おっぱい星人だけど自分もすっきりしたいな 03:13 レス数:21 HOT:20  52歳おばさんです - 出遅れました相変わらず最高です 00:39 レス数:16 HOT:16
52歳おばさんです - 出遅れました相変わらず最高です 00:39 レス数:16 HOT:16